飲酒運転やそれによる事故を防止するためには、アルコールチェッカーの正しい使い方を把握しておくことが非常に重要です。本記事では、アルコールチェッカーの仕組みを押さえた上で、アルコールチェッカーの正しい使い方や注意点、適切な選び方を解説します。
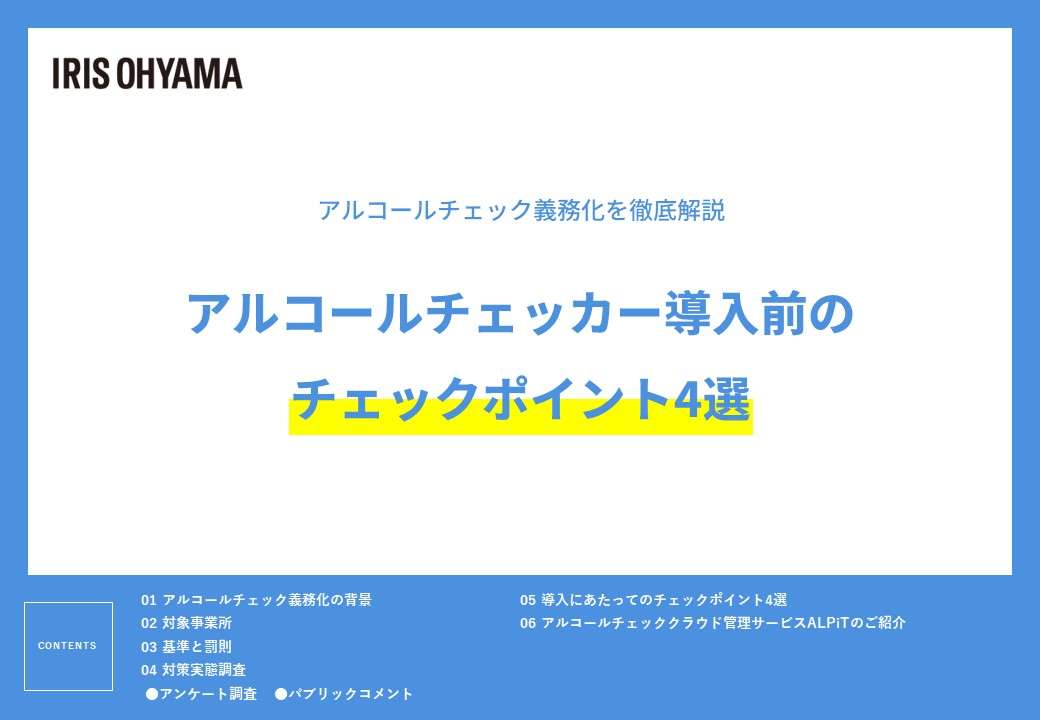
アルコールチェッカーとは

そもそもアルコールチェッカーとはどのようなものなのでしょうか。使う用途やアルコールチェックができる仕組み、種類について解説します。
体内の残留アルコール濃度を計測するための機器
アルコールチェッカーは、酒気帯び・飲酒運転防止のために使われる機器。アルコールチェッカーを使って、業務で車を使用する人の酒気帯びを確認します。
道路交通法が改正され、2022年以降には一定台数以上の白ナンバーを保有する事業所でも、アルコールチェックの実施と記録が必要になりました。それに伴い、アルコールチェッカーの使用が義務化されています。
呼気に含まれるアルコールを測定する
アルコールチェッカーに息を吹きかけ、体内に残ったアルコール濃度を数値化します。
アルコールを摂取すると、胃や小腸で吸収され、肝臓でアルコールを分解するもの。しかし分解されなかったアルコールは血中に入り肺に行くため、呼気からもアルコールが検出されるのです。
この仕組みを利用して、呼気に含まれるアルコールを測定します。
アルコールチェッカーの種類は豊富
アルコールチェッカーの種類は豊富にあります。そのため、用途や精度、使い勝手に合わせて適したものを使うのが望ましいでしょう。
主な種類は以下の通りです。
| センサー | 半導体式ガスセンサー、電気化学式センサー |
| 測定方式 | 吹きかけ型、ストロー型、マウスピース型 |
| タイプ | 据え置き型、携帯型 |
アルコールチェッカーの使用手順
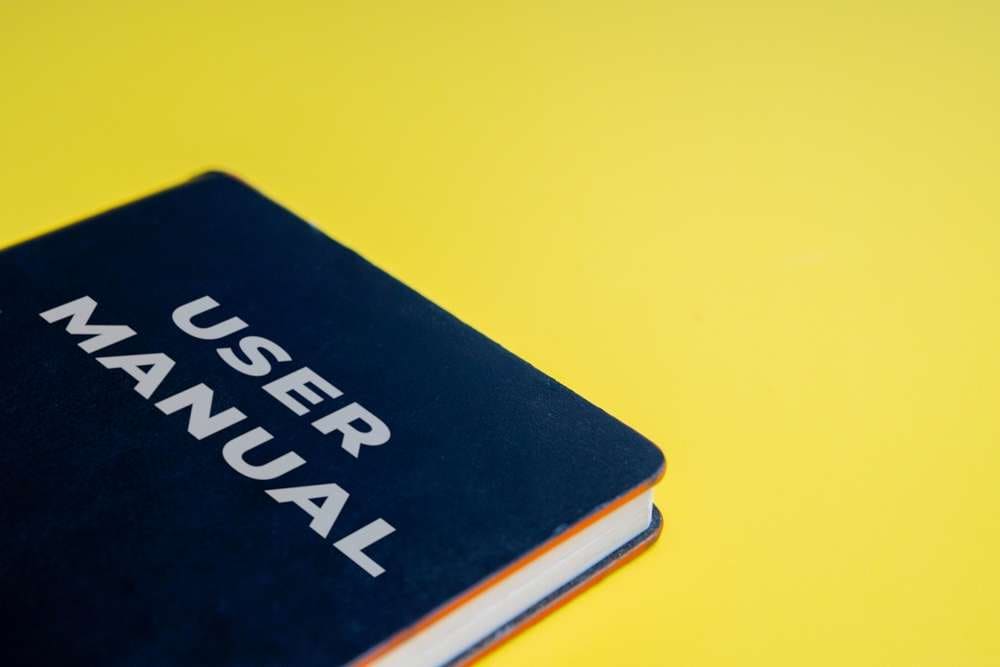
アルコールチェッカーの使用手順は以下の通りです。
1.電源を入れる
アルコールチェッカーの電源を入れ、スタンバイ状態になるのを待ちます。
2.準備完了まで待つ
機種によっては、内部センサーを温めるためのカウントダウンが始まります。表示が「測定OK」になるまで待ってください。
3.正しく呼気を吹き込む
マウスピースに向かって、指定された時間、一定の強さで息を吹き込みます。吹き込む時間は、通常5秒程度です。時間が短すぎたり息が弱すぎたりすると、正確に測定できません。
4.測定結果を確認する
吹き込みが完了すると、数秒以内に血中アルコール濃度(BAC)または呼気中アルコール濃度が画面に表示されます。基準値以上の場合は、運転や作業を控えましょう。
アルコールチェッカーの正しい使い方

ミスがないよう、アルコールチェッカーの正しい使い方を把握しておくことが大切です。測定の仕方や測定するタイミング、息の吹きかけ方などを解説します。
原則として確認者が立ち会う
アルコールチェッカーを使用する際は、原則として確認者の立ち会いが必要。アルコールの数値だけではなく、運転者の顔色や呼気などを、実際に目視でチェックする必要があるためです。対面でチェックすることで、精度や信頼性が上がり、不正防止につながります。
ただし、リモートワークや直行直帰などによって対面でのチェックが難しい場合もあるでしょう。その場合は、携帯用のアルコールチェッカーの使用と、携帯電話やPCによるビデオ通話で、測定結果に加えて運転者の様子を確認します。
運転する前後2回測定する
アルコールチェッカーで測定するタイミングは、運転する前と後の2回。厳密には、業務開始前、業務終了後でもかまいません。
運転前・業務開始前にチェックすることで飲酒運転の防止に、運転後・業務終了後にチェックすることで、業務中に飲酒していないことが証明されます。
機器の仕様に合わせてしっかりと息を吹きかける
アルコールチェッカーは、センサーが呼気に含まれるアルコールを感知する仕組み。仕様や吹きかける時間は機種によって異なりますが、例えば、「ピピっと音がするまで4〜5秒間しっかりと息を吹きかける」など、しっかりと息を吹きかけましょう。
誤検知防止のため、風が当たる場所を避けて息を吹きかけることも大切です。
アルコールチェッカーを使う際の注意点

アルコールチェッカーを使う際は、いくつかの注意点を守る必要があります。守らなければ、正しい測定結果が出ない他、アルコールが検知される場合もあるので注意してください。
測定前にうがいをする
口の中に食べ物が入っていると、正しく測定できません。検知の前に、水かお湯でしっかりとうがいをするか飲むようにしましょう。
なお、うがいの際はアルコールを含んでいる洗浄液を使うのは避けてください。アルコールが検知される場合があります。
測定前に飲食や喫煙をしない
測定前に飲食や喫煙をすると、正しく測定できない可能性があります。飲食した場合は、飲食後15〜20分くらい経過してから計測することで、より正確な数値を得られます。
また、アルコールを含んだ食品の摂取には注意が必要です。キムチなどの発酵食品やエナジードリンク、ミントガムなどを食べた後だと、アルコールチェッカーが反応することがあります。
喫煙も誤検知につながる可能性があるので、チェック前の喫煙は控えてください。
前日の飲酒に配慮する
意外に見落としがちなのが、前日に飲むお酒です。夜遅い時間までお酒を飲んでいた場合、摂取したアルコール量が多いと、翌日のアルコールチェックでアルコールが検知されることがあります。
アルコールの分解や代謝は個人差があるもの。人によっては、分解に時間がかかり翌日にもお酒が残っている場合も考えられます。自分のアルコール適正量に加え、飲酒を終える時間帯などを把握することが大切です。
車に乗る前日は、飲酒しない、早い時間で切り上げる、少量の飲酒にとどめるなど意識しましょう。
アルコールチェッカーの使用期限を確認する・メンテナンスをする
アルコールチェッカーには使用期限があります。製品によってまちまちですが、一般的には半年〜1年が使用期限で、そのうち何回使えるかも決められています。
法令を守って正しく計測するためにも、アルコールチェッカーを定期的にメンテナンスしましょう。
アルコールチェッカーの選び方

使用するアルコールチェッカーは、国家公安委員会が定めた「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」であることを満たしていなければなりません。要件を満たしているものの中から、使用シーンや使い勝手、各方式を基準に選びましょう。
参照:警察庁
形状で選ぶ
使い勝手や使いやすさを重視するなら、据え置き型か携帯型どちらが良いかを選びましょう。
<据え置き型>
事業所に置いて使用するタイプです。耐久性が高く、センサーさえ交換すれば、本体自体は長く使えます。運転者が業務前に事業所に寄る場合は、据え置き型がおすすめです。
<携帯型>
長距離を運転するドライバー、直行直帰が多い人に向いている形状です。小型で持ち運びしやすく、製品の価格自体も低め。使用場所を選ばないのがメリットです。
計測方式で選ぶ
測定方法は以下の3つです。
<吹きかけ式>
本体の吹き込み口に直接呼気を吹きかける方法。手軽に使用できるのがメリットです。
<ストロー式>
機器にストローを挿して息を吹き込みます。一直線に息が送り込まれるので、精度が高め。また、風など周囲の影響を受けにくいとされています。
吐いた息を逃さないのもメリットです。
<マウスピース式>
機器専用のマウスピースを付けて息を吹き込みます。メリットはストロー式と同様です。
検知方式で選ぶ
検知方式は主に以下の2つです。
<半導体式ガスセンサー>
電気抵抗値の変化を感知して測定する方式です。息を吹きかけることで付着した酸素量で、電気抵抗値の変化を計測します。アルコールを含んでいると酸素量が減り、電気抵抗値は低くなります。
低価格で、短時間で計測できるなどのメリットがある一方、アルコール以外にも反応する場合があるため注意が必要です。
<電気化学式(燃料電池式)センサー>
アルコールによって電気を発生させて測定する方式です。呼気に含まれるアルコールが多いほど、電流が強くなり電気の発生量が増えます。
価格が高く測定時間が長いのが難点ですが、ほぼアルコールにしか反応せず精度が高いのが魅力です
記録・管理の仕方で選ぶ
アルコールチェックの結果の記録や保管も義務付けられています。記録を紙ベースで行うかクラウド上で行うかによって、選ぶ製品が異なります。
<アナログの場合>
紙ベースでの記録や管理は、メモのような感覚で記録できるので非常に手軽です。一方で記入漏れなどの人為的ミスや、管理の手間が生じてしまいます。
<クラウドの場合>
アルコールチェッカーとアプリなどを連携させて、測定→記録→保管までを流れで行えるのが特徴。手作業が少ないためミスが減り、保管の手間もかかりません。
アルコールチェック義務化についておさらいしよう

アルコールチェッカーの運用を検討しているなら、アルコールチェック義務化についても押さえておきましょう。
白ナンバーへのアルコールチェック義務化は、トラックによる飲酒運転事故をきっかけに、2022年4月と2023年12月の二段階に分けて施行されています。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
アルコールチェッカーを選ぶなら、使い方が簡単な「ALPIT」

「ALPiT」は、アルコールチェックをした後の記録簿をクラウドで一括管理ができる、クラウド管理サービスです。計測結果は自動的にクラウド上で管理されるので、時短で管理業務が完了できます。
測定時には、自動的に顔写真を撮影。測定結果とともに顔写真がクラウドに送信されるため、不正を防止できるのも特徴です。検知器付きプランなら、検知器の寿命を迎える前に交換用のセンサーが届くので、常に正常な状態で検知できます。
〈ALPiTの詳細はこちら〉

アルコールチェッカーの使い方を把握して、正しく測定しよう

酒気帯び運転や飲酒運転防止のためには、アルコールチェッカーで正確に測定することが大切。そのためには、正しい使い方を知っておく必要があります。使用するタイミングや測定方法、また測定時の注意点をしっかり理解した上で、アルコールチェックを行いましょう。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


