2022年以降、一部の事業者に対して運転前のアルコールチェックが義務化されました。飲酒後、どの程度の時間を空ければ運転が可能か気になる方も多いでしょう。本記事では、飲酒後の運転再開可能な時間やアルコールの分解速度、計算方法を詳しく解説。さらに、飲酒運転の罰則やアルコールチェック義務化についても解説します。
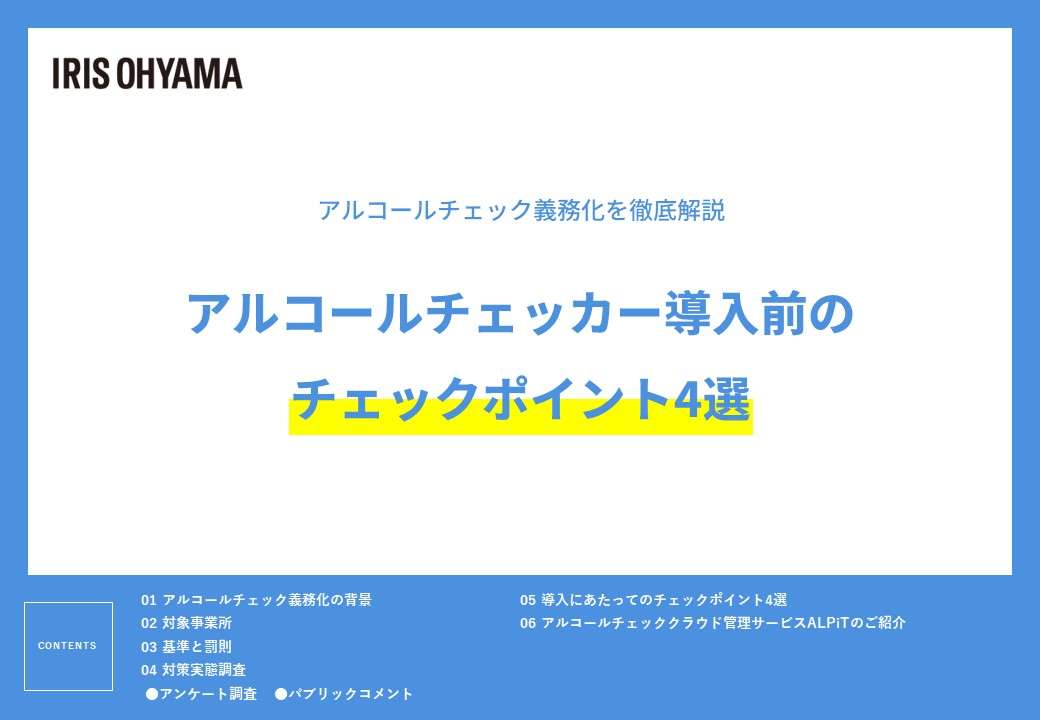
飲酒後、どれくらいの時間で運転が可能?

飲酒後に運転が可能になるまでの時間には個人差があり、アルコールの分解速度によって大きく異なるため、正確な予測は困難です。一般的には、アルコール1単位(約20g)の分解に平均して4〜5時間程度かかるとされています。しかし、この速度は体重や性別、年齢、体調、飲酒量などによって大きく左右されます。
さらに、睡眠中はアルコールの分解が遅れる傾向があるため、睡眠時間を過信せず、十分な時間的余裕を確保することが大切です。運転の予定がある日は、飲酒を控えるか、分解時間を逆算して行動するなど、慎重な判断が求められます。
アルコールの吸収と分解のメカニズム

アルコールは、胃や小腸で吸収され、血流に乗って全身へ運ばれます。体内に取り込まれたアルコールは主に肝臓で酵素によって分解されますが、処理しきれなかった分は脳にまで到達し、中枢神経を麻痺させます。これにより、酔いや眠気、判断力の低下などの影響が現れるといった仕組みです。
分解が追いつかない状態が続くと、脳の機能に影響を及ぼし、運転や判断行動に深刻な支障をきたすおそれがあるのです。
出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールの吸収と分解」
アルコールが分解される速度はどれくらい?

アルコールが体内で分解される速度は、飲酒量や個人の体質によって異なります。ここでは、把握しておきたいアルコールの単位やアルコール分解に必要な時間について解説します。
飲酒量の目安:アルコール「1単位」とは
アルコールの「1単位」とは、純アルコール約20gを含む飲酒量の目安を指します。飲酒量を単位で把握することで、体内でアルコールが分解されるまでにかかる時間のおおよその目安を立てやすくなります。
なお、近年では「1ドリンク=約10g」という基準も使われるようになっています。
| 種類 | 内容量の目安 | アルコール度数の目安 | 純アルコール量 |
| ビール | 500ml(中瓶1本/ロング缶1本) | 約5% | 約20g |
| 日本酒 | 180ml(1合) | 約15% | 約22g |
| ワイン | 200ml(グラス2杯) | 約12〜13% | 約19〜21g |
| ウイスキー | 60ml(ダブル1杯) | 約40% | 約20g |
| チューハイ | 350ml(缶1本) | 約7% | 約20g |
| 焼酎 | 110〜180ml(0.6〜1合) | 約20〜25% | 約18〜36g(種類により変動) |
アルコール「1単位」の分解にかかる時間
一般的に、体重が60〜70kg程度で、特別にお酒に弱くない人の場合、1時間で処理できるアルコール量は約5gとされています。つまり、純アルコール「1単位」(約20g)を体内で分解するには、およそ4時間かかる計算になるのです。
例えば、ビール中瓶1本(アルコール約20g)を飲んだ場合、それを完全に代謝・排出するには少なくとも4時間以上の時間が必要です。ただし、これはあくまで目安であり、アルコールの分解速度には体質や体調などによって大きな個人差がある点に注意が必要となります。
アルコールが抜けるまでの時間を計算する方法

アルコールがどれくらいで体から抜けるのかを知るためには、純アルコール量と体重当たりの計算が必要です。計算方法を詳しく解説します。
1.純アルコール量の計算
アルコールが体から抜けるまでの時間を把握するためには、まず自分が飲んだ量に含まれる純アルコールの量を知る必要があります。純アルコール量は、以下の計算式で求めることができます。
酒の量(ml) × アルコール度数(%) ÷ 100 × 比重(0.8)= 純アルコール量(g)
例えば、ビール500ml(中瓶1本/ロング缶1本)、アルコール度数5%の場合は、
500 × 0.05 × 0.8 = 20
となり、純アルコール量は20gです。このようにして、実際に摂取したアルコールの量を数値で把握することができます。
2.アルコール分解に必要な時間の計算方法
純アルコール量が把握できたら、次に体内からアルコールが抜けるまでの時間を計算します。計算式は以下の通りです。
純アルコール量(g)÷(体重(kg)×0.1)
先述したように、アルコール度数5%のビールを500ml飲んだ場合、純アルコール量は20gです。体重60kgの人の処理時間は、以下の通りです。
20 ÷(60×0.1)=約3.3時間
同じ500ml缶を2本飲めば、摂取量は40gとなり、分解には約6~7時間が必要になります。さらに日本酒や焼酎を続けて飲んだ場合は、当然ながら分解にかかる時間も長くなるということです。
また、睡眠中は分解が遅れる傾向があるため、就寝をはさんでも十分な時間的余裕を確保することが大切です。分解速度には体質や体調による個人差があるため、あくまで目安として参考にしましょう。
飲酒運転の罰則

アルコールが体内に残っていると、中枢神経系を麻痺させ、判断力の低下を引き起こします。その状態での運転は、重大な事故につながる危険性があるため、注意が必要です。次に、飲酒運転に関する罰則について確認しましょう。
運転者に対する罰則
飲酒運転に対する罰則は非常に厳しく定められており、違反の内容によって行政処分や刑事罰が科されます。アルコールの基準値に応じて処分内容が変わる「酒気帯び運転」と、状態によって判断される「酒酔い運転」とで区別されている点に注意が必要です。違反点数も加算され、一定以上になると免許の停止や取消処分の対象になります。
以下は、主な違反種別ごとの処分内容です。
| 違反種別 | アルコール基準値 | 行政処分 | 罰則 |
| 酒気帯び運転 | 0.15〜0.25mg/L未満 | 免許停止(90日) | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 0.25mg/L以上 | 免許取消(欠格期間2年) | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 数値基準なし(ふらつき・ろれつなど) | 免許取消(欠格期間3年) | 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
なお、「酒酔い運転」は、アルコール濃度ではなく、歩行のふらつきやろれつが回らないといった運転者の状態に基づいて判断されます。
運転者に関わる周囲の人の罰則
飲酒運転は、運転者本人だけでなく、それに関与した周囲の人にも法的な責任が問われます。車を貸した人、酒を提供した人、さらには同乗していた人まで、状況によっては厳しい罰則が科される可能性があります。
車両を提供した場合も、運転者と同等の処罰を受けるケースがあるため注意しましょう。
以下は、飲酒運転に関与した人物ごとの主な罰則の一覧です。
| 関与者 | 酒酔い運転の罰則 | 酒気帯び運転の罰則 |
| 車両提供者 | 懲役5年以下 または 罰金100万円以下 | 懲役3年以下 または 罰金50万円以下 |
| 酒類提供者 | 懲役3年以下 または 罰金50万円以下 | 懲役2年以下 または 罰金30万円以下 |
| 同乗者 | 懲役3年以下 または 罰金50万円以下 | 懲役2年以下 または 罰金30万円以下 |
「飲んだ本人だけが悪い」とは限らず、関わった人すべてが責任を問われる可能性があります。飲酒運転を防ぐには、周囲の適切な対応も欠かせません。
アルコールチェックの義務化について

現在、一部の事業者ではアルコールチェックの義務化が始まっています。義務化の概要と2023年12月から始まったアルコールチェッカー(アルコール検知器)による確認の義務化について解説します。
アルコールチェック義務化の概要
2022年4月から、一定台数以上の白ナンバー車両を保有する事業者にもアルコールチェックの実施が義務化されました。これに伴い、安全運転管理者の選任に加え、運転者の酒気帯び確認やその記録の保存が必要とされています。
もともとは緑ナンバー(営業用車両)のみが対象でしたが、制度の拡大により白ナンバー(自家用車両)にも対象が広がりました。業種を問わず、飲酒運転を防止するための管理体制強化が進められています。
▼内部リンク
同月記事「アルコールチェック義務化 対象者」
同月記事「白ナンバー アルコールチェック」
2023年12月からアルコールチェッカーによる確認の義務化
2023年12月から、アルコールチェッカーの使用による確認が義務化されました。これにより、これまでの目視確認に加え、機器を用いた酒気の測定が必須となるよう制度が改定されています。こうした改正は、飲酒運転の抑止力を一層高めるために講じられた措置です。
アルコールチェッカーは営業所に常備し、出張や直行直帰といった遠隔地での運転にも対応できる体制を整える必要があります。アルコールチェッカーは常に使用可能な状態で保管し、測定結果は記録のうえ1年間保存することが求められます。
▼内部リンク
同月記事「アルコールチェック義務化」
道路交通法全項目対応!アイリスオーヤマの「ALPiT(アルピット)」

ALPiT(アルピット)は、アルコールチェック義務化に対応した高精度な携帯型アルコールチェッカー(アルコール検知器)です。コンパクトで持ち運びしやすく、息を吹きかけるだけで簡単に測定できます。
測定結果や日時は端末本体に最大50件まで保存でき、専用アプリと連携すれば、データを自動でクラウドに記録することも可能です。
アルコール成分のみに反応する設計のため、他の物質による誤検知を防止。さらに、顔写真の記録機能を備えており、なりすましなどの不正使用も防げます。複数拠点での使用にも対応しており、全拠点のデータを一元管理できるため、記録業務の手間を省き、管理負担を大幅に軽減します。
アルコール分解の時間を知り、安全運転を心がけよう
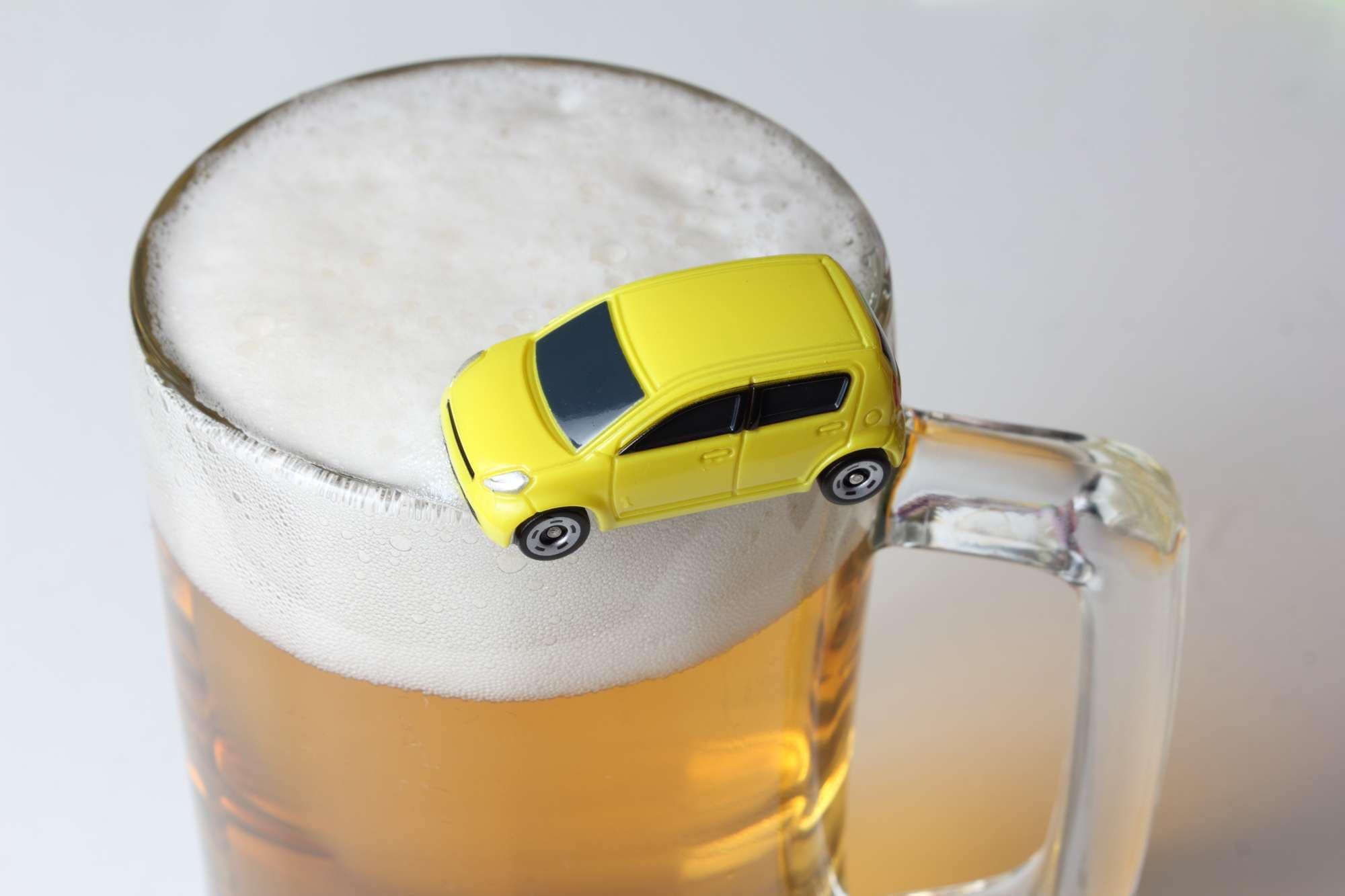
アルコールは体内で分解されるのに時間がかかるため、飲酒後すぐの運転はもちろん、数時間経過していてもアルコールが残っている可能性があり、重大な事故のリスクを高めます。
現在、一定の条件を満たす事業者にはアルコールチェックの義務があり、正確な測定ができる高性能なアルコールチェッカーの導入が推奨されています。
飲酒後は「完全にアルコールが抜けてから運転する」という意識をもち、事故の防止と法令遵守を心がけましょう。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


