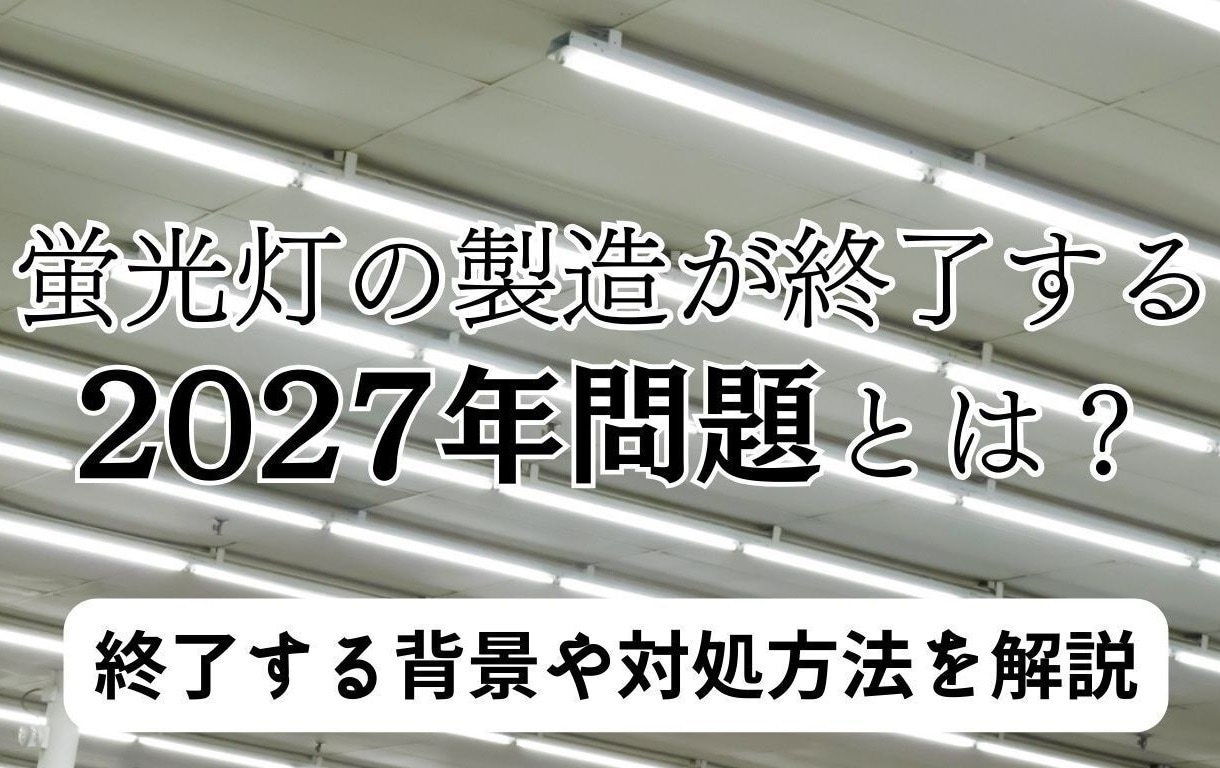点検を行って初めて、非常灯が故障していることに気付くケースがあります。非常灯にはさまざまな種類があり、交換する際には設置場所に合ったものを選択しなければなりません。
本記事では企業・事業者の方に向けて、非常灯の種類や選び方、誘導灯との違いまでを徹底解説。また、非常灯を選ぶコツやおすすめの商品もご紹介します。

非常灯とは?

まずは、あらためて非常灯とはなにかを整理しましょう。
■停電時に避難を助けるための照明
非常灯とは、災害や火災で停電が起きた際に、安全に避難できるように照らす器具です。
非常灯は独立した電源又は蓄電池を使用し、電力供給が途絶えても点灯します。そのため、停電時でも建物内を照らし、安全な避難を可能にします。
また、非常灯は避難だけでなく、火災時に消防隊が救助活動を行う際にも照明として役立ちます。緊急時に人の生命を守る重要な役割を担っていると言えるでしょう。
なお、非常灯は、建築基準法で一定の建物に設置が義務付けられています。設置基準については次項の「非常灯の設置基準」で詳しく解説するので、あわせて参考にしてください。
■誘導灯との違い
非常灯と誘導灯は、用途に大きな違いがあります。
非常灯は停電時に避難・救出を支援するための非常用の照明です。一方、誘導灯は非常口や避難経路を照らし、出口まで案内する役割があります。
また、両者は見た目も異なります。非常灯は通常の照明と似た外見をしていますが、誘導灯はわかりやすいアイコンを使います。たとえば、施設内でよく見かける緑色のライトの逃げる人のアイコンや矢印が表示される照明は、誘導灯の特徴です。
非常灯の設置基準

非常灯には法令で定められた設置基準があります。該当する建物は厳守しなければなりません。
建築基準法施行令第126条の4では、次の建物には非常灯の設置義務があると定めています。
- 特殊建築物(百貨店や映画館など)
- 3階建て以上・面積500平方メートル以上の建物
- 延面積1,000平方メートル以上の建物
- 採光可能な窓が設置されていない建物
万が一の際に建物内にいる従業員や利用者などの安全を守るために、非常灯の設置や定期的な点検、保守は建物を所有する企業・事業者の義務と言えます。
非常灯の種類

非常灯には点灯形態・電源・光源にいくつかの種類があります。設置場所によって適切なパターンが異なるため、設置・交換する場合にはそれぞれの種類を把握することが重要です。点灯形態・電源・光源に分け、各種類を解説します。
■点灯形態による分類
非常灯の点灯形態とは、どのタイミングで点灯するかの違いを指します。
専用型
専用型の非常灯は、通常時は消灯し、停電時のみ点灯する照明です。非常時のみ点灯する専用の照明という役割から「専用型」と呼ばれています。
専用型のなかでも、天井から飛び出すような形の直付型と、天井に埋め込まれる埋込型があります。
組込型
組込型の非常灯には、通常の照明と非常用の照明が同じ装置に組み込まれているのが特徴です。
このタイプは、通常の照明と非常灯を別々に取り付ける必要がないため、設置が安易であるというメリットがあります。
併用型
併用型の非常灯は、通常時には一般的な照明として機能し、停電時には非常灯としての役割を果たす、1台で両方の役割を担える照明です。通常の照明と非常灯が同じ装置で提供されるため、「併用型」と呼ばれています。
非常時には、通常の配置で非常灯が点灯し、日常と同様の配置を維持します。
■電源による分類
非常灯は停電時に点灯するために、独立した電力システムがあります。ただしその電源にも、内部電源で動く「電池内蔵型」と外部蓄電池を使用する「電源別置型」の2種類があります。
電池内蔵型
電池内蔵型は、非常灯本体に蓄電池が内蔵されているのが特徴です。蓄電池で独立して点灯できるため、災害や火事で電力インフラの切断があっても点灯することができます。電気回路の接続も必要がないため、設置も比較的簡単です。
ただし定期的に非常灯内部の蓄電池の交換が必要なため、設置場所によってはメンテナンスが困難なケースもあります。
電源別置型
電源別置型は、非常灯の機器の外に電源を持つタイプです。非常用予備電源として設置する外部蓄電池によって点灯します。停電時には外部蓄電池からエネルギーが供給され、自動的に点灯することが可能です。
バッテリー交換が不要であるというメリットを持ちますが、一方で外部蓄電池を導入するコストが高くつくという側面もあります。
電池内蔵型は単体でメンテナンスが可能なため、中小規模の施設におすすめです。一方、大規模の施設では、テナントエリア(=占有部分)に入らなくても一括でメンテナンス可能な、電源別置型がよいでしょう。
自社の設備に合わせた非常灯の選び方

一口に非常灯といってもさまざま形態や種類があります。見栄えだけではなく、自社の設備・環境にあった非常灯を選ぶことが大切です。
自社にぴったりな非常灯を選ぶには、次の2つのポイントをチェックしましょう。
- 天井の高さを確認する
- 順次包含半径から照射する範囲
天井の高さや照明器具の取り付け位置によって、照射される光の範囲が異なります。そのため、非常灯を設置する場所の天井情報は重要です。
また、順次包含半径とは、光が届く範囲を指します。機器や設置条件によって最適な配置は異なりますが、目安としては、30分間非常点灯した後、床面の水平面照度が1ルクス(蛍光灯またはLEDの場合は2ルクス)以上となるように配置しましょう。非常時でも足元を十分に把握できる光源を確保できます。
非常灯の交換時期はいつ?

非常灯は照明や本体機器、バッテリーで交換時期が異なります。導入前に確認しておきましょう。
■ランプ交換の時期
非常灯のランプ部分の交換時期は、点灯時間によって異なるため、一概には言えません。ただし、一般的な目安として、直管型蛍光ランプは約1〜2年、コンパクト型蛍光ランプは約半年から1年ほどが考えられます。ハロゲンランプについては交換時期に決まりはないため、気になるタイミングで交換することをおすすめします。
LED照明は、メーカーによって交換時期が異なるため、問い合わせて確認しましょう。
■本体交換の時期
非常灯を取り付ける本体部分は8〜10年で交換が一般的とされています。しかし非常時になってから使えないとなると意味がないため、故障する前に交換するのが望ましいでしょう。本体部分の寿命の目安は、次のような症状も見られるので目安にしてください。
非常灯の本体部分は、8〜10年での交換を推奨されています。ただし、非常時に正常に機能しないと設置の意味がないため、故障する前に交換することが望ましいでしょう。
本体部分の寿命が尽きる兆候には、次のような症状が現れることがあります。
- 照明の消耗が激しい
- 誤作動・故障が多い
- ソケットが変色・焦げ臭いにおいがする など
このような兆候が見られたら、すぐに交換しましょう。
■バッテリー交換の時期
非常灯のバッテリーは、約4〜6年ごとに交換することをおすすめします。通常、バッテリーは約4年を過ぎると性能が低下し始めます。
法令上、停電時には30分以上(長時間定格型の場合は60分以上)点灯する必要があるため、バッテリーの性能は重要です。
バッテリーも本体と同様に時間が経過すると劣化するため、適切な時期に交換しましょう。
おすすめの非常用照明器具

非常灯は長期間設置し続ける必要があるため、耐久性が高く、導入負担が軽減される製品が理想的です。
当社の非常灯は省エネ仕様であり、さらにJIL(Japan Institute of Light)の適合自主評定商品として認定されています。
JIL適合自主評定商品は、製品が安全性と安定性を確保しているという第三者機関の認定を受けた信頼性の高い製品です。
| 非常用照明器具 | 特徴 | ||
|---|---|---|---|
| LED専用型 | LED専用型 |
|
|
| 防雨・防湿型形 |
|
||
| LED専用型(電源別置) |
|
||
| LED一体型 | ベースライト型 |
|
|
| 直管LEDランプ搭載型 |
|
||
| 階段灯 |
|
||
| 階段通路誘導灯兼用型 |
|
||
参考:アイリスオーヤマ|非常用照明器具

非常用照明器具については次の問い合わせ先をご活用ください。
| 問い合わせ先 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|
| 新規購入問い合わせ相談 | 022-253-7095 | ||
| アフターサービスの問い合わせ | 0800-111-5300 | ||
自社の設備に適した、高性能な非常灯を導入しよう

非常灯は、停電時に人々の安全を守る重要な設備です。企業や事業者には、設置だけではなく、定期的な維持管理も求められます。
非常灯にはさまざまな種類があるため、交換時にも適切なものを選びましょう。たとえば天井に設置スペースが制限されている場合、専用型の非常灯を壁に取り付けるなど、さまざまな選択肢が考えられます。
各種非常灯の特性を活かして、正常に設置し、安心できる会社・施設作りを進めましょう。