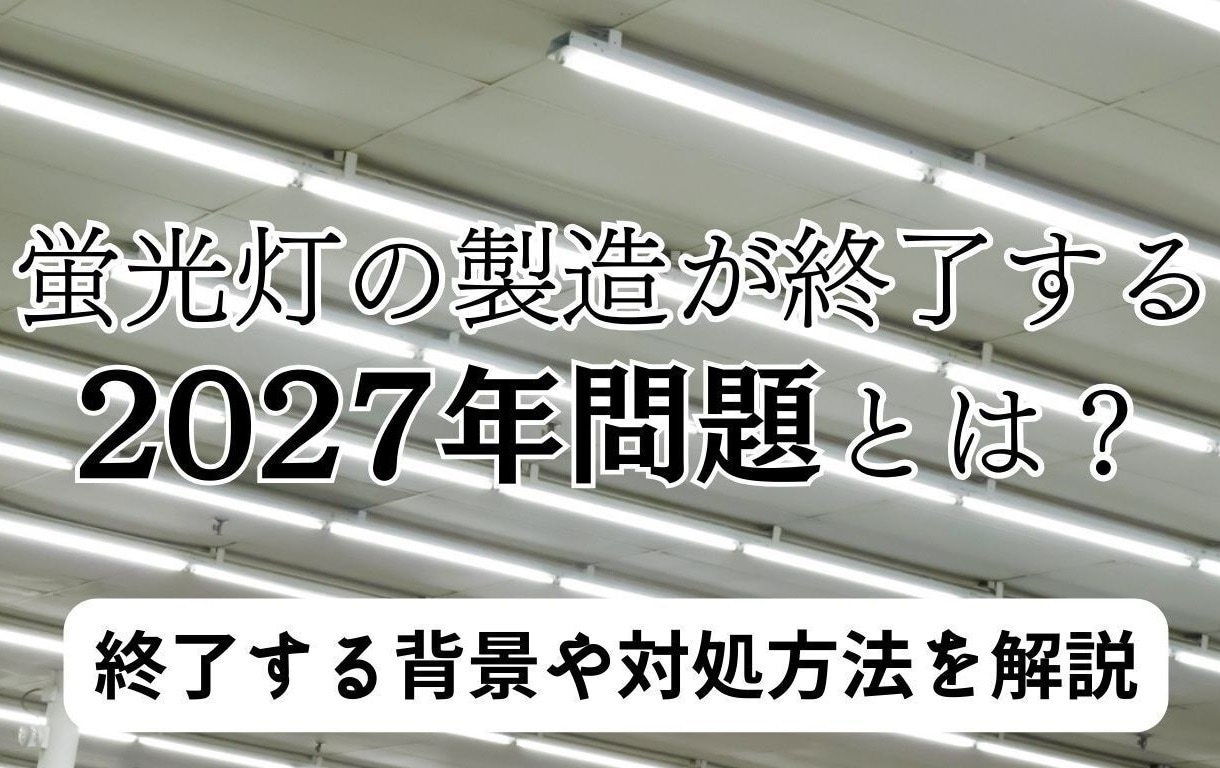2024年5月、大手電力会社10社が電気料金の値上げを決定しています。値上げの原因の一つに、電気・ガス価格激変緩和措置の終了があげられます。
本記事では、電気代を左右する電気・ガス価格激変緩和措置の概要をわかりやすく解説します。
電気・ガス価格激変緩和措置による値引き額や電気代を削減する方法も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

電気・ガス価格激変緩和措置とは?

電気・ガス価格激変緩和措置とは、政府が2022年10月に決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策の一つです。
近年は、中東情勢やウクライナ侵攻などの影響により、燃料価格の高騰が続いています。燃料価格の高騰は、家庭や企業が負担するガス代・電気代に値上げという形で反映されるのが現状です。
政府は、家庭や企業の電気代やガス代の負担を軽減するため、使用料に応じて料金を値引きする措置を導入しました。
電気・ガス価格激変緩和措置の対象となるのは、電気受給契約を締結している低圧または高圧の家庭および事業者です。(※電気代の場合)
値引きを受ける手続きは不要です。電力会社やガス会社が、国または事務局に申請し、補助金を受けます。申請業者は補助金を原資とし、電気代やガス代の値引きをおこないます。
適用時期
電気・ガス価格激変緩和措置により、電気代が値引きされるのは、当初2023年1月使用分から12月使用分まででした。
しかし、燃料価格の高騰は依然として続いており、円安が進んだことにより、2024年1月使用分から4月分まで適用期間が延長されています。2024年5月使用分以降の適用は縮小される予定です。
このような状況のなか、大手電力会社10社は2024年5月以降の電気料金の値上げを決定しています。
電気・ガス価格激変緩和措置による値引き額

電気・ガス価格激変緩和措置による値引き額は、電気とガスで異なります。値引き額は、当初よりも少なくなりつつあるのが現状です。
電気の値引き単価
電気代の値引き単価は、次のとおりです。
| 対象 | 2023年1月~8月使用分 | 2023年9月〜2024年4月使用分 | 2024年5月使用分 |
|---|---|---|---|
| 低圧 | 7.00円/kWh | 3.50円/kWh | 1.8円/kWh |
| 高圧 | 3.50円/kWh | 1.80円/kWh | 0.9円/kWh |
たとえば企業で月5,000kWhの電気を使用した場合、2023年1月~8月使用分は35,000円、2023年9月~2024年4月使用分は17,500円、2024年5月使用分は9,000円値引きされる計算になります。
ガスの値引き単価
ガス代の値引き単価は、次のとおりです。
| 対象 | 2023年1月~8月使用分 | 2023年9月〜2024年4月使用分 | 2024年5月使用分 |
|---|---|---|---|
| 都市ガス | 30円/立方メートル | 15円/立方メートル | 7.5円/立方メートル |
たとえば企業で月100立方メートルの都市ガスを使用した場合、2023年1月~8月使用分は3,000円、2023年9月~2024年4月使用分は1,500円、2024年5月使用分は750円値引きされる計算になります。
電気代高騰の原因

ここ数年は電気代の高騰が続いており、家計や企業経営を圧迫しています。電気代が高騰している背景には、次のような要素が深く関係しています。
- 円安
- ロシアによるウクライナ侵攻
- 化石燃料需要増加
- LNG・原油・石炭の供給価格の高騰
各要素を詳しく見ていきましょう。
円安
電気代が高騰している原因の一つは、円安です。円安は2022年から始まり、2024年現在も続いています。
円安は輸出が有利になる一方で、輸入には悪影響を及ぼします。
日本は、発電に不可欠な化石燃料を輸入に頼っています。円安の影響によって輸入コストが増加し、電気代の高騰につながっているというわけです。
また、円安が急激に進んだことにより、輸入コストだけでなく、燃料コストも高騰しています。
今後も円安が続く状況であれば、電力会社の申請により、電気料金の値上げが実施される可能性があります。
ロシアによるウクライナ侵攻
日本の電気代は、世界情勢の影響によって変動しやすい側面があります。
2022年2月後半には、ロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。ロシアは、世界でも有数の化石燃料の輸出国です。欧米諸国はロシアに対して資源輸出に制限をかけ、これにより、世界市場はパニック状態に陥ったという経緯があります。
日本の電源構成のうち、約7割を火力発電が占めています。火力発電に頼らざるを得ない日本では、高騰する化石燃料の価格が電気代の値上げとして表れることになりました。
※出典元:資源エネルギー庁「今後の火力政策について」
化石燃料需要増加
2020年初頭からは、世界的に新型コロナウイルス感染症が流行しました。未知なる感染症の拡大は、企業活動にも大きな影響を及ぼしました。
感染症対策によって外出制限がかかるなか、世界のエネルギー消費量が減少しました。
その後、日本では2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類に移行され、withコロナが主流になりました。経済活動は徐々に回復し、現在はエネルギー消費量が感染症拡大前と同水準まで戻っています。
withコロナにより、化石燃料の需要が増加したことも要因の一つとしてあげられます。
LNG・原油・石炭の供給価格の高騰
日本の電力は火力発電が多くを占めています。火力発電には、LNGや原油、石炭などの燃料が必要です。
円安やロシアによるウクライナ侵攻などの影響で、火力発電の燃料価格が高騰しています。特にLNG(液化天然ガス)は、環境に優しい燃料として世界から注目が集まっています。
しかし、エネルギー輸出大国であるロシアに対し、G7が輸出制限をかけたことで、調達できる国や量が限られているのが現状です。ロシアに対する輸出制限が解除されるまでは、電気代への影響は避けられないでしょう。
今後の電気料金の見通し

2020年に入ってから2年間は、新型コロナウイルス感染症の拡大やロシアのウクライナ侵攻などの突発的な影響により、電気料金が高騰する状況が続いていました。2023年は、2022年に比べると電気料金の値上げが緩やかになっています。
ただし、電気・ガス価格激変緩和措置の適用終了後は、再エネ賦課金の単価の値上げが懸念されます。再エネ賦課金とは、電力会社が再生可能エネルギーによって発電された電力を買い取る際にかかった費用の一部です。
再エネ賦課金は、年度ごとに単価が決まります。再エネ電力の買取量に応じて再エネ賦課金の単価は上がるため、発電設備を設置する家庭や企業が増えれば、電気料金の値上がりという形で反映される可能性があります。
企業の電気代を削減する方法

電気代の高騰は企業経営を圧迫しかねないため、何らかの対策が必要です。
ここからは、企業の電気代を削減する方法を紹介するので、自社で取り組んでみましょう。
LED照明への交換
現在、オフィスの照明に蛍光灯を使用している場合は、LEDへの交換を検討しましょう。LEDは蛍光灯よりも少ない電力で明るさを出せるため、消費電力を抑えられます。
また、LEDの寿命は長く、1本で40,000時間程度使用できるとされています。毎日10時間使用しても、10年以上使い続けられるため、電球切れによる交換の手間がほとんどありません。
当社では、オフィスに最適なLED一体型ベースライトを取り扱っています。ラインルクスシリーズはソケットがないため、連結時にユニット同士が隣り合っても、継ぎ目がほとんど気になりません。
ラインナップも豊富なので、LED照明への交換をご検討の企業様は、ぜひ一度当社にご相談ください。豊富な実績とノウハウをもとに、自社にとって最適なLED照明を提案させていただきます。
<LED照明のご相談はこちら>

省エネ電化製品に買い替え
オフィスで使用している電化製品が古い場合は、新しいものに買い替えることで電気代を削減できる可能性があります。近年は省エネ意識が高まっているため、省エネ性能に優れた電化製品が豊富です。
たとえばエアコンは電力消費の半数近くを占めているため、省エネ性能が高いものに買い替えると、一定の節電効果が期待できるでしょう。
既存のエアコンのまま節電に取り組む際には、当社のエナジーセーバーの活用をご検討ください。
エナジーセーバーは既存のエアコンに設置するだけで、最大50%の省エネを実現できるAI搭載空調省エネソリューションです。AIが空調の運転を最適化するため、快適さを損なわず、節電を実現できます。
※出典元:資源エネルギー庁「節電アクション」
<エナジーセーバーの詳細はこちら>

太陽光発電設備の導入
大幅に電気代を削減したい場合は、太陽光発電設備を導入するのも一つの手です。自社の敷地内に太陽光発電を設置すると、自家発電・自家消費できるため、電力会社から供給される電気の消費量を減らせます。
また、自家発電した電力が余った場合は、電力会社に買い取ってもらうことも可能です。
ただし、太陽光発電設備を導入する際には、高額な初期費用がかかります。国や自治体のなかには、太陽光発電設備の設置で活用できる補助金制度を設けているため、公式サイトや窓口で確認してみてください。
蓄電池の導入
電気代を削減するために、太陽光発電設備の設置と同時に、蓄電池を導入する方法もあります。蓄電池とは、電気を蓄えられる機能を搭載した充電装置のことです。近年は技術が進歩しており、優れた性能の蓄電池が数多く登場しています。
大規模な災害が発生した場合、電力会社からの電力の供給が滞るリスクがあります。自社に蓄電池を導入し、電気を蓄えておけば、万が一のときでもすぐに使用することが可能です。
蓄電池の導入は、太陽光発電設備を単体で導入する場合に比べ、自家発電・自家消費を実現しやすくなります。ただし、太陽光発電設備と同様に、蓄電池を導入する際には初期費用が高額になりがちです。
電力会社の見直し
2016年4月からは、電力の完全自由化がスタートしました。これにより、大手電力会社と小売事業者との価格競争が起き、選ぶ業者やプランによっては電気代を安くできる可能性が高まりました。
現在、大手電力会社と契約している場合は、新電力への乗り換えを検討してみましょう。自社に適したプランかつ安いプランを提供している業者と契約すれば、電気代の削減につながります。
ただし、新電力でもプランによっては大手電力会社と変わらないケースもあるため、事前にシミュレーションが必要です。
また、倒産や事業撤退などにより、電気代が突然高騰するリスクもあるため、十分に検討するようにしましょう。
2024年春以降は積極的に節電対策に取り組もう

近年は電気代の高騰が続いているものの、電気・ガス価格激変緩和措置により、やや抑えられている状況です。
しかし、電気・ガス価格激変緩和措置は、2024年4月使用分までとなっています。2024年5月使用分以降は、大手電力会社も値上げを決定しているため、ますます電気代が負担になる可能性が高いでしょう。
電気代は、企業の工夫次第で削減することが可能です。今後も電気代が値上がりする可能性を想定し、早い段階から企業で節電対策に取り組むことが大切です。
節電対策として、LED照明への交換やエナジーセーバーの導入をご検討の場合は、ぜひ当社にご相談ください。