お酒を飲んだ後は、睡眠をとっていてもアルコールが抜けていないことがあります。意図せず飲酒運転してしまわないよう、アルコールが抜ける時間を知っておきましょう。この記事ではアルコールが抜ける時間の目安と算出方法、アルコールが抜ける時間に影響するものについて詳しく紹介します。
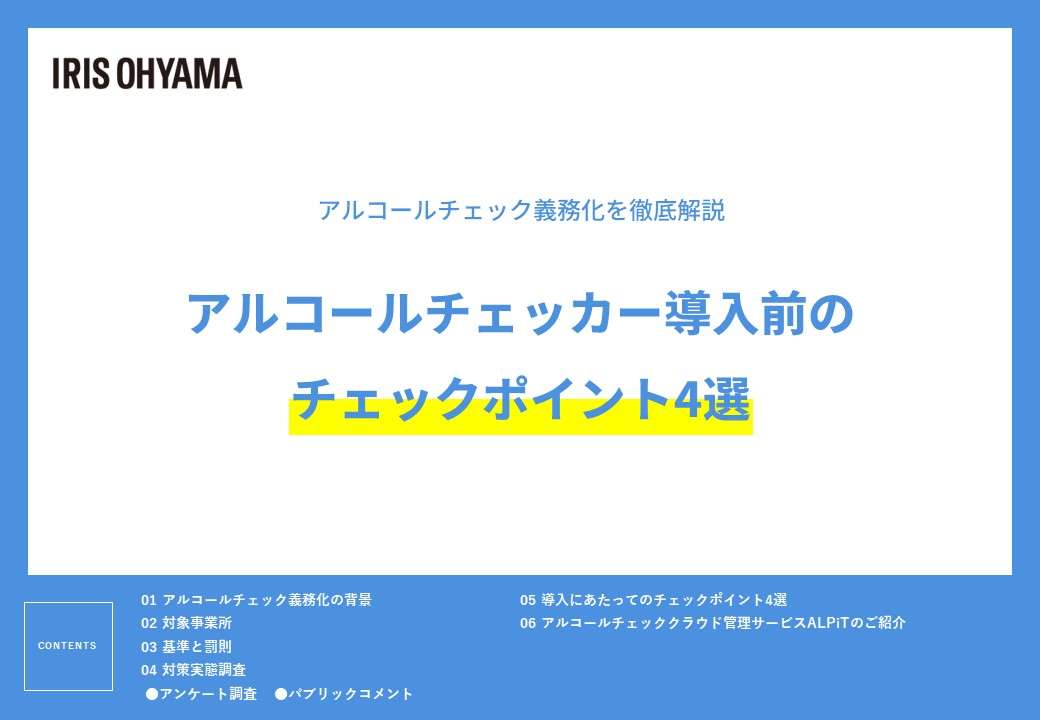
アルコール摂取量の基準「1単位」とは

アルコール摂取量の基準単位となる1単位とは、純アルコールに換算すると20g。厚生労働省では、1日の適度な飲酒量を「純アルコールで20g」程度としています。
アルコール量は「お酒の量(ml)×(アルコール度数÷100)×0.8」で求められます。この計算式をもとに、種類ごとの1単位の目安量を表したものが以下です。
| 種類 | 量 |
|---|---|
| ビール | 500ml |
| 日本酒 | 1合(180ml) |
| ウイスキー | 60ml |
| ワイン | 200ml |
| チューハイ | 350ml(7%) |
| 焼酎 | 100ml(25%) |
アルコールが抜ける時間の目安と計算方法

「少し飲んだだけ」「仮眠をとった」といっても、アルコールが体から抜けるには予想以上に時間がかかります。ここではアルコールが分解される時間の目安、アルコールが抜ける時間の算出方法について紹介します。
1単位のアルコールが分解される時間の目安
1単位のアルコールが分解され体から抜ける目安としては、お酒が飲める男性で4時間、お酒の弱い人や女性、高齢者で5時間です。ただしこの時間は、体重や体質、年齢、性別などにより個人差があります。
例えば3単位以上のお酒を飲んだ場合、半日以上はアルコールが消えません。夜飲酒すると、翌朝もアルコールが残っている可能性があります。
その状態で車を運転すると飲酒運転となる可能性が高いため注意が必要です。
アルコールが体から抜ける時間の算出方法
体内で分解されるアルコール量は、体重1kgにつき1時間で0.1g。例えば、体重60kgの人がビール350ml(純アルコール量14g)を飲んだ場合の計算式は以下の通りです。
14g÷(60kg×0.1g)≒2.3
つまり、アルコールが抜けるまでに2~3時間かかる計算になります。
ただしこの時間はあくまでも目安です。個人のアルコール分解能力や体調、性別、年齢などによって左右されます。
アルコールが抜ける時間に影響するもの

アルコールが体から抜ける時間は、性別や年齢、遺伝などの影響によって個人差があります。アルコールが抜ける時間に影響するものを具体的に紹介します。
①性別
1時間でアルコール分解ができる量は、男性が約9g、女性が約6gです。女性が男性よりも分解が遅い理由としては、男性より肝臓が小さい、女性ホルモンの影響、体脂肪が多い、水分量が少ない、などが挙げられます。
②年齢
年齢を重ねると肝臓の機能が低下し、アルコールを分解するスピードが遅くなります。また、体外へアルコールを排出するために必要な体内の水分量が、加齢とともに減少するのも原因です。
これらの理由から、年齢を重ねるとお酒に酔いやすく、アルコールが抜けるまで時間がかかります。若い頃と同じ量のお酒を飲んでしまうと、アルコールの血中濃度が高くなりやすいので注意しましょう。
③遺伝子型
両親から受け継いだ遺伝子型の性質によっても、アルコールに強い人・弱い人に分かれます。
お酒を飲んだ時に発生する、アセトアルデヒドを分解する酵素が「ALDH2」。この活性が弱い、または欠けていると少量でも悪酔いしやすくなるようです。
ALDH2の遺伝子には、お酒の分解能力が高いN型と分解力が低下したD型があり、両親から受け継いだ遺伝子によって以下の3タイプに分けられます。
| 型 | タイプ |
|---|---|
| NN型 | ALDH2が活性している。アルコールに強い。 |
| ND型 | NN型の1/16しか活性していない。ほどほどに飲める。 |
| DD型 | ALDH2が活性していない。弱い、まったく飲めない。 |
寝るとアルコールは抜けやすいのか

飲んだ後でも仮眠をとればアルコールが抜ける、と思っている人は多いはず。しかしアルコールが抜ける時間には個人差があります。仮眠をとったからといって車を運転できるとは限りません。
仮眠をとっている間は内臓が休んでいて、体はアルコールを分解しにくい状態です。起きている時と比べて、分解に2倍の時間がかかります。
普段からお酒をよく飲む人は、アルコールが回っている状態に慣れている場合があるため、特に注意が必要です。仮眠をとったことで、アルコールが抜けたと思い込まないようにしましょう。
もしアルコールが残った状態で運転してしまうと、注意力や判断力が低下しているので大変危険です。
飲酒運転した際の処分・罰則

飲酒運転を取り締まるために、法律で厳しい処分と罰則が設けられています。酒気帯び運転と酒酔い運転の処分と罰則について詳しく紹介します。
違反にならないからといっても、少量でも飲んだ状態での運転は危険です。飲酒運転は本人だけではなく、周りの人にも大きな影響を与えるので絶対にやめましょう。
①酒気帯び運転
呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の状態で運転している場合、酒気帯び運転に該当します。
| 処分 | 罰則 |
|---|---|
| ●0.15mg/L以上0.25mg/L未満の場合:違反点数が13点、免許停止期間が90日 ●0.25mg/L以上の場合:違反点数25点、免許取り消し処分、2年間の欠格期間 |
●運転者と車両などの提供者:3年以下の懲役または50万以下の罰金 ●酒類の提供者や車両の同乗者:2年以下の懲役または30万以下の罰金 |
※参照元:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」
②酒酔い運転
呼気中のアルコール量に関係なく、アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態で運転すると、酒酔い運転に該当します。
| 処分 | 罰則 |
|---|---|
| ●違反点数35点、免許取り消しと3年間の欠格期間 | ●運転者と車両などの提供者:5年以下の懲役または100万以下の罰金 ●酒類の提供者や車両の同乗者:3年以下の懲役または50万以下の罰金 |
※参照元:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」
飲酒運転撲滅を目指すアルコールチェック義務化と対策法

飲酒運転防止のため道路交通法が改正され、白ナンバー事業者もアルコールチェックが義務化されました。最後に道路交通法の改正内容の詳細と、アルコールチェックにおすすめの「ALPiT」を紹介します。
法改正によりアルコール検知器を使ったチェックが義務化
2022年4月の法改正により、緑ナンバーに加えて白ナンバー事業者もアルコールチェックが義務化されました。
次いで2023年12月より、アルコール検知器によるチェックの義務化が開始。一定台数の車を所有する事業者は安全運転管理者を選任し、運転前後にアルコール検知器を使ったアルコールチェックとその記録を行う必要があります。
「ALPiT」ならアルコールチェックがスムーズ

アイリスオーヤマのALPiTは、簡単なステップでアルコールチェックから記録保管までできるクラウド管理サービスです。
アルコール検知器を使用したチェック結果は、1年間記録として保管が必要。ALPiTなら息を吹き込むだけで、読み取った測定結果をクラウドに自動送信します。3年間保存できるため、紙での記録や管理が不要です。
加えてパソコンの管理画面でチェック結果をリアルタイムで確認できる他、アルコールを検知するとメールで知らせてくれる機能も搭載されています。
〈ALPiTの詳細はこちら〉
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/camera/products/alpit/
アルコールが抜ける時間の把握とチェックで飲酒運転の撲滅を

お酒を飲んだ後は、「一晩寝れば大丈夫」といった安易な考えで車を運転するのは禁物。万が一事故を起こしてしまうと、厳しい罰則を受けなければいけません。アルコールが分解される時間は、年齢や体質、遺伝などによってまちまちです。アルコールチェッカーを活用し、従業員の飲酒運転撲滅に取り組みましょう。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。






