法改正により、2025年からすべての建築物に対して省エネ基準適合が義務化されます。エネルギーの利用や環境保護に関して社会的な機運が高まっている中、省エネを意識し始めている企業も多いでしょう。そこで今回は、省エネ基準適合の義務化について詳しく解説します。併せてオフィスで取り組める省エネ対策や、空調の省エネに有効な機器も紹介します。

省エネ基準とは
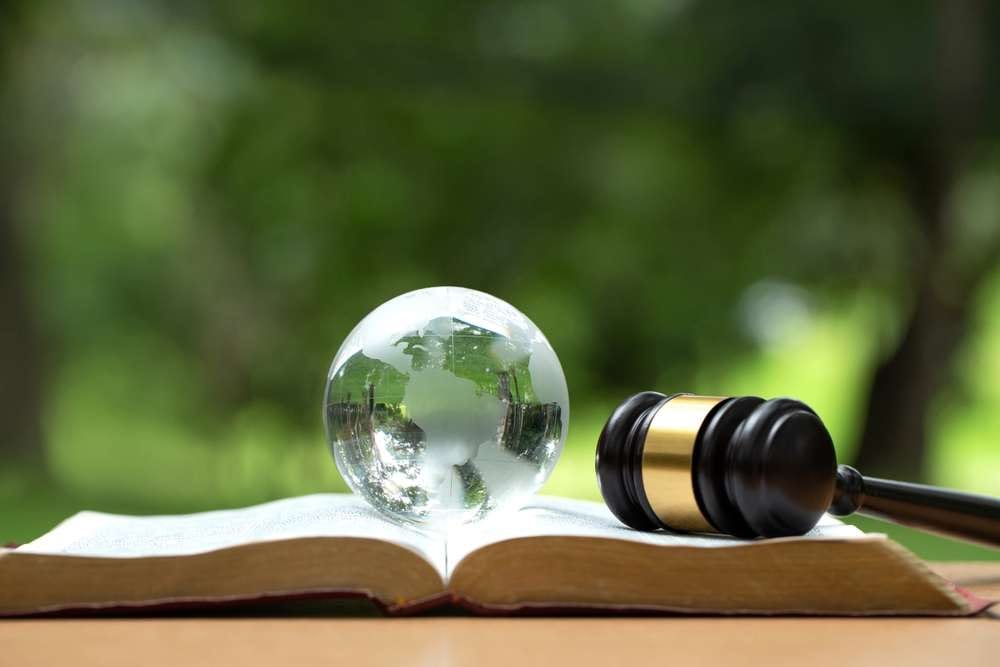
まずは省エネ基準とは何かということから知るため、省エネ基準の概要を解説します。また、2025年4月から実施予定の「省エネ基準適合」の義務化について、推進される背景もみていきましょう。
省エネ基準の概要
省エネ基準(省エネルギー基準)とは、建築物省エネ法に定められている、建築物におけるエネルギー消費性能の基準です。空調・換気・照明・給湯といったエネルギーの総量から太陽光発電などで創り出したエネルギーである創エネ量を減じる「一次エネルギー消費量」と、外皮(壁・窓等)の表面積あたりの熱の損失量「外皮基準」の2つが、一定の基準を下回っていることが条件となります。
初めて制定されたのは1980年。当時は工場やそのほか建築物など対象が特定的であり、また規制内容は断熱性に関するもので、努力義務でした。その後省エネ基準は、1990年代、2000年代と改正され、徐々に細かな規制に変化していきます。
特に2000年代の改正では、省エネ基準の目的も大きく転換しています。それまでは化石燃料の使用量削減を目的としたものでしたが、二酸化炭素の排出量削減や温暖化防止など、より大規模な環境問題の改善を目的とするようになりました。
2025年4月~「省エネ基準適合」義務化の背景
2025年4月には、省エネ基準適合が義務化されます。これはすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられるということです。この改正の背景には、世界中で脱炭素やカーボンニュートラルの動きが推し進められていることがあります。これまでよりさらに省エネに力を入れる国が増えているため、日本もそれにならう形です。
省エネ基準に適合した建築物のメリット・デメリット

省エネ基準に関する法規制は徐々に細かくなってきていますが、省エネ基準適合の建築物が、具体的に自分達の身の回りや生活にどのような影響を与えるのかイメージしにくい人もいるかもしれません。省エネ基準適合の建築物のメリット・デメリットを知れば、理解が深まります。
省エネ基準に適合した建築物のメリット
省エネ基準に適合した建築物は、冷暖房への依存を減らせることがメリットの1つです。断熱性や換気性に優れているため、冷暖房を控えてできる限り自然の環境に近づけられ、過ごしやすいでしょう。冷暖房の使用頻度が減れば、光熱費の節約にもつながります。
また、エネルギー消費の抑制に貢献できることもメリットと言えます。特に資源が限られている日本にとってエネルギーの確保と省エネは重要な課題です。省エネ基準に適合する建築物は、こうした社会規模の課題を改善していくため重要な存在を担っています。
省エネ基準に適合した建築物のデメリット
省エネ基準に適合した建築物のデメリットは、建てる際のコスト面です。省エネ基準に適合していない建築物よりも機能性が高い構造になっているため、設計や資材も専門的な部分が多くなり、必然的に費用が高くなりやすい傾向にあります。ただし先述した通り、建築物が完成した後のランニングコストとしてはエネルギー代が抑えられるため、長い目でみればお得感も生まれるでしょう。
省エネ性能アップのための主な取り組み

ここで、省エネ性能アップのために建築物に取り入れられる具体的な取り組み例も紹介します。オフィスビルや工場など住宅以外の用途の建築物と、住宅に分けて取り上げます。
オフィスビルなどの建築物
オフィスビルや工場など、住宅以外の規模が大きめな建築物については、次のような取り組みで省エネアップを期待できます。
- 太陽光発電
- 高効率空調設備
- 断熱窓・サッシ
- LED照明
一般住宅
一般住宅で、主にみられる省エネ性能アップの取り組みは次の通りです。
- 太陽光発電
- ひさし
- 断熱材
- ペアガラス・二重サッシ
- 高効率給湯器
オフィスで実践できる省エネ対策

日本国内では省エネ基準の改正により、二酸化炭素の排出や温暖化の防止など環境保護推進の動きが活発化しています。今後の法改正でよりさまざまな建築物に省エネ基準適合が求められるため、企業においても省エネを意識しておきたいものです。ここからは、オフィスで実践できる省エネ対策を紹介します。
オフィスにおいて省エネ意識を高める
省エネを推進するためには、まずオフィス内の意識を高める必要があります。さまざまな取り組みを考えても、実際にそれを実行する従業員の意識が伴わなければ失敗しやすいでしょう。まずは省エネを成功させる土台づくりです。社内の通知やメール、掲示などで、省エネの必要性を周知します。
照明器具の掃除や間引きを行う
照明器具を定期的に掃除することも省エネ対策です。照明器具は汚れによって明るさが変わります。掃除をして十分な明るさを確保できれば、多くの照明をつける必要はありません。また照明器具の必要な部分を考えながら間引きを行えば、照明の消費電力を減らせます。
電気消費の無駄を省く
日々の中でこまめに電気消費の無駄を省くことも重要です。例えば、室内のスイッチやコピー機・パソコンの電源など、使わないときにはこまめにオフします。しばらく使わない電気機器は電源プラグを抜くのも良い方法です。地道な取り組みではありますが、この小さな積み重ねが省エネにつながります。
空調の使用場所や温度設定を調整する
空調の使い方を工夫すると省エネにつながります。例えば、使用する場所を決めること。全体に空調を使うのではなく部分的にする、スペースを区切って特定の場所にだけ送風を集中させるなどの工夫があります。
また、温度設定を調整することも重要です。冷やし過ぎ、暖め過ぎは消費電力を上げてしまいます。一般的な温度設定の目安は夏28℃、冬20℃です。温度設定は目安を目指し、服装で各自調整などを行うと良いでしょう。
省エネ基準を意識した空調節電なら「エナジーセーバー」

工場や倉庫、店舗などの省エネ対策の1つとしておすすめしたいのが、空調節電に特化した「エナジーセーバー」です。既存の業務用エアコンに取り付けるだけで、自動で運転を最適に調整。設定温度を変えずに温度の上下変動を最適化するので、快適な空間を保ったまま省エネできます。温度ムラを少なくし、エアコンの無駄な稼働も防げるため、消費電力を削減可能です。
省エネの効果をデータで可視化でき、より一層実感しやすくなります。導入するだけで手軽に省エネ対策ができるでしょう。利用については、一括購入と、アフターサービスの充実した「あんしん空調省エネパック」をご用意しております。
〈エナジーセーバーの詳細はこちら〉
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/air/products/energy-saver/
省エネ基準を意識しつつできることから取り組みを

2025年に省エネ基準が義務化されれば、社会全体でさらに省エネに対する意識は高まるでしょう。国際的な課題の解決に企業としても貢献すべく、できることから省エネ対策に取り組むことが大切です。企業内で省エネ対策に関する理解を深め、こまめなエネルギー節約や省エネ用機器の導入など、対策の仕方はさまざまです。いろいろな方法を試しながら、省エネに強い企業づくりにつなげてください。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


