飲酒運転や酒気帯び運転防止を目的に義務化されていたアルコールチェックは、2022年の道路交通法の改正により対象となる事業所が拡大されました。本記事ではアルコールチェック義務化の概要や対象となる事業所、事業所がとるべき対策、アルコールチェックの実施手順などを解説します。
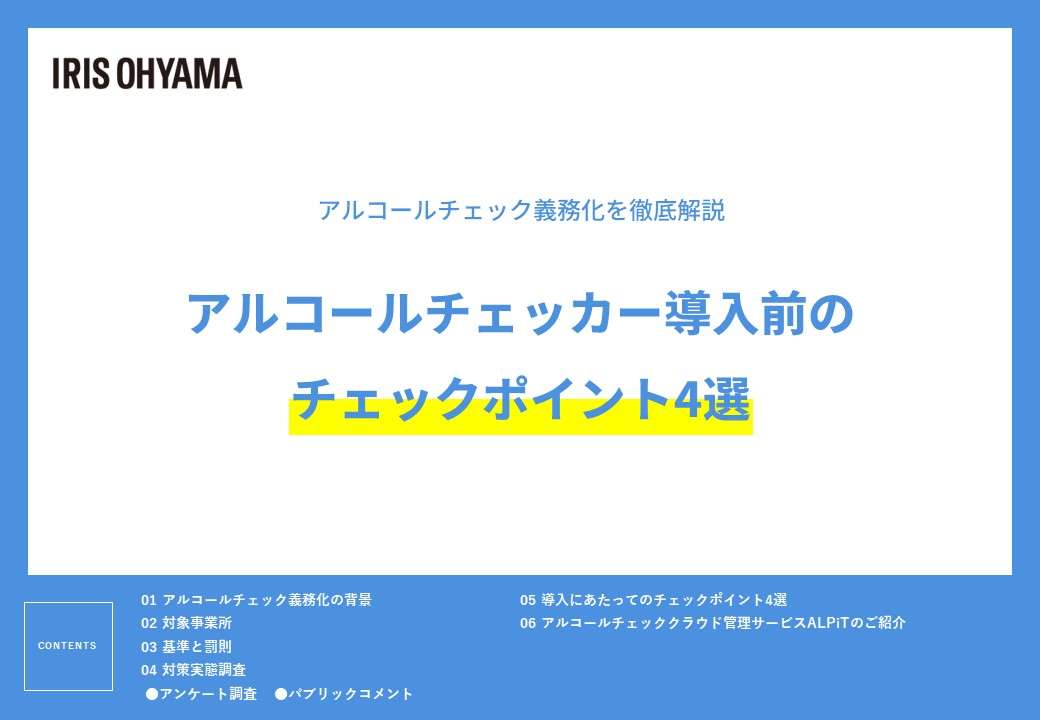
アルコールチェック義務化の概要
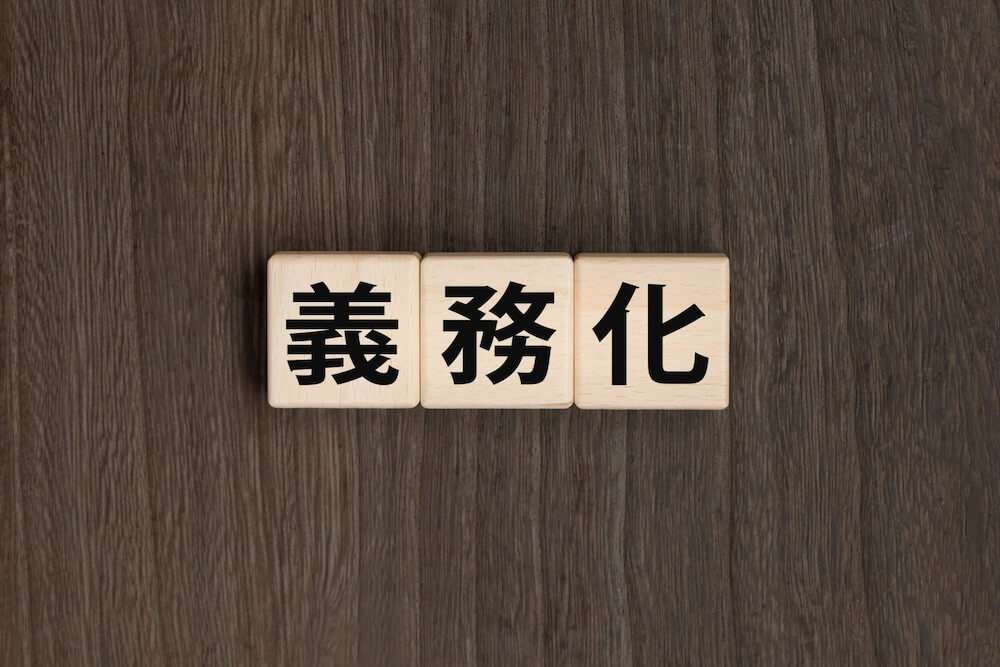
アルコールチェックの義務化は飲酒運転による事故の発生により、段階的に引き上げられてきました。飲酒運転は個人だけではなく企業や社会全体で取り組んでいくべき問題です。まずは、アルコールチェック義務化の概要を見ていきましょう。
義務化された背景
アルコールチェックが最初に義務化されたのは2011年。仕事中の運転でも飲酒運転が発生していたため、緑ナンバーの自動車を対象にアルコールチェックが義務化されました。
さらに、2021年6月に白ナンバーの飲酒運転トラックが引き起こした事故がきっかけで、義務化の対象範囲が拡大されました。
| 事業用の自動車のナンバープレートの色 | 違い |
|---|---|
| 緑ナンバー | 「有償」で人や荷物を目的地に運ぶ事業用の自動車(タクシー・バス・トラックなど) |
| 白ナンバー | 「無償」で人や荷物を目的地に運ぶ事業用の自動車 |
見逃された飲酒運転による事故は社会で問題視され、2022年4月の道路交通法の改正により、白ナンバーの自動車にもアルコールチェックが義務化されています。
2022年4月|対面・目視でのアルコールチェックが義務化された
2022年4月から、運転前後の計2回のアルコールチェックが義務化されました。
<義務化された項目>
運転前後の運転者が酒気を帯びていないか目視等で確認する
アルコールチェックの結果をデータや日誌等で記録し、1年間保存する
2023年12月|アルコール検知器によるアルコールチェックが追加された
2023年12月から、アルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されました。義務化の内容には定期的な点検やいつでも使用できる状態にしておくなど、アルコール検知器の取り扱いについても含まれています。
<義務化された項目>
運転前後の運転者が酒気を帯びていないかの確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
アルコール検知器は常時有効に保持すること
アルコールチェック義務化の対象となる事業所

新たにアルコールチェック義務化の対象となったのは、安全運転管理者を配置している事業所です。安全運転管理者とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所ごとに選任される安全な運転に必要な業務を行う者のこと。業種にかかわらず、以下の条件に該当する事業所または営業所が対象です。
<安全運転管理者を選任する事業所の条件>
- 乗車定員が11人以上の自動車を、1台以上保持する事業所
- その他の自動車を、5台以上保持する事業所
※大型・普通自動二輪車は、1台を0.5台として計算
※1事業所あたりの台数
アルコールチェック義務化の対象事業所がとるべき3つの対策

アルコールチェック義務化の対象であれば、安全運転管理者の選任やアルコール検知器の準備が必要です。アルコールチェック義務化の対象事業所がとるべき対策を解説します。
①安全運転管理者の選任
アルコールチェック義務化の対象となる企業は、安全運転管理者を選任しなければなりません。安全運転管理者の資格要件は次のとおりです。
<安全運転管理者の資格要件>
20歳以上
自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者等
過去2年以内に、国家公安委員会による安全運転管理者の解任命令を受けていないこと
過去2年以内に、酒酔い・酒気帯び運転、妨害運転などの違反行為をしていないこと
出典:警察庁「安全運転管理者制度の概要」
安全運転管理者の選任義務に違反した場合、50万円の罰則が科せられます。アルコール義務化の対象事業所で、安全運転管理者を選任していない場合は速やかに手続きしましょう。
H3 ②アルコール検知器の準備
アルコールチェックをするにはアルコール検知器が必要です。国家公安委員会が定める「呼気中のアルコールを検知、酒気帯びの有無または濃度を音や色(光)・数値で確認できる機能を有する機器」を手配します。
またアルコール検知器が正常に動作するよう、常に使用できる状態にしておくことが求められます。
H3 ③アルコールチェックの記録・保管体制の整備
アルコールチェックの実施だけではなく、結果を1年間記録することも義務化されています。記録は紙でも電子でも構いません。記録を保管する場所を用意して、1年間保存します。
アルコールチェックの実施手順

実際にどのような流れでアルコールチェックを行うのか、実施手順を紹介します。
運転の前後にアルコール検知器で酒気帯びの有無を確認
安全運転管理者が、運転の前後にアルコール検知器で呼気中のアルコール濃度を測定します。これから業務を行う運転者が飲酒していないか、業務中に飲酒をしていないかを厳重にチェックします。
アルコールチェックを行うタイミングは業務開始前の出勤時や朝礼時、業務終了後の退勤時など、運転者が集まる時に行うと良いでしょう。
アルコールチェックした内容を記録する
目視・アルコール検知器を用いて、アルコールチェックした内容を記録します。
<記録する項目>
確認者名
運転者名
運転者が業務で乗車する自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
確認の日時
確認の方法(対面ではない場合は具体的方法等)
酒気帯びの有無
指示事項
その他必要な事項
記録した内容を1年間保管する
アルコールチェックで記録した内容を1年間保管します。誤字脱字や記入漏れがないか確認し、1ヵ月ごとにまとめるなど見やすく整理して保管してください。
義務化されたアルコールチェックを怠った場合の罰則
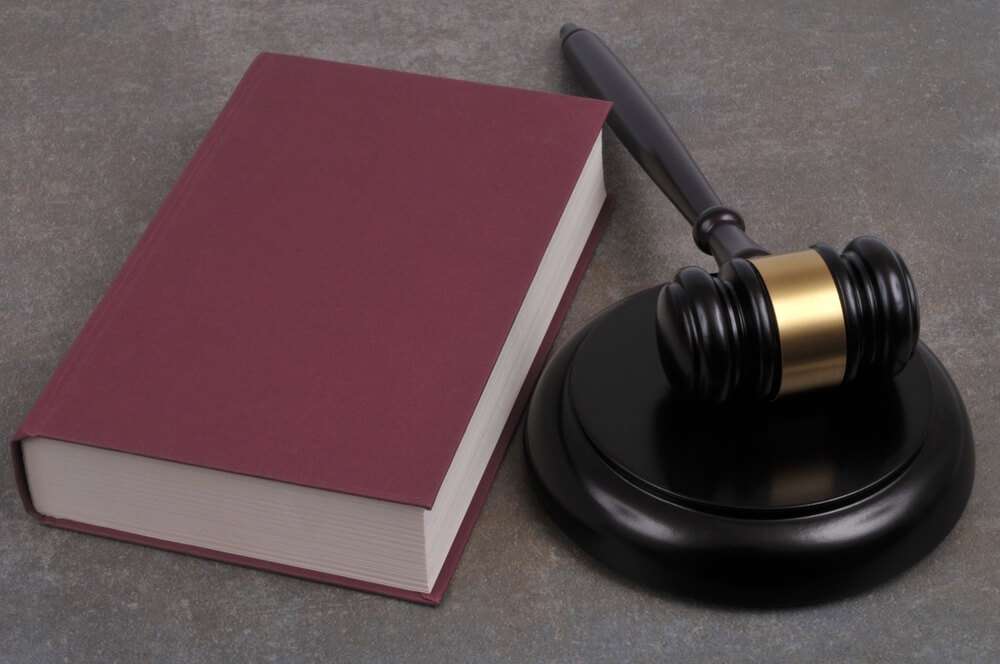
アルコールチェックは道路交通法によって義務付けられています。守らなかった場合は罰則が科される可能性があります。
安全運転管理者への罰則
アルコールチェックを怠ったとしても罰則はありませんが、安全運転管理者の業務違反になります。業務の怠慢が見られた場合、国家公安委員会から安全運転管理者の解任命令や是正措置の命令が下される可能性も。もしも従わなかった場合は罰則が科せられます。
飲酒運転に該当した場合の罰則
アルコールチェックが見逃され、従業員が飲酒運転をした場合は厳しい罰則が科されます。
| 罰則を受ける人 | 状況 | 罰則 |
|---|---|---|
| 運転者 | 酒酔い運動 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 運転者 | 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 車両提供者(企業の代表者または責任者) | 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 車両提供者 | 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 酒類提供者・同乗者 | 酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 酒類提供者・同乗者 | 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
業務中に飲酒運転をすると、運転者だけではなく企業や酒類を提供した人、同乗者にも罰則が科されます。飲酒運転を起こさせないためには、企業全体で意識を向上させる必要があります。
酒酔い・酒気帯びの違いやアルコール基準値などを詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。
▼内部リンク「飲酒運転 基準」
アルコールチェックによる業務コストを削減できる「ALPiT(アルピット)」
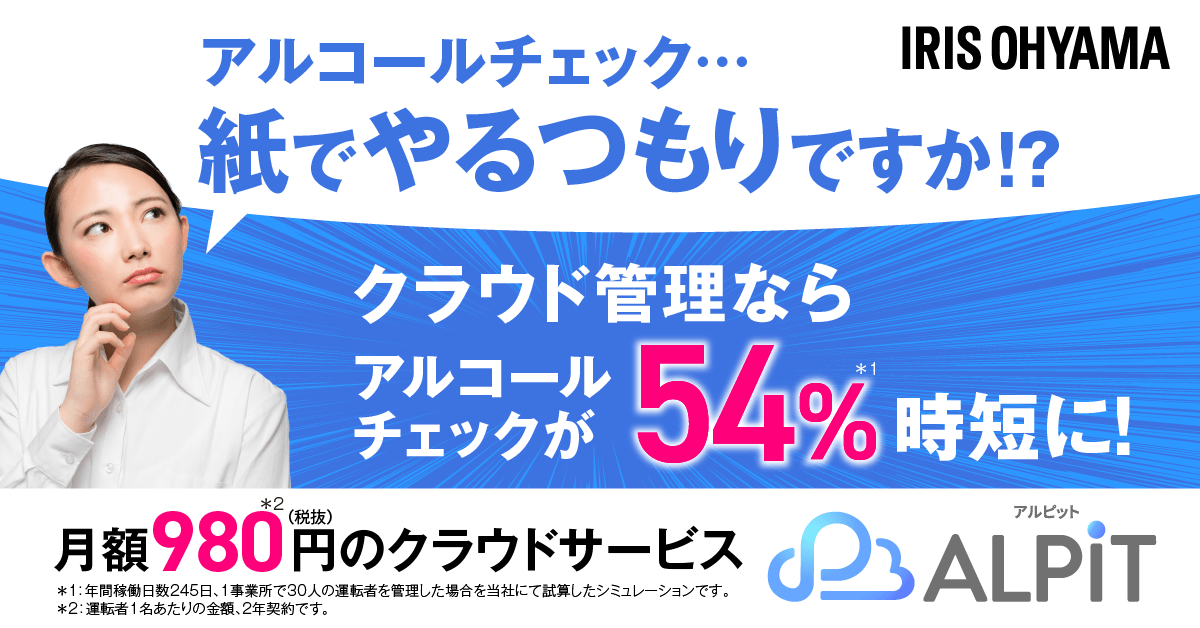
ALPiT(アルピット)なら、飲酒運転をさせないために必要なアルコールチェックの業務負担を大幅に軽減できます。アルコールチェックが義務化されたことにより安全運転管理者や運転者の業務が増加、運転者一人一人にアルコールチェックと記録・管理をする時間や手間がかかることになりました。
ALPiTはアルコール検知器に息を吹くだけで検査結果を送信、自動でクラウド管理ができます。チェック結果をクラウドで一元管理できるため、安全運転管理者の業務負担を軽減します。
アルコールチェックによる業務コストを削減するなら、ALPiTを導入してみてはいかがでしょうか。
〈ALPiTの詳細はこちら〉
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/camera/products/alpit/
アルコールチェック義務化への対策をして、業務を効率化

アルコールチェックは、業務中の飲酒運転を撲滅するために必要不可欠です。義務化の対象である事業所は、安全運転管理者の選任やアルコールチェックの準備・記録・管理が必須。安全運転管理者や運転者だけに任せるのではなく、企業全体で取り組んでいきましょう。また無理なく運用できるよう、アルコールチェック業務を効率化できるツールの導入も検討してみてください。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。






