3Sとは「整理」「整頓」「清掃」の頭文字をとった言葉です。職場を整理整頓し、清潔な状態を維持していくことで、生産性向上や職場の安全性の確保、さらには社員のやる気をアップするといった効果が期待できます。この記事では3Sとは何か、活動の目的や効果、さらに実践的な進め方について解説します。
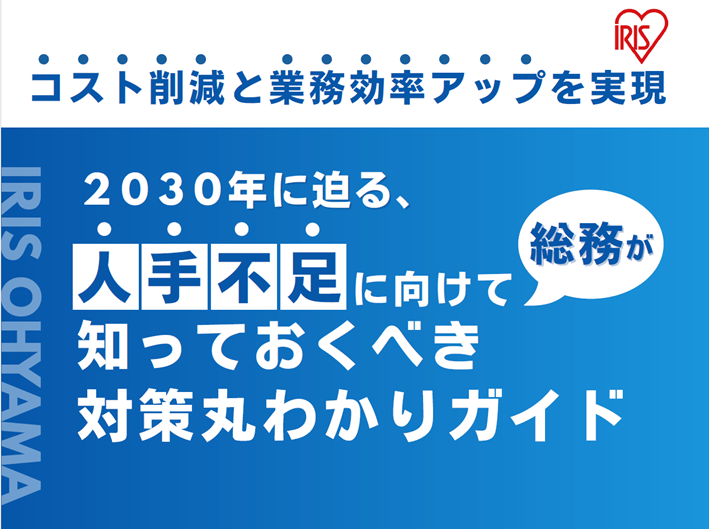
3Sとは

初めに3Sとは何かについて解説します。あわせて、似た言葉である5Sとの違いも説明します。
「整理」「整頓」「清掃」のこと
3Sとは「整理」「整頓」「清掃」の頭文字のSからできた言葉です。
- 整理:物品の必要、不必要を区別し、不要な物を処分すること
- 整頓:物の配置を決めること。必要な物がスムーズに取り出せるようにする
- 清掃:作業空間をきれいにすること。ゴミや汚れのない状態を保ち、怪我や事故のリスクを減らす
整理、整頓、清掃を徹底することにより、職場環境の改善を図るための活動を「3S活動」と呼びます。業務の効率化や職場の改善に役立つ活動のスローガンとして、主に製造業で掲げられていましたが、今では業種を問わず多くの企業で導入されています。
5Sとの違い
5Sとは、3S(整理・整頓・清掃)に「清潔」と「躾」を加えた言葉です。
- 清潔:きれいな状態を維持すること
- 躾(しつけ):決められたことを実行できるよう、習慣をつけること
3Sができると職場が清潔になり、それを維持するためには社員の教育や職場のルール作りが必要です。
3Sの目的

3Sの目的は、安全性が高く効率的で快適な職場を作ることです。
床の清掃が行き届き、周囲の物を片付けておけば、不慮の事故で怪我をする心配がなくなります。単に見た目がきれいな職場を作るのではなく、誰にでも使いやすく整理、整頓された職場を作ることが目的です。
3Sが実現できれば、日常的な小さな業務の無駄がなくなり、社員のリソースを節約できて本業により力を集中できるようになります。
3Sの効果

3Sの導入で得られる主な効果には、コストの削減、業務の効率化、安全・快適な職場環境の構築や社員の自主性の育成が挙げられます。それぞれについて解説します。
コストの削減
3Sにより不用品を減らせると、スペースに余裕が生まれてコスト削減につながります。
オフィスを借りる場合、毎月のランニングコストとして家賃がかかります。3Sにより必要なスペースを減らすことで、より家賃の安いオフィスに移転も可能です。置き場を確保するために倉庫などを借りている場合は、不用品を処分して解約できるかもしれません。
オフィスを移転せずにそのまま利用する場合でも、生産性のあることに空間を活かせます。
業務の効率化
3Sが実施されれば、物の置き場を把握できるので効率良く業務が捗ります。
無駄な物が多く、整理されていない職場では、時間や従業員の労力が無駄に使われやすい傾向です。整理整頓されていれば、物を探すという余計な作業がなくなり、業務にすばやく着手できるようになります。
またスペースを常に確保できていると、スムーズに作業を進められて業務効率の向上に効果的です。作業効率を高めることで結果的に納期を短縮でき、業務改善に使う時間を確保できるようになります。
安全・快適な職場環境の構築
3Sにより職場が清潔に保たれていれば、気のゆるみや不注意による事故を予防できます。
備品や社員の私物が整理されず、どこに何があるか整頓されていない、ゴミが散乱して清掃されていない環境では、うっかりミスによる事故が起こりやすくなります。また周囲に物が積み上げられていれば、地震などのはずみで物が崩れ落ち、事故が起きてしまう危険も。
清掃や整頓が行き届けば、床の上に物が少なく歩きやすく、机の上が整頓されて作業スペースを確保できるので、快適な職場が実現できます。スムーズに移動できる作業動線を確保することは、安全対策になるとともに、業務の効率化にもつながります。
社員の自主性の育成
3S活動は、職場で働く社員全員が主体的に参加することで効果が高まります。
社員それぞれがルールや改善方法を話し合い、3S活動を進める上で何をどのように実行すべきか、必要なことを考える機会を持つことは自主性の育成につながるでしょう。社員教育の一環として利用できるのも、3Sの効果です。
3Sの進め方

3Sの実際の進め方についてみていきましょう。3S活動を効果的に進めるための4つのステップについて説明します。
ステップ1. 目標を明確にする
最初に3S活動を行う目標を明確にします。目標を明確にすることで社員の理解や納得を得られやすくなり、活動をスムーズに進めやすくなります。
社員全員が3S活動に参加できる環境や機会を用意しましょう。例えば、社員全員が責任を持てるように、3Sのどれかのプロジェクトの担当者を割り振るなどがおすすめです。
ステップ2. 現状を可視化する
次に現状の業務プロセスを可視化し、流れを把握できるようにします。職場を整理、整頓するには、何が必要で何が不要かを明確にする必要があります。業務プロセスを把握できると、どこに3S活動を行う余地があるかを見直すことにつながるでしょう。
ステップ3. ルールを作成する
3S活動を定着化するには、具体的なルールの作成が必要です。明確なルールがないと、社員それぞれの裁量で整理、整頓や清掃をするためにばらつきが生じてしまいます。誰もが守りやすいルール化が大切です。まずは工具や資材の定位置、清掃の手順をルール化するところから始めてみてはいかがでしょうか。
ステップ4. 活動の記録と見直しを継続する
3Sを継続するには、活動を記録して見直ししていくことが大切です。3S活動の内容や活動時間、良かった点や改善すべき点などを毎回記録し、見直す習慣をつけることで、活動を継続できるようになります。
3S実施のポイント

3Sを実行するポイントは、社員の自主性を高めることです。それには最初の段階で活動の目標を明確にし、社員全体で共有することが大切。実現に向けて立てた方策に従い、活動を進めていき、必要に応じてルールや方策の見直しをしていきます。
見直しをするには、その過程を「見える化」し、現状を把握できるようにしておきます。目標や指標の達成具合をグラフや表、数値で示しておくと良いでしょう。
3Sに活用できるアイリスオーヤマのおすすめ清掃ロボ「Whiz i アイリスエディション」

清掃ロボットを活用することで3Sの品質を向上できます。アイリスオーヤマのDX清掃ロボット「Whiz i アイリスエディション」を紹介します。
「Whiz i アイリスエディション」は、搭載されたAIにより室内の構造や設置された物、人などを感知しながら、床をムラなく清掃ロボット。人による清掃に比べて、舞い上がるほこりを大幅に削減しつつ確実に汚れを取り除けます。
事前の設定を行うことで、決まった時間・場所を自動的に清掃可能です。清掃作業は完全に独立して自動で行うため、人員不足の解消やコストの削減が叶います。最大77%の清掃コストを削減できます。
〈Whiz i アイリスエディションの詳細はこちら〉
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/robotics/products/whiz-i-v2/
3Sで安全性が高く、効率的で快適な職場を実現しよう

3S活動は、整理・整頓・清掃の3つのステップを通じて職場環境を改善する手法です。3S活動により、効率的で安全な職場を実現できます。3Sの実施には社員の自主性と定期的な見直しが必要です。清掃作業を効率化し、社員のリソースを3Sの整理・整頓に集中するために清掃ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


