近年、多くの業界が人手不足に陥っています。自社の工場でも人手不足が課題となり、解消したいと考えている管理職も多いのではないでしょうか。人手不足は、早めの対策で解消できる可能性があります。
人手不足が深刻化する前に、原因や企業への影響を把握しておくことも大切です。そこでこの記事では、人手不足の原因や企業に及ぼす影響などを解説します。人手不足を解消した企業の事例も併せて解説するので、自社の課題を解決するために役立ててください。
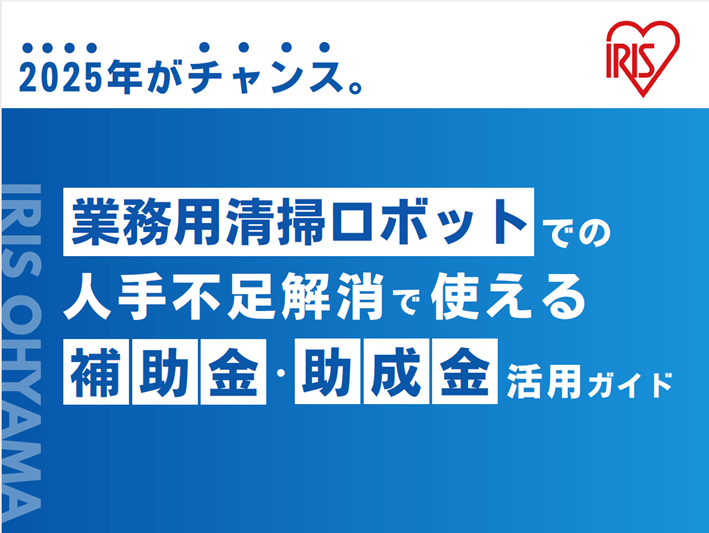
【2023年最新】工場・製造業の人手不足の現状

厚生労働省の「2022年版ものづくり白書」によると、製造業の就業者数は約20年間で157万人減少していることがわかっています。
| 年 | 製造業就業者数 |
|---|---|
| 2002年 | 1,202万人 |
| 2021年 | 1,045万人 |
また、34歳以下の若年就業者数も、約20年間で121万人減少しています。
| 年 | 製造業若年就業者数 |
|---|---|
| 2002年 | 384万人 |
| 2021年 | 263万人 |
製造業においては、15歳以上65歳未満の生産年齢人口に該当する就業者数が減少傾向にあるのが現状です。
※出典元:厚生労働省「2022年版ものづくり白書」
工場が人手不足になる原因とは?

製造業が人手不足に陥る背景には、労働人口の減少や指導する人材の不足などが関係しています。このほかにも、社会構造の変化や製造業に対するイメージなどが人手不足を加速させていると考えられています。
■労働人口の減少
製造業における人手不足の原因の一つは、少子高齢化による労働人口の減少です。総務省統計局の「労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)」によると、2019年をピークに労働人口が減少傾向にあることがわかっています。
| 年 | 労働人口 |
|---|---|
| 2012年 | 6,565万人 |
| 2013年 | 6,593万人 |
| 2014年 | 6,609万人 |
| 2015年 | 6,625万人 |
| 2016年 | 6,678万人 |
| 2017年 | 6,732万人 |
| 2018年 | 6,849万人 |
| 2019年 | 6,912万人 |
| 2020年 | 6,902万人 |
| 2021年 | 6,907万人 |
| 2022年 | 6,902万人 |
※出典元:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)」
厚生労働省の「2022年版ものづくり白書」によると、65歳以上の高齢就業者数が年々増加傾向にあり、約20年間で33万人増加していることがわかります。
| 年 | 製造業高齢就業者数 |
|---|---|
| 2002年 | 58万人 |
| 2021年 | 91万人 |
製造業においては、15歳以上65歳未満の生産年齢人口に該当する就業者数が減少傾向にあるのが現状です。
製造業の全就業者に占める高齢就業者の割合は、2018年頃から9%とほぼ横ばいで推移しています。
※出典元:厚生労働省「2022年版ものづくり白書」
労働人口の減少に加え、高齢就業者の増加による人材構成の変化が製造業の人手不足に拍車をかけているのが現状です。
■指導する人材の不足
製造業が人手不足に陥っている背景には、後進人材の教育が上手くいっていないことも関係しています。指導に関わる人材不足が顕著なのは、技能人材です。
経済産業省の「製造基盤白書(ものづくり白書)2018年版」では、特に確保が課題となっている人材として、技能人材をあげた事業所が59.1%だったことがわかっています。
| 特に確保が課題となっている人材 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 経営人材 | 7.1% | |||
| デジタル人材 | 4.1% | |||
| 技能人材 | 59.1% | |||
| 期間工 | 4.3% | |||
| 企画・マーケティング人材 | 1.0% | |||
| 設計・デザイン人材 | 8.5% | |||
| 研究開発人材 | 5.7% | |||
| 営業・販売・顧客へのアフターサービス人材 | 7.5% | |||
| 上記以外 | 2.7% | |||
※出典元:経済産業省「製造基盤白書(ものづくり白書)2018年版」
さらに厚生労働省の「2022年版ものづくり白書」によると、指導する人材が不足している事業者が6割を超えています。
| 製造業における能力開発や人材育成に関する問題点の内訳 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 指導する人材が不足している | 63.5% | |||
| 人材育成をおこなう時間がない | 51.6% | |||
| 人材を育成しても辞めてしまう | 34.5% | |||
| 鍛えがいのある人材が集まらない | 29.9% | |||
| 育成をおこなうための金銭的な余裕がない | 16.9% | |||
また、時間的な理由で十分な教育体制を整備できない事業所や、教育体制が整備できていても上手く機能していない事業所も多いことがわかっています。
※出典元:厚生労働省「2022年版ものづくり白書」
■人材の流動化
かつては終身雇用制度が浸透していたため、一つの企業で定年まで勤め上げるのが一般的でした。しかし、近年はライフスタイルや価値観の多様化により、終身雇用制度は崩壊しつつあります。人材が流動的になっているため、定着率が向上せず、人材不足に陥りやすい傾向にあります。
また、新型コロナウイルス感染症拡大を機に、新しい生活様式が普及したことで、テレワークやハイブリッドワークなどの柔軟な働き方が注目され始めました。多くの企業で柔軟な働き方が導入されたものの、工場を中心とするマンパワーが必要な現場では導入できませんでした。多様な働き方を重視する求職者も多い中で、それに対応できない工場では、新たな人材の採用に苦戦しているのが実情です。
■工場勤務へのネガティブなイメージ
製造業が人手不足に陥っている原因の一つは、世間からのイメージが関係しています。工場勤務に対しては、「きつい」「汚い」「危険」のいわゆる「3K」のイメージが定着しています。
ネガティブなイメージがある「3K」の職場を避ける求職者も多いため、製造業への応募者が減少しているのが現状です。しかし、近年はオートメーション化により、「3K」に該当する作業の多くは機械でおこなえるようになりました。
また、働き方改革により、製造業を含む多くの業界で長時間労働を是正する動きも加速化しています。工場勤務へのネガティブなイメージを払拭するためには、決して「3K」の労働環境ではないことを外部に積極的に発信する必要があります。
工場の人手不足による影響

工場が人手不足に陥ると、企業に次のような悪影響を及ぼします。
- 生産力の減少による倒産リスクの増加
- 長期的な競争力の減少
- 労働環境の悪化
人手不足になりつつある状況であれば、企業に悪影響を及ぼす前に対策を講じる必要があります。
■生産力の減少による倒産リスクの増加
人手不足が恒常化すると工場の生産力が低下し、倒産してしまうリスクがあります。特に中小企業では工場勤務の従業員が非正規雇用のケースも多く、ギリギリの状態で生産ラインを回しているところも少なくありません。
受注量が増加すれば、人手不足が原因で生産ラインを維持できない可能性もあります。たとえ業績が好調でも、生産ラインが維持できなければ顧客離れにつながり、事業の縮小や黒字倒産に至るおそれもあります。
■長期的な競争力の減少
離職率が高いことが原因で人材不足に陥っている場合は、長期的な競争力の低下を招くおそれがあります。人手不足で利益率が伸び悩むと、適切な設備投資まで資金が回らなくなり、増産体制を取ることも難しくなるでしょう。
また、工場が人手不足になると、中堅の従業員や管理職が代わりに負担を強いられる可能性があります。中堅以上の従業員が本来おこなうべき専門性の高い業務や高度な判断などに注力できなくなると、新たな価値や独自の強みを生み出しにくくなり、競争力の低下につながりかねません。
■労働環境の悪化
人手不足が深刻化すると、従業員一人当たりの業務負担が増加し、労働環境が悪化する可能性があります。政府主導の働き方改革により、企業には長時間労働の是正や有給休暇の取得義務などが課されています。
求職者も快適な労働環境を重視する傾向にあり、優秀な人材を確保し、定着率を向上させるためには、労働環境の整備が必要です。しかし、人手不足になると、残業時間の増加や疲労によるケアレスミスの増加につながるおそれがあります。また、労働環境が悪い職場では従業員のモチベーションが低下し、休職者や離職者が増加しやすいリスクがあるので注意が必要です。
工場の人手不足を解消する9つの対策

工場では、人手不足に陥る前に何らかの対策が必要です。人手不足を解消するおもな対策は、次のとおりです。
- 採用活動の見直し
- 採用枠の拡大
- 期間工や派遣人材、外部人材の活用
- 教育制度の見直し
- 従業員の待遇や福利厚生の見直し
- 業務効率化の推進
- 社内コミュニケーションの促進
- フォロー体制の構築
- 働きやすい環境づくり
特に重要になるのは、新たな人材の確保と既存人材の定着です。それでは、各項目を詳しく解説します。
■採用活動の見直し
人手不足を解消するには採用活動を見直し、休職者に選ばれる企業になることが重要です。まずは工場勤務の求人探しで、求職者にどのような項目が重視されているのかをリサーチしましょう。
求職者が重視している項目と自社の現状を照らし合わせ、課題を抽出します。次に課題の解決策を見出し、実際に改善していきます。たとえば求職者が「残業が少ない」ことを重視しているにも関わらず、長時間労働が常態化しているようであれば、労働時間の管理を徹底しましょう。
また、採用活動を進める際には、求職者が重視している項目を重点的にアピールすることも大切です。併せて、面接や採用フロー、採用活動で使用する媒体の見直しなどもおこなうと効果的です。
■採用枠の拡大
人手不足を解消するには、採用の間口を広げてシニア世代や女性、外国人などの雇用を積極的におこない、新たな人材を確保するのも手段の一つです。
シニア世代の再雇用促進
近年は、就労意欲の高いシニア世代が増えています。内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、労働力人口総数に占める65歳以上の労働者の割合は年々上昇傾向にあることがわかっています。
| 年 | 割合 |
|---|---|
| 2012年 | 9.3% |
| 2013年 | 9.9% |
| 2014年 | 10.6% |
| 2015年 | 11.3% |
| 2016年 | 11.8% |
| 2017年 | 12.2% |
| 2018年 | 12.7% |
| 2019年 | 13.1% |
| 2020年 | 13.3% |
| 2021年 | 13.4% |
※出典元:内閣府「令和4年版高齢社会白書」
現役時代に、製造業に従事した経験を持つシニア世代もいるかもしれません。実務経験が豊富なシニア世代を再雇用し、指導者として登用すると、指導者不足の解消につながるでしょう。
女性の雇用促進
厚生労働省の「2022年版ものづくり白書」によると、製造業における女性就業者数は約20年間で90万人減少していることがわかっています。女性就業者の割合は2009年頃からほぼ横ばいで、30%前後を推移しています。
| 年 | 製造業における女性就業者数 |
|---|---|
| 2002年 | 403万人 |
| 2021年 | 313万人 |
※出典元:厚生労働省「2022年版ものづくり白書」
女性就業者の割合は全産業に比べて低いものの、生産工程の自動化などを進めたり、出産や育児へのサポート体制を整備したりすることで、雇用のチャンスが生まれるでしょう。
また、近年は国が女性の活躍を推進しているため、積極的に雇用すると企業イメージのアップにもつながります。女性の場合、出産や育児、介護などで仕事を断念するケースも珍しくありません。短時間勤務を選べるようにすると、柔軟な働き方に対応できるため、雇用促進が期待できます。
外国人の雇用促進
工場の人手不足を解消するには、外国人技能実習制度を活用する方法もあります。外国人技能実習制度とは日本が国際貢献するために、発展途上国をはじめとする外国人を一定期間に限って受け入れる制度です。
製造業においては、カーペット製造やプラスチック成形などの約50種が外国人技能実習制度の対象になっています。現在までに、建設業や製造業などの多くの企業が外国人実習生を受け入れています。
■期間工や派遣人材、外部人材の活用
定期的な繁忙期や需要の増加により、一時的な人材不足を解消するには、期間工や派遣人材、外部人材への委託も視野に入れましょう。自社の従業員として雇用すると、閑散期に余剰人材を抱えるリスクがあります。
しかし、外部の人材サービスを活用すれば一時的な人員を補充できるだけでなく、固定費となる人件費をおさえることが可能です。上手く活用できれば、人材の流動化に強い組織体制を作れるでしょう。ただし、外部の人材サービスは一時的な人員補充となるため、自社の正社員を増やしたい場合は別途根本的な対策が必要です。
■教育制度の見直し
既存の教育制度を見直すと従業員の早い成長につながり、定着率の向上が期待できます。製造業における従来の教育は、「見て覚える」のが一般的でした。しかし、従業員の高齢化が進む工場ではナレッジをデータベース化し、教育やマニュアルを言語化あるいは体系化して提供する必要性が出てきました。
ナレッジマネジメントを徹底することで、指導する従業員の工数を削減しつつ、人材を効率良く育成できます。企業のなかには自社製品の情報をナレッジマネジメントツールで管理し、従業員が製品知識を習得するツールとして活用しているところもあります。
■従業員の待遇や福利厚生の見直し
近年は、待遇や福利厚生が充実した企業への就職を希望する求職者も増えています。人材の定着率が低い工場の場合、待遇や福利厚生が不十分な可能性も考えられるため、内容を見直してみましょう。
見直すべきおもな待遇や福利厚生の内容は、次のとおりです。
- 給与
- 休暇制度
- 資格取得のサポート制度
- 育児休暇
- 育児手当 など
待遇の改善や福利厚生の見直しによって働きやすい環境を整備できるため、離職率を低減し、定着率の向上が期待できます。
■業務効率化の推進
工場の人手不足を解消するには、業務効率化を図るのも手段のひとつです。業務の無駄をなくして既存従業員の負担を軽減できれば、離職による人材流出を防ぐことが可能です。たとえば、多能工を育成する方法があります。
多能工とは、一人で複数の業務を進められる人材のことです。工場に多能工が複数いると、必要に応じてさまざまな部署に配置できるため、人手不足の解消につながります。このほかには、業務のデジタル化による自動化、省人化、省力化を推進する方法もあります。
■社内コミュニケーションの促進
従業員同士のコミュニケーションが活性化すると、人手不足も解消できる可能性があります。コミュニケーションの活性化によって従業員同士の結束が生まれ、悩みや困りごとを相談しやすい環境が醸成されるからです。
直接的なコミュニケーションのほかに、掲示板やチャット、サンクスカードなどのツールを活用してみましょう。「見て覚える」が浸透している製造業では、若い従業員に対して丁寧な指導やコミュニケーションが取れておらず、離職につながっているケースも珍しくありません。円滑なコミュニケーションが取れるようになれば、信頼関係も構築され、離職の防止が期待できます。
■フォロー体制の構築
人材の流出が顕著な製造業では、従業員のフォロー体制を整備することも大切です。悩みを相談できず、離職を決断する従業員もいるかもしれません。問題が起きてからでは手遅れになるケースもあるため、企業はフォロー体制を整備し、トラブルを未然に防げるようにしておきましょう。
具体的にはマネジメント層へのコーチング研修の実施、定期面談の実施、研修制度の充実などがあげられます。さまざまな施策を通じて従業員をフォローすることで、相談しやすい環境が構築され、離職を防ぎやすくなります。
■働きやすい環境づくり
工場勤務には、いわゆる「3K」のネガティブなイメージが定着しています。人材を効率的に獲得し、流出を防ぐためには、工場勤務に対するネガティブなイメージを払拭することも大切です。ネガティブなイメージを払拭するためにも、次の「5S」を徹底しましょう。
- 整理・・・不要なものを処分する
- 整頓・・・必要なものは使いやすい場所に置く
- 清掃・・・掃除して点検を実施する
- 清潔・・・常に清潔な状態を維持する
- しつけ・・・上記の4つの「S」を習慣化する
5Sは製造業だけでなく、さまざまな業界で活用されています。たとえば看護の現場では、5Sの徹底によって医療ミスの防止につながっています。工場の場合、5Sと同時に空調や照明、におい対策も徹底し、従業員が快適に働ける環境を整備しましょう。
また、5Sを徹底して労働環境を整備した後は、自社メディアやSNSを通じて社外にアピールすると、ネガティブなイメージを払拭するのに効果的です。5Sを社内に浸透させる際には、アイリスオーヤマの清掃ロボットの活用も検討してみましょう。
清掃ロボット「Whiz i アイリスエディション」は目立つ場所だけでなく、均一に全面清掃するため、清掃品質もアップします。床をくまなくきれいにすることで、浮遊菌量が最大5分の1程度に抑制されるため、清潔な状態を維持できます。
清掃ロボット「Whiz i アイリスエディション」をはじめとするアイリスオーヤマの工場向け製品は、こちらのページに掲載されているので、ぜひチェックしてみてください。
〈アイリスオーヤマの工場向け製品はこちら〉

工場の人手不足を解消した企業事例

工場を持つ企業のなかには、独自の対策を講じて人手不足を解消したところもあります。ここからは人手不足を解消した企業の事例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
■【事例1】旭電気株式会社 様
旭電気株式会社では新規事業の着手にともない、既存の女性従業員の能力向上を課題に抱えていました。女性従業員の能力向上を図るために、女性が働きやすい環境を整備しています。具体的な施策は、次のとおりです。
- 妊娠中の配置転換を含めた配慮
- 育児休業期間中の代替要員の確保
- 育児休業中の従業員への情報提供
- 短時間勤務制度の整備 など
施策を講じた結果、4名の女性従業員が管理職に昇格しています。また、女性が働きやすい職場との評判が社外に広がったことにより、人材を採用しやすい状況になりました。
※出典元:経済産業省「中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集」
■【事例2】エイベックス株式会社 様
エイベックス株式会社では入社10年未満の従業員が約9割を占めており、早期離職や定着率の低さを課題に抱えていました。そこで教育に重点を置き、入社1年未満の従業員を対象にした導入教育や共育デーを設けました。
また、文理や性別、国籍を問わない採用方針を掲げ、採用対象の幅を拡大しています。毎週金曜日を「定時の日」に設定し、長時間残業を減らす取り組みも実施しています。その結果、離職率が低下し、労働意欲が高い女性からの応募も増えました。
■【事例3】アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマでは「人材の定着や採用」への対策として製造部でインターンシップを実施しています。
実施の目的は次のとおりです。
- 仕事内容のリアルを伝え、学生がイメージする仕事内容とのギャップを埋めるため
- 製造部門の仕事の魅力を伝えるため
夏休み期間の5日間に30名を受け入れており、会社説明や職種説明、製造ラインでの業務体験を提供しています。
工場の人手不足カバーにはテクノロジーの活用がカギ
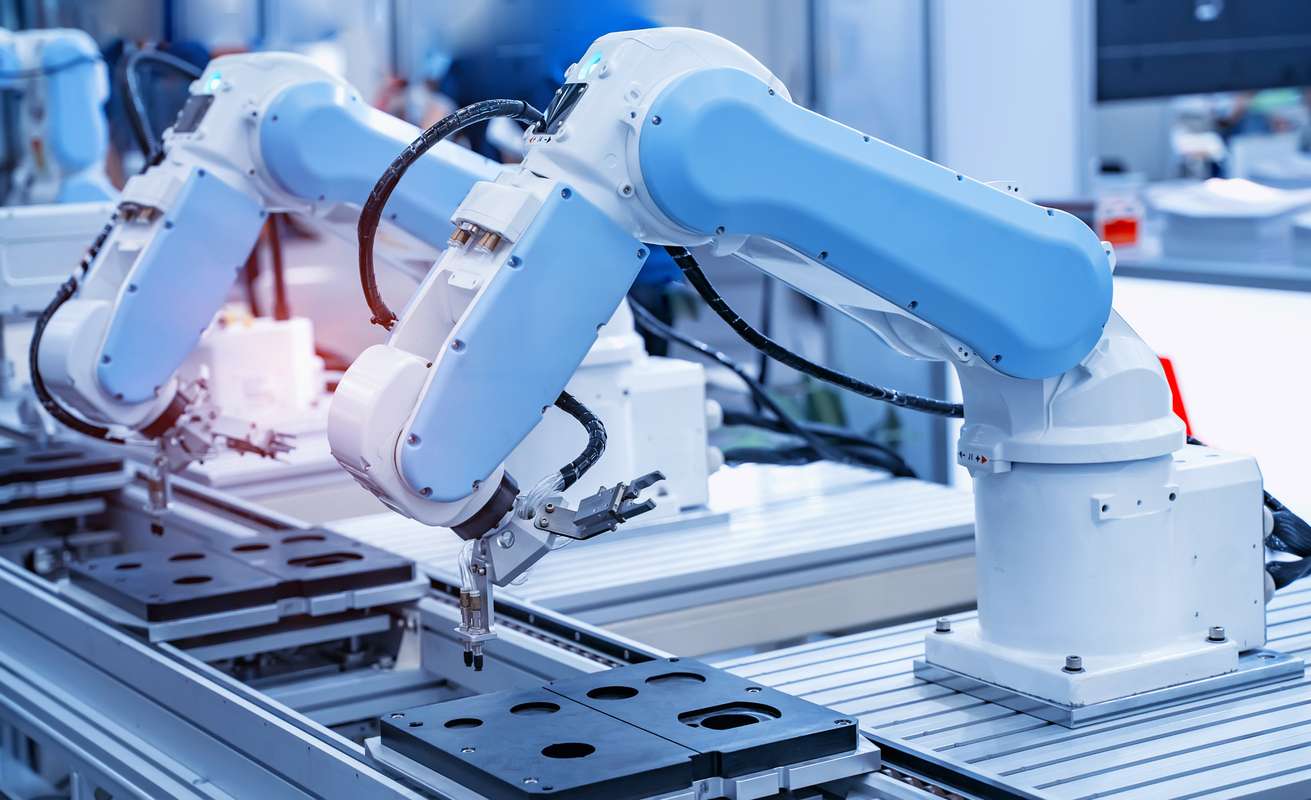
工場の人手不足を解消するには人材の増員だけでなく、定着率の向上を目指す必要があります。同時にDXの推進やITツール、ロボットの活用により、業務効率化と自動化を実現させ、人手不足をカバーすることも重要です。
DX化によって工場内の業務効率化と自動化を図れば、人手不足をカバーでき、生産力の低下を防げます。具体的にはAIで単純作業を自動化する、知識やノウハウなどのデータベース化で研修にかかる時間と手間をおさえるなどの方法があります。ただし、システムを導入するにあたり、初期費用や研修費用などのコストがかかる点には注意が必要です。
■ITツールの活用
工場の人手不足を解消する方法としては、スマートグラスやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスの活用が効果的です。たとえばスマートグラスは、レンズ部分のディスプレイを通じて実際に見えている光景に情報を重ねて表示することが可能です。
ウェアラブルデバイスを活用すると、離れた場所にいる従業員に対してリモート指導ができます。離れた場所の情報も確認できるため、工場が複数の場所にある場合に役立ちます。
■ロボットによる業務効率化
部品の運搬や清掃などの簡単作業をロボットに任せることで、不要な移動時間やミスをなくし、業務効率化が実現できます。ロボットを活用することで人的リソースを「人にしかできない作業」に割けるため、人手が確保しにくい時期での活躍が期待できます。人手の充足によってさらなる生産性の向上にもつながるため、働きやすい環境整備や人材定着に一躍買うことになるでしょう。
ロボットには、産業用ロボットとサービス用ロボットの2種類があります。特にサービスロボットにおいては大規模な設備も不要で、小規模から中規模の工場でも導入が容易であるためまずはサービスロボットの導入から検討してみましょう。
工場でサービスロボットを活用した成功事例
株式会社ライジングでは、アイリスオーヤマのサービスロボット「Keenbot」を活用しています。サービスロボットは運搬作業を代行しており、無駄な移動を削減し、資材の取り間違いといったミスもなくなりました。
サービスロボットの活用によって「人にしかできない作業」に集中できる環境を整備し、生産性の向上を実現しています。アイリスオーヤマのサービスロボットは、こちらで詳しく紹介しています。
〈アイリスオーヤマのサービスロボットの詳細はこちら〉

さまざまな施策を講じて人手不足を解消しよう
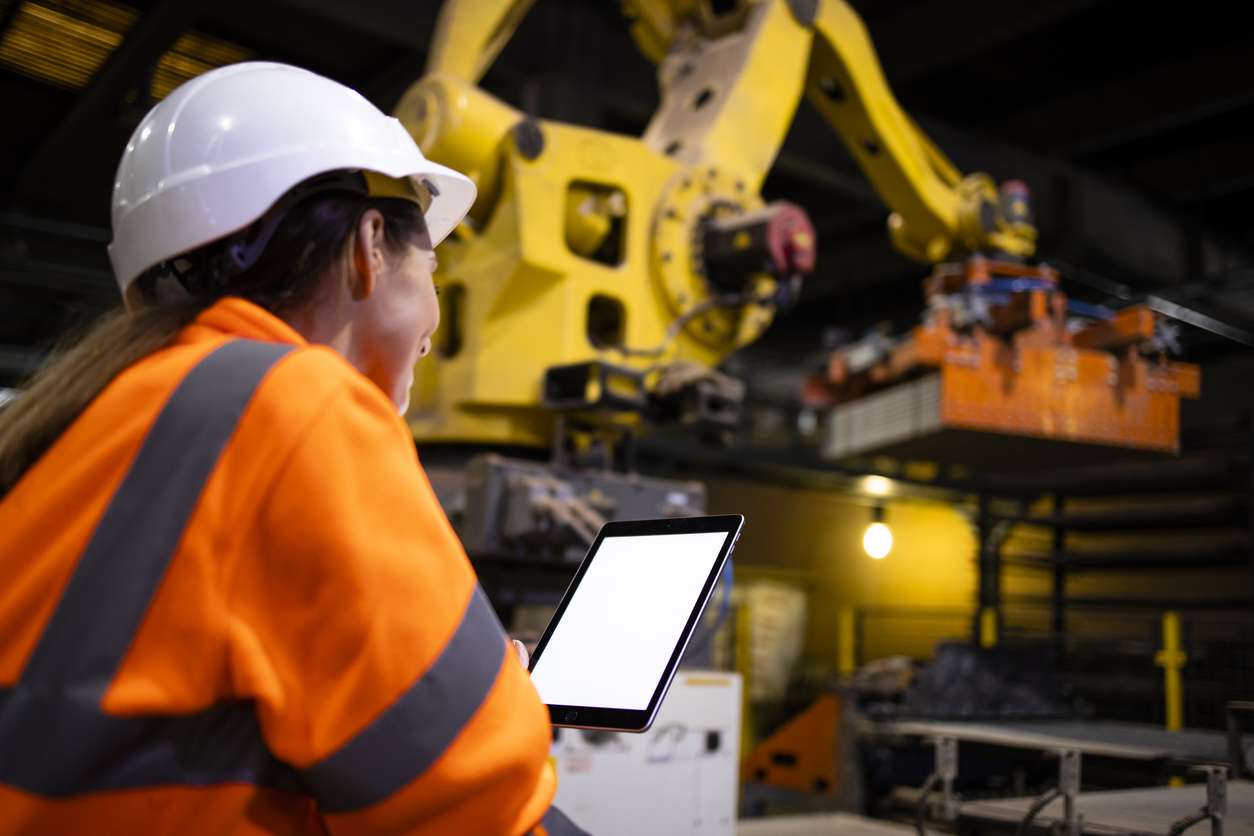
近年は、多くの業界が人手不足を課題に抱えています。少子高齢化による生産年齢人口の減少や人材獲得競争が激化している中、新たな人材を獲得するのが難しくなっています。定着率を向上させ、人手不足を解消するためにも、企業は何らかの施策を講じなければなりません。
人材不足を解消するには採用枠を広げる、福利厚生を充実させて従業員の満足度をアップするなどの方法があります。ロボットの活用は人的リソースを確保できるため、既存の従業員だけでも人手不足を解消できる可能性があります。労働環境を見直したり活用するツールを検討したりして、工場の人手不足を解消しましょう。


