企業のアルコールチェックは、運転前だけでなく運転後にも求められます。特に法改正以降、安全運転管理者の責任が増し、チェックの実施タイミングや記録保存が義務化されました。本記事ではアルコールチェックのタイミングや適切な実施方法、注意点を解説します。安全な運転管理のために押さえておきたいポイントを確認しましょう。

運転前?運転後?アルコールチェックを行うタイミング

企業の安全運転管理者がアルコールチェックを行うタイミングは、ドライバーの運転前と運転後の1日2回が基本とされています。
運転前のチェックは、酒気帯び状態で運転させないために重要です。また、アルコールチェックは運転後にも実施する必要があります。その理由は、勤務中に飲酒していなかったかを確認するためです。運転の直前や直後での実施が難しい場合は、出勤時と退勤時に行っても問題ありません。
アルコールチェックは本来、安全運転管理者が対応すべきものですが、確認者が不在の場合に備えて、副安全運転管理者や補助担当者をあらかじめ定めておき、対応可能な体制を整えておくことが重要です。
▼内部リンク 同月記事
「アルコールチェック 確認者がいない場合」
法改正後に安全運転管理者の業務に追加された内容

2022年の法改正により、安全運転管理者にはアルコールチェックの実施と記録保存が義務付けられました。さらに2023年12月から、アルコールチェッカーを使用して運転前後のチェックが求められています。追加された内容を詳しく解説します。
アルコールチェッカーを用いた酒気帯び確認
運転前後にドライバーの酒気帯びを確認することが、安全運転管理者の重要な業務として新たに加わりました。目視によるチェックに加えて、アルコールチェッカーを使用してより確実に酒気帯び状態を判断することが求められています。
結果の記録・保存とアルコールチェッカーの常時保持
アルコールチェックの結果は記録し、1年間保存することが義務付けられています。記録を適切に管理することで、警察などの確認や監査にも対応できる体制が求められます。また、アルコールチェッカーは常に正常に使用できる状態を保ち、正確な測定ができる環境を整えておくことが重要です。
【運転前・運転後】アルコールチェック実施のステップ

アルコールチェックは、「運転前後に安全運転管理者が立ち会って検知器を用いて実施し、結果を記録して1年間保存する」ことが基本となります。チェックを確実に行うためには、全体の流れを把握し、手順通りに対応することが重要です。
以下のステップを踏むことで、法令に準拠した管理体制を整えることができます。
- 運転前に安全運転管理者が立ち会い、検知器を用いてアルコールチェックを実施する。
- ドライバーが結果を記録簿に記入する。
- 運転を開始する。
- 運転後に安全運転管理者が立ち会い、再度検知器でアルコールチェックを行う。
- ドライバーが再度結果を記録簿に記入する。
- ドライバーから安全運転管理者へ記録簿を提出する。
- 安全運転管理者が内容を確認し、記入漏れ等があれば修正を依頼する。
- 確認後、記録簿は1年間保存する。
アルコールチェックで記録する8項目

アルコールチェックの結果は、正確に記録し、1年間保存する必要があります。記録すべき項目は法令で8つ定められており、抜け漏れなく記載することが重要です。
また、チェックを実施した際は、対面・非対面(ビデオ通話など)の別や確認方法も必ず記録に残す必要があります。
【記録する8項目】
- 確認者名
- 運転者名
- 自動車の登録番号または識別できる番号
- 確認の日時
- 確認の方法(アルコール検知器の使用有無、直行直帰時はビデオ通話などの方法を明記)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
以下の記事では、各内容やフォーマットなども紹介しています。
▼内部リンク
アルコールチェック記録簿に書く内容とは?運用・管理方法と効率化のカギ
アルコールチェックを正しく実施するためのポイント
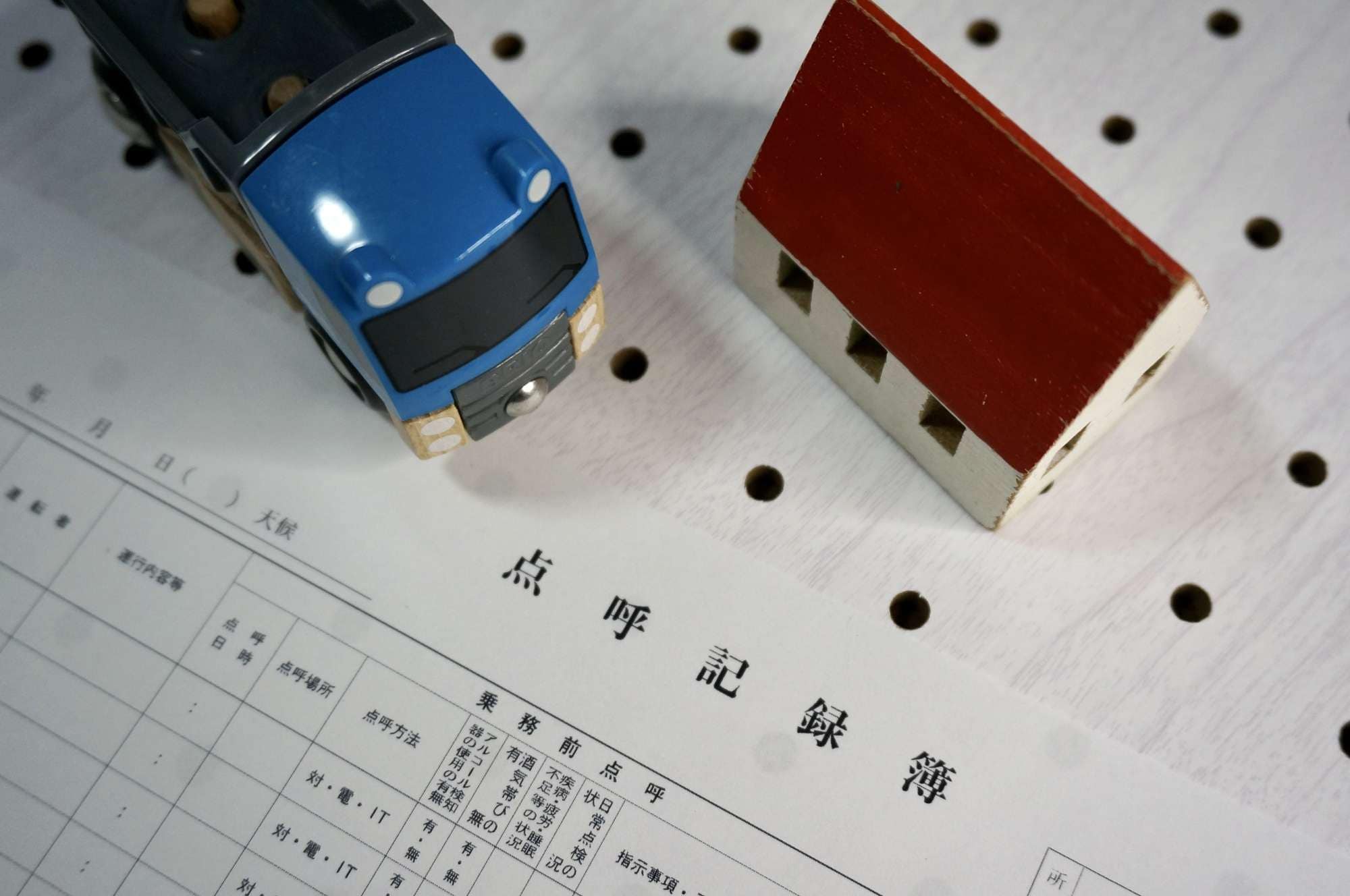
アルコールチェックを確実に実施するには、対面確認や目視・チェッカーの併用、リモート時の対応方法を正しく理解しておくことが大切です。詳しく解説していきます。
安全管理者が対面でチェックをする
アルコールチェックは原則として安全運転管理者が対面で行います。安全運転管理者による対面確認が省略されることはなく、適切な管理のもと実施する必要があります。運転者の状態確認を怠らず、ルールを徹底することが重要です。
目視とアルコールチェッカーの両方で確認する
アルコールチェックは、目視とアルコールチェッカーの両方で確認することが基本です。数値だけに頼らず、目視による確認も必ず実施する必要があります。
目視確認の主なポイントは以下のとおりです。
- 顔色に異常がないか
- 呼気にアルコール臭がないか
- 声の調子やろれつに問題がないか
- 受け答えや態度に不自然さがないか
- 身体のふらつきや異常な行動がないか
このように二重の確認を行うことで、安全性を高め、見逃しや誤検知を防ぐことができます。
直行直帰などの場合はリモートで確認する
直行直帰や出張などのケースでも、アルコールチェックは必ず実施する必要があります。対面での確認が難しい場合には、携帯型アルコール検知器を活用し、カメラやモニター、電話などの双方向の手段を用いて、顔色や声の調子、測定結果を確認することが求められます。
なお、メールやチャットなどの一方向の手段による確認は認められていません。遠隔での確認であっても、安全運転管理者が確認の責任を持つことが必要です。
※出典:警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A」
▼内部リンク
アルコールチェックが義務化!直行直帰時の対応や作業効率化のポイント
アルコールチェックを怠った場合の罰則

アルコールチェックを怠った場合、企業や安全運転管理者、ドライバーそれぞれに厳しい罰則が科されます。ここでは、安全運転管理者制度違反や飲酒運転による行政処分・刑事罰の内容を詳しく見ていきます。
安全運転管理者制度に違反した場合の罰則と処分
アルコールチェックを怠ることで、安全運転管理者制度に違反した場合には、罰金や行政処分が科される可能性があります。違反の内容に応じて処分も異なるため、事前に把握しておくことが重要です。
【安全運転管理者制度違反の内容と処分】
| 違反種別 | 内容 | 処分 |
|---|---|---|
| 選任義務違反 | 選任対象であるにもかかわらず、安全運転管理者を選任していない場合 | 50万円以下の罰金 |
| 解任命令違反 | 解任命令が出たにもかかわらず、引き続き選任または再度任命した場合 | 50万円以下の罰金 |
| 是正措置違反 | 公安委員会からの是正措置勧告に従わず、改善を行っていない場合 | 50万円以下の罰金 |
| 選任・解任届出義務違反 | 選任または解任から15日以内に所轄の公安委員会へ届出を行っていない場合 | 5万円以下の罰金 |
また、違反が繰り返される場合や重大な事故が発生した場合には、営業停止や車両使用停止といった行政処分が科されることもあります。
さらに、飲酒運転によって死傷事故が発生した場合には、企業や管理者に対して刑事罰や民事責任が問われる可能性もあるため、十分な注意と対策が必要です。
▼内部リンク
アルコールチェックを怠った場合の罰則を解説|安全運転管理者にもペナルティはある?
ドライバーが飲酒運転をした場合の罰則と処分
飲酒運転は重大な違反行為であり、刑事罰と行政処分の両方が科されます。違反の内容によって罰則が異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
また、飲酒運転はドライバー個人の問題にとどまらず、企業全体のリスクにつながるため、従業員への教育と管理体制の徹底が不可欠です。
【ドライバーが飲酒運転した場合の罰則と行政処分】
| 運転の状態 | 呼気中アルコール濃度 | 違反点数 | 行政処分 | 罰則 |
|---|---|---|---|---|
| 酒気帯び運転 | 0.15mg/L以上~0.25mg/L未満 | 13点 | 免許停止(90日間) | 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 0.25mg/L以上 | 25点 | 免許取消(欠格期間2年)※ | 同上 |
| 酒酔い運転 | 数値ではなく酩酊の有無で判断 | 35点 | 免許取消(欠格期間3年)※ | 5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
※ 欠格期間とは、免許取消処分後に再取得できない期間です。
なお、酒酔い運転はアルコール濃度の数値ではなく、ろれつが回らない、正常な受け答えができないなどの明らかな酩酊状態によって判断されます。
アルコールの基準値に関しては、以下の記事も参考にしてください。
アルコールチェッカーの正しい使い方

アルコールチェッカーは、しっかりと息を吹きかけないと正確な測定ができません。吹き込みが不十分な場合や、風の影響を受けやすい場所で使用した場合には、誤検知やエラーが発生する可能性があります。
アルコールチェッカーには主に3つのタイプがあり、使用前に取扱説明書を確認し、それぞれの操作方法を正しく守ることが大切です。
【吹きかけ式】
- 機器の吹き込み口に直接息を吹きかけて測定する。
- 簡単に使えるが、周囲の空気の影響を受けやすいため注意が必要。
【ストロー式】
- ストローを本体に差し込み、息を吹き込んで測定する。
- ストローを通すため精度が高く、環境の影響も受けにくい。
- 衛生面を考慮し、ストローは毎回交換する。
【マウスピース式】
- 専用のマウスピースに息を吹き込んで測定する。
- 高精度な測定が可能で、機種によっては吹きかけ式・ストロー式と兼用できるものもある。
- マウスピースの清掃や交換も忘れずに行う。
正しい使い方を徹底することで、測定精度を保ち、誤検知やトラブルを防ぐことができます。
アルコールチェッククラウド管理サービス「ALPiT Pro」

ALPiT(アルピット)は、携帯型アルコールチェッカーの測定データをクラウドで自動記録・保存できる管理サービスです。測定結果はリアルタイムで反映され、管理者の作業負担や確認の手間を大幅に軽減することができます。
紙での管理にありがちな記載漏れや紛失のリスクがなく、ヒューマンエラーや記録ミスの防止にもつながります。
また、検知器とセットになったプランも用意されており、アルコールチェック業務全体の効率化と安定した運用が実現可能です。
〈ALPiT(アルピット)の詳細はこちら〉

アルコールチェックは運転前・運転後に実施し安全管理を徹底しよう

アルコールチェックは、運転前と運転後に実施する必要があります。記録項目やチェック方法など細かなルールが定められており、違反すれば企業や運転者に厳しい罰則が科されます。安全運転管理者は正しい運用を徹底することが重要です。本記事の内容を参考に、現場のチェック体制や記録方法をぜひ見直してみてください。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


