2022年の道路交通法改正により、白ナンバー車両を一定台数以上使用する企業にもアルコールチェックの義務が課されるようになりました。これまで対象外だった一般企業でも、運転前後の酒気帯び確認や記録保存が求められるようになり、管理業務にも大きな影響を与えています。この記事では、義務化の対象となる事業所の条件から、実施する方法、必要な準備までを解説します。
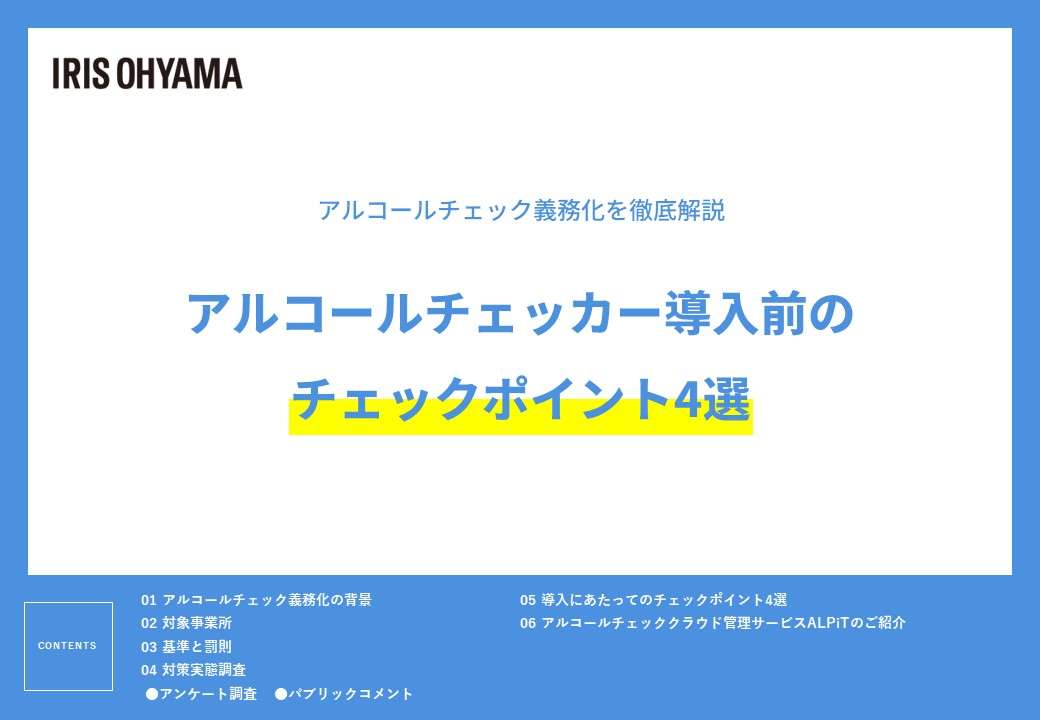
アルコールチェック義務化の概要

アルコールチェック義務化とは、白ナンバー車両を一定台数以上保有する企業に対し、運転前後に酒気帯びの有無を確認することを義務付ける制度です。道路交通法が2022年4月に見直されたことで、従来の緑ナンバー(運送業・旅客業など)に加え、営業車を使う一般企業にも適用対象が拡大されました。
国土交通省は、点呼時のアルコール検知器の使用を明確に義務付けていて、企業には法令に準じた対応が求められています。
▼外部リンク:国土交通省「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/

アルコールチェック義務化の対象者

アルコールチェック義務化の対象者は、段階的に緑ナンバーの事業用車両を保有する運送・旅客業者に加え、白ナンバー車両を一定台数以上保有する一般企業にも拡大されました。
2011年5月から対象「運送業や旅客業などの緑ナンバーの事業者」
2011年5月からは、トラック・バス・タクシーなど緑ナンバーの事業用車両を保有する運送業や旅客業者に対し、アルコール検知器を用いた点呼の実施と、事業所内への検知器の備え付けが義務化されました。対象となるのは、有償で人や物を運ぶ事業者であり、当初はこうした緑ナンバー車両のみが規制の対象とされていました。
2022年4月から対象「一定台数以上の社用車を保有する白ナンバー事業者」
2022年4月の法改正により、白ナンバー車両を一定台数以上保有する一般企業も新たにアルコールチェック義務化の対象に加わりました。対象となるのは、1事業所あたり「白ナンバー車を5台以上」または「定員11人以上の車両を1台以上」保有している企業です。なお、バイク(原付を除く)は0.5台としてカウントされます。
営業車や送迎車などを日常的に運用している企業の多くがこの条件に該当するため、自社が対象となっているかを確認し、早めに体制整備を進める必要があります。
アルコールチェックの義務化が拡大された背景

アルコールチェックの義務が一般企業にまで拡大された背景には、2021年に千葉県八街市で発生した重大な交通事故があります。飲酒運転をしていた白ナンバーのトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、5人が死傷するという痛ましい事故となりました。運転者からは基準値を超えるアルコールが検出されましたが、当時は白ナンバー車両にチェック義務がなかったため、防げたはずの事故とも言われています。
この事故を契機として、飲酒運転の再発防止と企業の安全管理強化を目的に法改正が進み、従来の緑ナンバーだけではなく、白ナンバー車両にもアルコールチェック義務が拡大されることになりました。
義務化されたアルコールチェックの内容

アルコールチェックの義務化は、段階的に内容が強化されています。ここでは、それぞれの義務内容について解説します。
2022年4月から義務化された基本チェックの内容
2022年4月の法改正により、事業所では運転前後にドライバーの酒気帯びを目視などで確認し、その結果を1年間保存することが義務化されました。確認は出発時だけではなく、帰社後にも実施する必要があり、業務全体を通して酒気帯びがないことを確認する体制が求められます。この取り組みは、安全運転管理者の責任のもとで行われ、点呼を通じて確実に実施される仕組みづくりが重要とされています。
2023年12月からはアルコール検知器の使用・保守義務が追加
2023年12月からは、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されました。単に設置するだけではなく、常に有効な状態で保持することが求められ、営業所への設置や、直行直帰などに対応するための携行型の導入など、運用体制の見直しも必要となっています。
また、アルコール検知器は設置しているだけでは不十分であり、管理者はその機器の電源が入るか、破損がないかを毎日確認し、週1回は正常に作動するかどうかの動作確認も行わなければなりません。
アルコールチェックの実施方法4ステップ&ポイント

アルコールチェックの実施は、適切な手順で行うことが重要です。ここでは、実施に必要な4つのステップについて解説します。
1. 安全運転管理者を選任する
アルコールチェックの実施にあたり、まず最初に必要なのが安全運転管理者の選任です。安全運転管理者は、企業や団体において運転者の飲酒状況を確認し、適切な指導・管理を行う責任者であり、アルコール検知器を使用して定期的にチェックを行います。
この選任は法令により義務付けられていて、定員が11名を超える車両を1台でも保有している、またはその他の車両を5台以上保有する事業所には、1名の安全運転管理者を置く必要があります。選任や解任があった場合は、15日以内に管轄の公安委員会へ届出しなければなりません。選任義務に違反すると、50万円以下の罰金が科されることがあります。安全運転管理者は、交通事故防止に向けた社内教育や啓発活動などの重要な役割を担います。
2. 運転前後にアルコールチェックを実施する
アルコールチェックは運転の直前・直後に限定する必要はなく、出勤時や退勤時に実施しても法令上問題ありません。そのため、朝礼や終業点呼に組み込むことで、日常業務の妨げにならずに実施することが可能です。
また、直行直帰の業務や遠隔地での運転者に対しては、ビデオ通話や電話でのIT点呼も認められていて、柔軟な対応が可能。対面でのチェックでは、表情・声の調子・呼気のにおいなど、目視による確認も重要な判断材料になります。
3. アルコールチェックの内容を記録する
チェックの実施後には、記録を残すことが法律で義務化されています。記載すべき項目は以下のとおりです。
<記載すべき主な項目>
・日時
・運転者名
・確認者名
・車両番号
・使用機器
・確認方法
・結果
・指示事項
特に2023年12月以降は、アルコール検知器の使用を明記することが必要になりました。記入漏れやミスを防ぐために、専用の記録簿や管理システムを活用し、運用ルールを徹底することが大切です。

4. 記録は1年間保存する
作成したアルコールチェックの記録は、紙・デジタルいずれの形式でも構いませんが、1年間は保管しなければなりません。記録は月ごとなどで整理し、誰が見てもすぐに確認できる状態に保つことが理想です。
特に法令違反や万が一の事故が発生した際には、記録の有無が企業の管理責任に直結します。保存漏れや紛失を防ぐためにも、保存フローの整備と、定期的な見直しが欠かせません。
アルコールチェック義務化で必要な準備

アルコールチェック義務化に対応するには、体制の整備と業務フローの見直しが不可欠です。安全運転管理者の選任をはじめ、実務に適した検知器の導入や記録・保存の仕組みづくりを進めることで、スムーズな運用と法令遵守が可能になります。ここでは、義務化対応に必要な準備を3つ紹介します。
1.安全運転管理者の選任と体制整備をする
アルコールチェック義務化に対応するうえで、最初に行うべきなのが安全運転管理者の選任です。未選任の場合は5万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。
既に安全運転管理者を選任している場合でも、アルコールチェックという新たな業務が追加されたことを踏まえ、業務フローや体制の見直しが必要です。
2.運用に合ったアルコール検知器を導入する
アルコール検知器の導入においては、自社の運用方法に適した機器を選ぶことが安全管理の基本です。2023年12月以降は、国家公安委員会が定める、音・光・数値などで酒気帯びを判定できる検知器の使用が義務化されていて、メーカーは問われないものの、記録機能の有無や携帯性、消耗品の管理などを事前に確認することが求められます。
さらに、機器を常時正しく使える状態に保つためには、定期点検や消耗品の補充も欠かせません。
3.記録・保存の仕組みを確立する
アルコールチェックの結果は、1年間の保存が法律で義務付けられているため、記録方法と保存体制の明確化が必要です。紙でもデジタルでも構いませんが、紙の場合はファイルによる整理、デジタルの場合はフォルダ名や保存場所の統一など、社内でのルール設定が重要になります。
さらに、酒気帯びが確認された場合の対応フローをあらかじめ定めておくことで、万が一の際にも慌てずに対応できます。
アルコールチェック義務を怠った場合の罰則規定

アルコールチェックの未実施は、安全運転管理者の業務違反にあたります。現時点でチェックを怠ったこと自体に直接的な罰金は科されませんが、公安委員会から是正命令や管理者の解任命令が出される可能性も。命令に違反すれば罰則対象となり、企業の信頼にも大きな影響を及ぼします。
飲酒運転が発覚した場合の罰則
| 分類 | 処罰 | 違反点数(運転者のみ) |
| 酒酔い運転 | 年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 35点(免許取消・欠格3年) |
| 酒気帯び運転(0.25mg/L以上) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 25点(免許取消・欠格2年) |
| 酒気帯び運転(0.15〜0.25mg/L未満) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 13点(免許停止90日) |
関係者も罰則の対象
飲酒運転に関連する罰則は、運転者以外の関係者にも適用される点に注意が必要です。
| 関係者 | 酒酔い運転の場合 | 酒気帯び運転の場合 |
| 車両提供者(会社・管理者) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 酒類提供者 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
| 同乗者 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
罰則は広範囲に及ぶため、企業としての信頼維持や再発防止の観点からも、就業規則にアルコールチェックの実施を明記することが重要です。管理者やドライバーだけに任せるのではなく、企業全体で取り組む体制づくりが、安全対策の実効性を高めます。
アルコールチェック業務を効率化!アイリスオーヤマのALPiT

「ALPiT(アルピット)」は、アイリスオーヤマが提供するアルコールチェックのクラウド管理サービスです。アプリを起動してアルコールチェッカーに息を吹き込み、測定結果を確認後に顔写真を撮影するだけで、結果は自動的にクラウドへ送信されます。
送信されたデータは管理画面上でリアルタイムに確認できるため、安全運転管理者は拠点ごとのチェック状況をひと目で把握可能。紙やExcelで手作業していた記録集計や帳簿管理といった業務が不要になり、業務負担の大幅な削減と運用の効率化が実現します。
さらに、端末の寿命に合わせて毎年交換用センサーが自動で届くため、機器の買い替えや寿命管理の手間もありません。月額料金には本体代も含まれていて、継続的に安心して運用できる仕組みが整っています。
<ALPiTの詳細は詳しくはこちら>
アルコールチェック義務化の対象者は適切な体制を整えよう

アルコールチェック義務化の対象となる企業は、安全運転管理者の選任や記録の保存など、適切な体制づくりが欠かせません。法令を正しく理解し、実施や管理方法を整えることで、リスクを未然に防ぎましょう。クラウド管理サービスの活用も、効率化の有効な手段です。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


