工場清掃は単なる美観維持にとどまらず、生産効率の向上、従業員の安全確保、製品品質の安定に直結する重要な業務です。この記事では、工場清掃の重要性を掘り下げ、手順や効率化のための方法、注意点について解説します。さらに清掃業務の効率化やコスト削減に役立つ清掃ロボットも紹介しますので、参考にしてください。
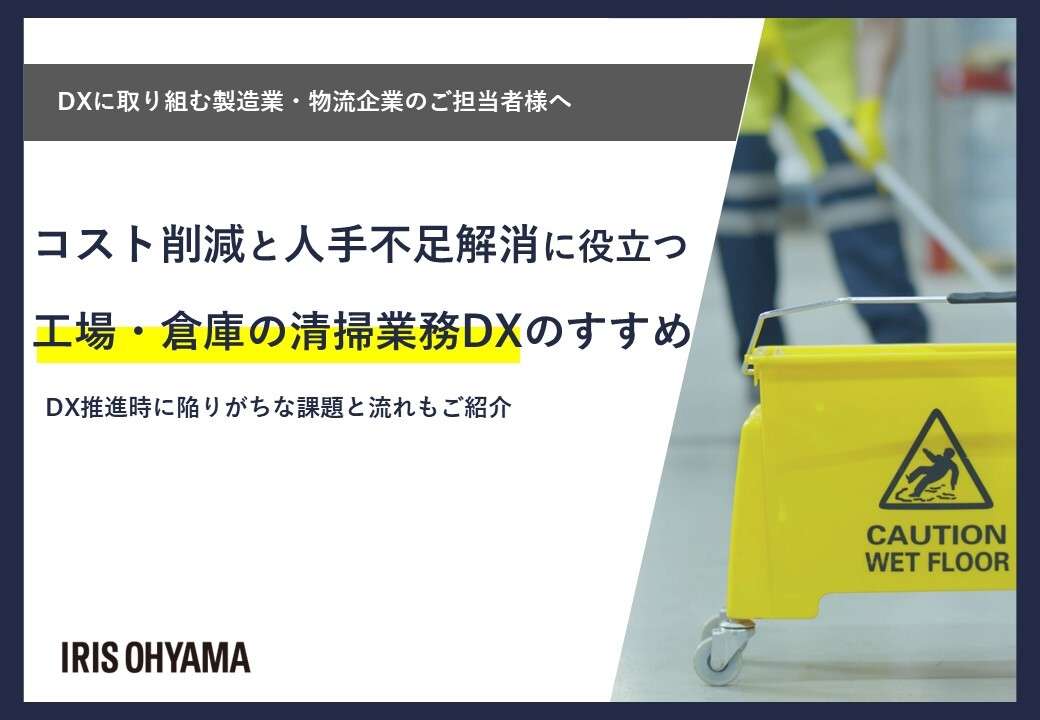
工場清掃の重要性とは

工場清掃は、単に環境をきれいにするだけではなく、生産性や安全性、品質管理に関わるために重要です。汚れやゴミを放置すれば、製品への異物混入や機械トラブルを引き起こし、不良品の発生や設備故障につながって修理費用や廃棄コストの増加を引き起こします。
清掃は、5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の基本でもあり、継続的な環境改善の第一歩です。清潔で整った作業環境は、必要な物を探す無駄な時間がなくなり、作業効率が向上します。さらに従業員のモチベーション維持にも効果的です。工場清掃を習慣化することで、品質の安定、業務の効率化、コスト削減、そして企業イメージの向上にもつながります。
▼内部リンク
工場における5Sとは?取り組むメリットや進め方を解説
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/itrends/articles/2933/
工場清掃のメリット

工場清掃は単なる環境整備以上に、作業の効率化や企業イメージ向上に大きく貢献します。主なメリットである作業の効率化、異物混入リスクの軽減、従業員のモチベーション向上、企業イメージの向上について解説します。
作業の効率化・生産性の向上
清潔で整理された工場環境は作業の流れをスムーズにし、生産性を高めます。工具や資材が定位置にあり、床面が清掃されていることで、作業員は無駄な移動や探しものを減らせます。機械のメンテナンスが容易になり、稼働率向上にもつながるため、生産目標の達成がより現実的になるでしょう。
異物混入リスクの軽減
定期的な清掃により、工場の生産ラインや作業エリアを清潔に保て、異物混入のリスクを大幅に軽減できます。工場における異物混入の主な原因は、掃除道具や備品の破片、毛髪や埃など。適切な清掃ができていれば、備品の異常にも気づきやすくなります。日常的な清掃を習慣化することがリスク対策として有効です。
従業員のモチベーション向上
清潔な職場環境は従業員のモチベーション向上につながります。汚れた環境ではストレスが溜まり、作業意欲が低下する一方、整理整頓された環境では集中力も高まり、安全意識も向上します。モチベーションを維持できれば、業務効率化、生産性向上、離職率の低下といった効果も期待できるでしょう。
企業イメージの向上
清掃の行き届いた工場は、訪問者に好印象を与えるのも大きなメリットです。特に取引先や監査機関、採用面接で来社する求職者にとって、清潔で整った環境は「信頼できる会社」といったプラスのイメージにつながります。
応接室や会議室といった来客対応スペースは、日頃から丁寧に清掃を行うことが重要です。外部からの訪問が多い工場では、特に日常的な清掃を徹底しましょう。
工場清掃の手順

工場の清掃には、ドライ方式とウェット方式の2種類があります。ドライ方式は、水を使わずにゴミを除く方法で、ウェット方式は水を使って床を洗浄する方法です。
ドライ方式の清掃手順
ドライ方式は水を使わずに床を清掃する方法です。
<手順>
1. ほうきや掃除機などで床の埃やゴミを取り除く
2. ウェットモップで床を水拭き。汚れがひどい場合は洗剤を溶かした水を使用する
3. ドライモップで床の水気を拭き取る
水気が残っていると転倒の原因になります。水気を残さないように、最後はドライモップで徹底的に拭き取りましょう。
ウェット方式の清掃手順
ウェット方式とは、床に排水溝が付いた工場で行う清掃方法です。水を流せるので洗浄しやすいのが特徴です。
<手順>
1. ほうきや掃除機などで床の埃やゴミを取り除く
2. ウェットモップで床を水拭きする
3. 汚れがひどい場所には、洗剤を撒いて油や汚れが浮くように馴染ませる
4. 汚れが浮いたらブラシでこすり洗いをする
5. 水で洗い流す
6. スクイジーやワイパーで水をしっかり排水溝に流す
7. (場所に応じて)ドライモップで水気を拭き取る
工場清掃の頻度

工場清掃の頻度は、工場の業種や生産プロセス、製品の特性、衛生基準によって異なりますが、一般的には日常清掃と定期清掃に分けられます。それぞれについて説明します。
日常清掃
日常的な汚れを落とすために行う日常清掃は、毎日行うのが理想です。汚れは付着した直後が落としやすいので、汚れが付きやすい場所や使用頻度の高い場所は、毎日、簡単に掃き掃除やモップがけを。例えば当番を決め、当番の従業員は15分~20分程度仕事を切り上げ、掃除をするなどが有効です。
従業員に清掃の大切さを意識づけし、習慣化しましょう。汚れが多くつきやすい場合は、業者に依頼するのもおすすめです。
定期清掃
定期清掃は日常清掃でカバーできない部分を徹底的に清掃するもので、月に1回~数ヵ月に1度程度が目安です。清掃が困難な場所や危険が伴う場所、専門知識が必要となることもあり、専門業者に依頼するのが一般的です。工場の汚れ具合や予算によって、依頼する頻度を決めましょう。
工場清掃を効率化する5つの方法

工場内の清掃を効率よく行うためには、作業環境や道具の管理を見直すことが大切です。日々の清掃作業を効率化するための方法5つを紹介します。
整理整頓の徹底を心がける
効率よく清掃するには、整理整頓が必須です。整理整頓は5S活動の要素です。整理整頓がされていないと、清掃を行う前に散らかったものを移動させる必要があり、効率が悪くなります。
ものの置き場所を決め、使用後は定位置に戻すように徹底しましょう。効率よく清掃できるだけではなく、紛失に気づきやすくなり作業効率もアップします。従業員全員が道具の定位置を把握できるように、置き場所に道具の名前や数を書いておくのがおすすめです。
高さがあるものは設置しない
工場内や更衣室には、棚やロッカーといった高さがあるものは避ける方が無難です。高さがあるものの上は埃などが溜まりやすく、清掃しにくいためです。溜まり続けて落ちてきた埃などが作業着や道具に紛れ込むと、異物混入を招いてしまいます。高さのある棚やロッカーの設置が必要な場合は、上部に傾斜をつけるなど工夫しましょう。
空間を確保して配置する
壁や床とものとの間に、清掃道具が入る空間を確保します。壁や床に接しているものはゴミが溜まりやすく、清掃時にものを動かす手間も発生します。ブラシやモップを差し込んで清掃できる空間は約15cm、人が入り込んで清掃できる空間は約60cm程度です。清掃道具が入る空間を確保できるように、余裕を持って設備配置しましょう。
空間の確保が難しい場所では、ものや壁の隙間を完全に埋めてしまったり、キャスターをつけて移動しやすくしたり工夫してください。
場所や用途ごとに清掃道具を使い分ける
清掃用具は、清掃場所や用途ごとに用意して使い分けます。汚れた場所で使った用具で別の場所を清掃すれば、かえって汚れを広げてしまう恐れがあります。汚染場所と清潔な場所の清掃用具はしっかり使い分けましょう。複数の場所で同じ種類の用具を使う場合は、使用箇所別に違う色のテープを貼るなど、誰でも一目でわかる状態で保管してください。
清掃マニュアルを作成する
効率よく清掃する方法をまとめた清掃マニュアルを作成し、従業員に配布します。清掃マニュアルには、清掃箇所や工程、清掃用具の手入れ方法など可能な限り詳細に明記してください。
サイズなど持ち運べるように工夫した清掃マニュアルを配布したり、作業場所に掲示したりすることで従業員がこまめに確認でき、正しい方法で素早く清掃できます。従業員一人ひとりの清掃の質を統一し、常に良い衛生状態を保てるでしょう。
工場清掃の注意点

工場清掃は安全性や作業効率にも直結する重要な業務ですが、やり方を誤ると思わぬトラブルを招くこともあります。工場清掃を行う際に押さえておくべき注意点を解説します。
従業員全体で取り組む
一部の人に任せるのではなく、従業員全体に清掃の重要性を意識づけし、一体となって取り組みましょう。効率よく清掃できる環境を整えても、従業員が清掃への重要性を理解しなければ適切に継続できません。従業員に清掃の重要性を周知し認識してもらうことで、マニュアルの順守を徹底します。ただし従業員が毎日できる清掃には限りがあります。工場が広い場合は人数の増員や業者への委託を検討してみてはいかがでしょうか。
機械を止めてから清掃する
機械を清掃する際は必ず機械を止めてから行ってください。工場には至る所に機械があったり、強力な洗剤を使ったりするので危険が伴います。思わぬ油断が事故につながります。清掃時には機械を止めるように徹底し、従業員の安全を十分に確保しましょう。
床の清掃に留意する
工場の床には埃や油、ゴミといったさまざまな汚れが付着しているので、特に清掃に気をつけましょう。きちんと清掃せずに放置していると汚れが溜まり続け、取り除くのが難しくなります。汚れが付着した状態で足元がすべって転倒したり、悪臭が発生したりなどの恐れがあります。効率的、効果的な清掃のために床洗浄機の導入もおすすめです。
害虫・害獣駆除は専門業者に依頼する
害虫や害獣の駆除は個人では難しいため、専門業者に依頼してください。予防策として捕虫器の設置による工場内への侵入防止や、日々の清掃で害虫や害獣のエサになるものを取り除くなどが考えられます。まずは予防策を徹底し、害虫や害獣の発生を防ぎます。万が一、発生した場合は専門業者による完全駆除を依頼しましょう。
工場清掃に効果的なアイリスオーヤマの清掃ロボット
アイリスオーヤマの清掃ロボットは、幅広い用途に対応できる4モデルを揃えています。工場の規模や求める機能に合わせて選べます。
Whiz i アイリスエディション

清掃コストを最大77%削減※でき、ボタン1つで簡単に操作できる清掃ロボットです。
多くの業務用ロボットは清掃ルートをプログラミングする必要がありますが、Whiz i アイリスエディションは手押しで動かして清掃ルートを登録すれば、2回目以降はスタートボタンを押すだけで登録したルートの自動走行が可能です。床清掃をWhiz i アイリスエディションに任せ、人はそれ以外の作業に集中できます。清掃ムラを防ぎ、障害物や動くものを感知すると止まるなど安全性が優れているのも特徴です。
導入前には、専任担当者が活用方法を丁寧にレクチャーし、導入後もカスタマーサクセスチームによるアフターサポート体制が整っています。
<「Whiz i アイリスエディション」の詳細はこちら>

※1.800㎡での清掃を想定した比較。日本ビル新聞社「『ビルメンテナンスの積算&見積』カーペットの作業能率」を参照し当社にて試算。
BROIT

BROITは、日本の清掃基準を満たすために開発された床清掃ロボットで、特に高い清掃品質が魅力です。強力な床洗浄力で汚れを効果的に取り除き、床材や汚れの種類に合わせた3つの清掃モードを備えています。シンプルな操作で、誰でも簡単に扱えるよう設計されているのも特徴。障害物や段差を検知する安全設計と、遠隔監視によるサポート体制も備えられており、安心して使用できます。
< 「BROIT」の詳細はこちら >

Phantas アイリスエディション

吸引から掃き掃除、水洗浄、モップ掃除と多彩な機能を備えた製品です。
充電ステーションに戻るようセットすれば自動で充電可能です。狭い通路やテーブルの下なども通り抜けられるコンパクトなサイズで幅広い用途に使えます。
・アプリを使ってスマートフォンから清掃タスクのスケジューリングや、清掃実績のデータを確認できるのもメリットです。また障害物に対して0cmまで接近して清掃できる、サイドブラシと高精度センサーも特徴です。
壁際にたまった汚れも残さず一掃できます。障害物回避能力に優れ、リアルタイムで障害物を察知しスマートに避けて走行可能です。
<「Phantas アイリスエディション」の詳細はこちら>

Scrubber 50 Pro アイリスエディション

大規模施設に最適な清掃ロボットです。
18Lの水が入る大容量タンクを備え、1回の充電で900㎡の範囲を清掃可能です。オート充電と循環の機能の組み合わせで最大4,000㎡を清掃でき、大規模施設にも対応します。25kgのブラシ圧で汚れを強力洗浄。6種類のパッドとブラシがあり、用途や床材に最適な清掃コンディションを実現できます。
<「Scrubber 50 Pro アイリスエディション」の詳細はこちら>

効率的な工場清掃で、生産性と安全性を向上させよう

工場清掃は、生産性の向上や従業員の安全、企業イメージの向上に欠かせない重要な業務です。日々の清掃を効率的に行うためには、5Sを基本とした環境づくりや清掃マニュアルの整備、さらに従業員全員で取り組む意識も不可欠です。アイリスオーヤマの清掃ロボットを活用すれば、効率とコスト削減が実現できます。適切な清掃計画を立てて、安全で清潔な工場運営を目指しましょう。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


