2022年の法改正により、一定の条件を満たす事業所ではアルコールチェックが義務化されました。しかし実際の運用では、安全運転管理者が不在となる場面も少なくありません。本記事では、義務化と安全運転管理者の概要、確認者がいない場合の正しい対応方法と、効率化する方法について解説します。
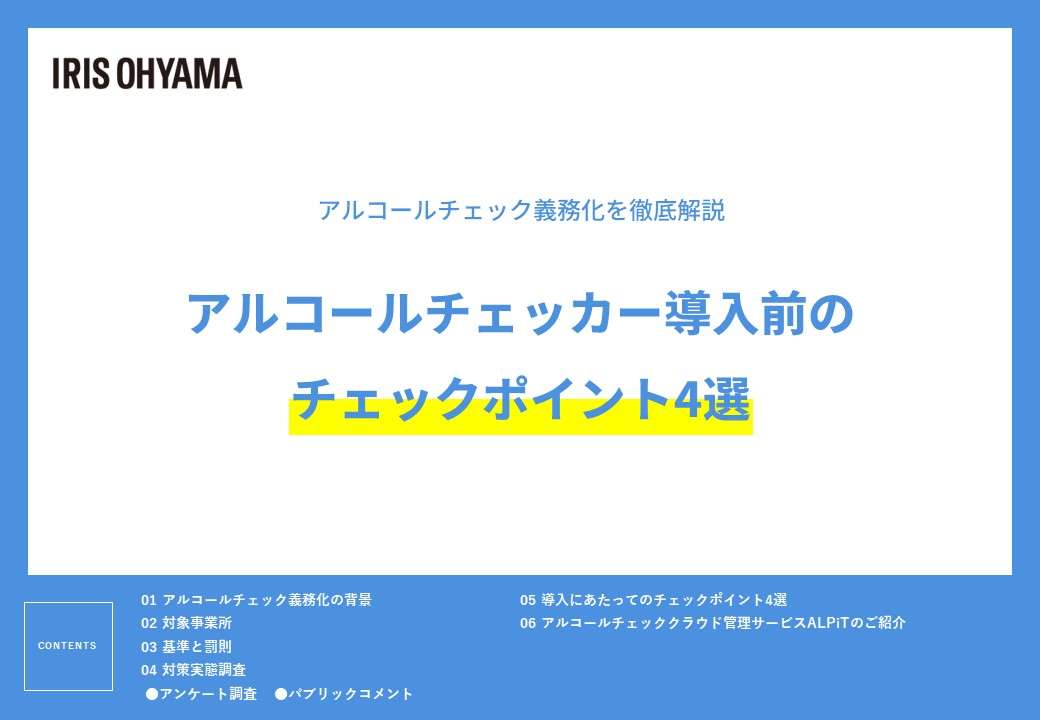
アルコールチェック義務化とは|まずは基本をおさらい

白ナンバーの社用車を一定台数以上保有する企業では、安全運転管理者の選任と、運転前後にアルコールチェックの実施・記録が法律で義務付けられています。2022年4月の法改正により、目視等による酒気帯びの確認と記録保存が必須となり、さらに2023年12月からはアルコール検知器を用いた測定と、機器の常時有効保持も義務化されました。
こうした法改正の背景には、白ナンバートラックによる重大な飲酒事故があり、アルコールチェックの対象が特定業種から全業種へと広がるきっかけとなりました。
▼内部リンク:アルコールチェック義務化とは?対象事業所や怠った場合の罰則を解説
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/itrends/articles/3353/
アルコールチェックの確認者とは?

アルコールチェックの実施には、記録や確認を担う確認者の存在が欠かせません。ここでは、安全運転管理者を始めとする確認者の役割やそれぞれの違いについて解説します。
アルコールチェックの確認・記録をする役割を持つ者
アルコールチェックの確認者とは、運転者の酒気帯びの有無を確認し、その結果を記録する役割を持つ人物です。確認者として認められるのは、安全運転管理者、副安全運転管理者、またはその業務を補助する者に限られています。
単なる同僚や本人による自己申告は原則として認められておらず、体制が整っていないまま運用すると、法令違反と見なされる可能性もあります。
▼内部リンク:安全運転管理者とは│選任基準・資格要件・業務内容などわかりやすく解説
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/itrends/articles/3456/
安全運転管理者・副管理者・補助者の違い
確認者として認められる安全運転管理者、副安全運転管理者、補助者には、それぞれ業務範囲や資格要件、届け出義務の有無などに違いがあります。
安全運転管理者・副管理者・補助者の違い
確認者として認められる安全運転管理者、副安全運転管理者、補助者には、それぞれ業務範囲や資格要件、届け出義務の有無などに違いがあります。
| 区分 | 業務内容の範囲 | 資格要件 | 届出の要否 |
|---|---|---|---|
| 安全運転管理者 | 健康・アルコールチェック、安全運転教育、記録管理全般 | ・20歳以上(副安全運転管理者を設置する場合は30歳) ・運転管理実務経験2年以上(同等以上の能力を有すると公安委員会が認めた者) |
選任日から15日以内に所轄警察署に届出が必要 |
| 副安全運転管理者 | 管理者の業務を補佐 | ・20歳以上 ・運転経験3年以上 ・運転管理の実務経験が1年以上 |
選任日から15日以内に所轄警察署に届出が必要 |
| 安全運転管理の業務を補助する者(補助者) | 管理者の業務を補助 | 特に資格要件なし | 届出不要(社内での明示は必要) |
アルコールチェックの確認は原則として安全運転管理者が行う
アルコールチェックの実施は、安全運転管理者の業務の一部として法令に定められています。特に中小企業では、安全運転管理者本人が運転業務も担っているケースが多く、補助者の指定や確認体制の工夫が必要です。確認業務が曖昧なまま運用されると、記録不備や監査対応のリスクが高まり、企業としての信頼性にも関わってきます。
アルコールチェックの正しい運用ルール

アルコールチェックを適切に実施するには、法律に基づいた運用ルールの理解と体制づくりが重要です。ここでは基本的な実施ルールと、企業が守るべきポイントを解説します。
運転前後にアルコールチェックを2回実施することが原則
アルコールチェックは、運転前と運転後の2回、必ず実施するのが原則です。チェック方法は、目視による確認に加えて、アルコール検知器を用いる必要があります。
対象となるのは、業務で車両を運転するすべての従業員であり、直行直帰や出張といったケースでも例外は認められません。安全運転管理者は、機器の測定結果や運転者の様子を正確に記録・管理し、確認漏れがないように徹底しましょう。
記録は1年間保存し、改ざん防止の仕組みも必要
測定結果は、確認日時・運転者の氏名・測定値などを正確に記録し、1年間の保存が義務付けられています。記録方法は紙でもアプリでもかまいませんが、不正防止の観点から、運転者本人の署名や顔写真付きでの記録が推奨されます。
検知器の定期点検と運用体制の整備も不可欠
アルコール検知器は、常に正確な測定ができる状態にしておく必要があります。週1回以上の点検や、電池残量・故障の確認を習慣化し、トラブルの予防に努めましょう。また、安全運転管理者だけではなく、副管理者や補助者も運用ルールを理解しておくことで、担当者が不在の際にも対応可能となり、現場の混乱を防げます。
就業規則にルールを明記し、違反時の対応も設定する
アルコールチェックを徹底するには、就業規則に実施ルールを明文化することが大事です。例えば「直行直帰時の遠隔確認の義務」「チェック拒否・記録改ざん時の罰則」といった具体的な規定を設けることで、従業員への理解と協力を得やすくなります。企業の安全管理責任を果たすためにも、明確な体制整備が求められます。
確認者がいない場合のアルコールチェックの正しい対応方法

アルコールチェックは原則として対面で実施しますが、確認者が不在だったり、ドライバーと離れていたりする場合も対応が必要です。ここでは、確認者がいない場面での正しい対応方法を解説します。
安全運転管理者が不在の場合は補助者や副管理者が対応できる
アルコールチェックの実施は本来、安全運転管理者の業務ですが、管理者が不在の場合には副安全運転管理者や補助者によって代行が可能です。補助者には特別な資格は不要で、あらかじめ社内で指定しておけば運用できます。ただし、測定結果に異常が見られた場合には、必ず安全運転管理者へ報告し、最終的な判断を仰ぐ必要があります。
ドライバーと確認者が離れている場合は遠隔確認で対応できる
直行直帰や出張などで、運転者と確認者が別の場所にいる場合でも、オンラインによるリアルタイムの遠隔確認によって代替することが可能です。
具体的にはビデオ通話を使って、顔色や受け答え、アルコール検知器の測定結果をその場で確認し、その記録を管理者へ報告・保存することで、非対面でも対面に準ずる対応ができます。こうした遠隔での確認体制を事前に整備しておくことで、抜け漏れのない運用が実現します。
アルコールチェックを効率化する方法

アルコールチェックの義務化に対応するには、効率的な運用体制の構築が欠かせません。ここでは、確認作業や記録管理の手間を減らし、正しい運用を実現する効率化の方法を紹介します。
クラウド連携型の測定機器とアプリを活用する
アルコールチェックを効率良く行うには、クラウド連携型の測定機器と専用アプリの導入が効果的です。運転者が検知器で測定するだけで、結果がクラウドに自動保存されるため、確認者の手作業による記録は不要になります。
顔写真付きで記録できるタイプであれば、直行直帰や遠隔地の運転者に対しても対面に準ずる確認が可能です。これにより、ミスや改ざんのリスクも抑えられ、記録の保管・管理が一層スムーズになります。
アルコールチェック代行サービスを導入する
確認者の人員確保が難しい場合には、アルコールチェック代行サービスの導入も一つの手段。運転者が専用アプリや電話で測定結果を報告すると、遠隔地のオペレーターがその内容を確認し、記録してくれる仕組みで、24時間対応が可能です。特に夜間・早朝や直行直帰の多い業務において効果的で、安全運転管理者の負担軽減にも大きく貢献します。
アルコールチェックを把握・効率化できるクラウド管理サービス「ALPiT」

「ALPiT」は、従業員のアルコールチェック結果をスマートフォンとクラウドですばやく一元管理し、安全運転管理者の負担を大幅に軽減する管理サービスです。使用する端末は電気化学式のモデルで、寿命に応じて交換用センサーや端末が自動で届くため、追加購入の手間もありません。
チェック結果はクラウド上に自動保存され、3年間のデータ保管が可能です。CSV形式での帳簿出力、基準値のカスタマイズ、飲酒検知時の自動メール通知など、多彩な機能を備えています。紙やExcelでの管理に比べて運用コストを最大3割削減できるのも大きなメリット。複数拠点の状況もリアルタイムで把握でき、企業全体の安全運転管理を効率的にサポートします。
〈ALPiTの詳細はこちら〉
https://www.irisohyama.co.jp/b2b/camera/products/alpit/
確認者がいない場面でも適切なアルコールチェックの運用体制を

アルコールチェックは、安全運転を守るための重要な義務です。安全運転管理者がいない場合でも、補助者の設置や遠隔確認の体制を整えることで、法令に準拠した運用が可能になります。さらに、クラウド管理ツールや代行サービスの活用により、業務負担を軽減しつつ、正確かつ効率的な管理が実現できます。どのような勤務形態でも対応できる体制を整えることが、安全と信頼を守る第一歩です。
※こちらに掲載されている商品情報・価格・キャンペーンは掲載日時点での情報です。
※価格は変動することがございますのであらかじめご了承ください。


