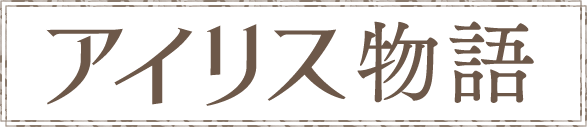アイリスオーヤマは、プラスチック製品の下請け町工場「大山ブロー工業所」として創業しました。
「アイリス物語」では、現在に至るまでのアイリスグループの歴史を連載でお届けします。
第二話脱下請けで売上100倍
「町工場のオヤジで一生を終えたくない」という強い意志を持つ健太郎は、メーカーになり自社開発した自社ブランドの商品を製造したいと考えました。当時はプラスチック自体が先端産業で成形技術が確立されていなかったので、他社の嫌がる仕事、難易度の高い仕事を受けるようにしました。また、稼いだ利益は生産設備の強化に使い、量産化と効率化を進めていきました。そして、失敗を繰り返しながらも技術を磨いていき、ついに自社製品を開発したのでした。
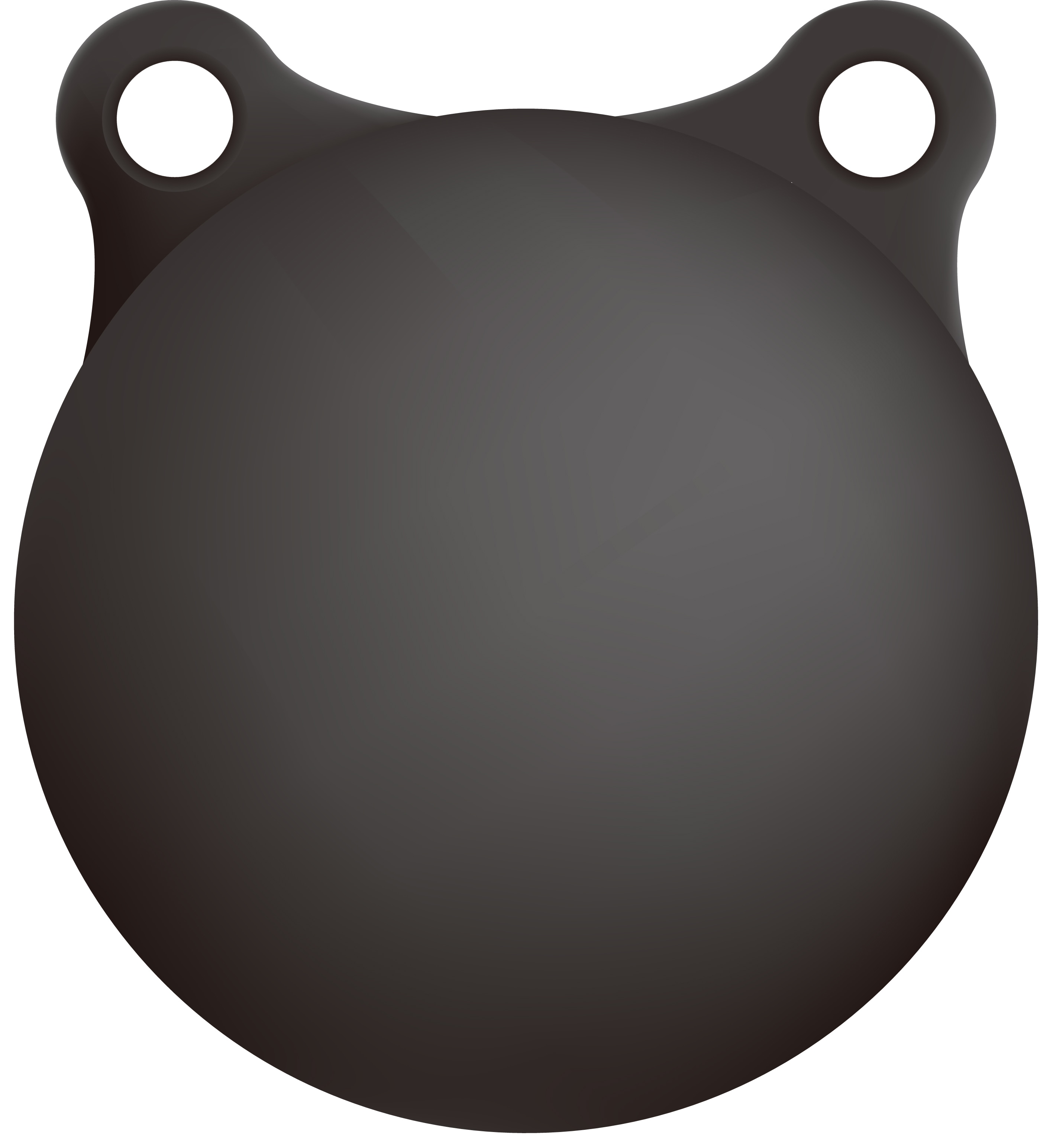
ガラス製に代わる、軽量で耐久性の高いプラスチック製の養殖用ブイ
メーカーとして独り立ちした最初の商品は「養殖用のブイ」。
健太郎が21歳の時のことです。当時、各地の海で養殖が盛んにおこなわれており、ガラス製の「浮き」が多く使われていました。ここに目を着け、割れやすいガラス製に置き換わるプラスチック製の「浮き」を開発しました。
水産業の中でもニッチな商品ではありますが、軽くて壊れにくいこのブイは待望の商品として養殖業界で瞬く間に普及する商品に成長し、今日のアイリスオーヤマの礎を築きました。
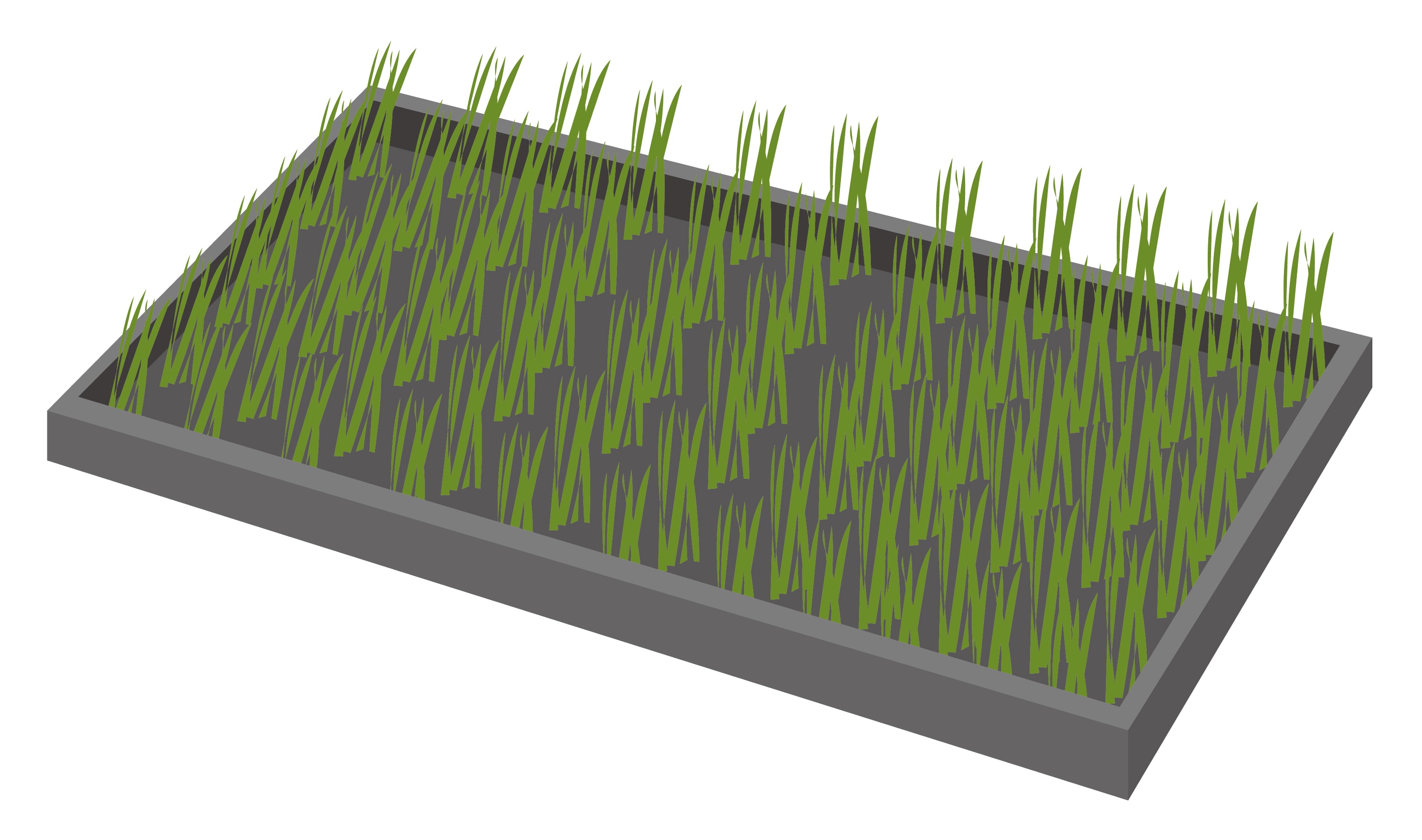
手植えから田植え機への変化に対応したプラスチック製の育苗箱
次に手掛けたものは「育苗箱」です。
1965年頃に田植え機が発明され、規格サイズの稚苗を育てるための育苗箱が必要になりました。しかし、当時使われていた木製の育苗箱は水気に弱く、耐久性も良くありません。そこで、健太郎が25歳の頃、寸法精度が高く、軽くて丈夫なプラスチック製の育苗箱を開発したところ大ヒット。
ちょうど日本万国博覧会が開催された1970年のことでした。
こうして、町工場だった「大山ブロー工業」は1971年に「大山ブロー工業株式会社」となり、代表就任当初500万円だった売上はたった7年で5億4000万円になりました。
 1971年頃
1971年頃仙台工場(現、大河原工場)建設予定地と
健太郎(左)
やがて、水産業・農業のメインマーケットである東日本からの受注が増えると、需要に近いところで商品を供給する生産拠点が必要になってきました。そこで、東北の中でも発達した物流網があり、年間降雪量が少ない宮城の地を選び、1972年、健太郎が27歳の時に仙台工場(現・大河原工場)を新設したのでした。
(第三話に続く)
- 『仙台工場』

1972年
広い敷地と最新設備が入った工場「仙台工場」竣工-
現、大河原工場(宮城県柴田郡大河原町)。
水産業・農業のメインターゲットである東日本(特に北海道・東北)への市場参入を進めるためには、東北の生産拠点が必要になった。健太郎は日本地図を開き、物流の便が良い宮城県に工場を新設することを決めた。当時、最新設備を入れた工場は150人程の従業員が働いていた。