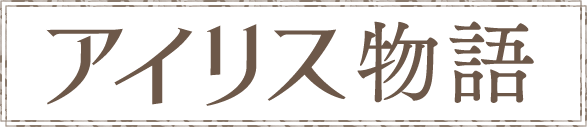アイリスオーヤマは、プラスチック製品の下請け町工場「大山ブロー工業所」として創業しました。
「アイリス物語」では、現在に至るまでのアイリスグループの歴史を連載でお届けします。
第十二話国内体制の強化、全国配送網の確立
メーカーベンダースタートの翌年となる1987年より、健太郎は全国規模の物流ネットワークを急ピッチで構築していきます。
 わずか10年で日本全国を日帰り配送圏におさめた
わずか10年で日本全国を日帰り配送圏におさめた
87年には兵庫県/三田工場、90年には佐賀県/鳥栖工場、92年には本部拠点となる宮城県角田I.T.P、94年には北海道工場と2−3年おきに工場を新設し続けます。そして、97年の静岡県/富士小山工場の完成により、主要地域のホームセンターをいずれかの工場から半径300km以内、つまり日帰り圏内に収めることに成功しました。その後2000年からの3年間で滋賀県/米原工場、埼玉工場を加え、関東・関西の大きなマーケットへの対応力を高め、配送網をより強力なものに進化させました。
 斎藤は現在、新設のアイリスフーズ(株)岩手工場の初代工場長を務めている
斎藤は現在、新設のアイリスフーズ(株)岩手工場の初代工場長を務めている
このスピード経営の最中で現場の責任者や工場長として三田工場、角田工場、富士小山工場の立ち上げに関わったのが斎藤浩です。約2年毎の転勤や中途採用者との社風や考え方の共有、機械・建物のトラブル対応など気苦労も多かったものの、その後に繋がる多くの経験を積めたといいます。「いろいろな場所で立ち上げを担当した経験は大いに役立っています。特に、苦しいときにも志をともにできた仲間は財産。どこの工場にも信頼でき、いざという時に力を貸してくれる人材がいるので助かります。」
物流ネットワークの強化に関して、なぜ「工場」の話題を取り上げるのだろうと不思議に思われるかもしれません。工場は“生産拠点”ですが、実際はどんな工場でも製品を送り出す“物流”の機能を担っています。メーカーであれば、「いかに効率よくモノづくりができるか」を考えて工場立地を決めるのが一般的です。当社も生産効率だけを考えれば、全国に8つもの工場を持つ必要はありませんでした。しかし、メーカーベンダーとして顧客ニーズに応えることを考えるとそれだけでは不十分でした。
お得意先様の立場で考えれば「売れたもの、欲しいものを迅速に供給できる」ことがより重要なはず。健太郎は、工場とは供給基地だと位置づけ、物流立地の視点で工場建設地を選定しました。従って、国内工場のほとんどは高速道路のインターチェンジ、それもジャンクションへのアクセスを意識して建設しました。
 大規模な自動倉庫群が15,000アイテムに及ぶ製品の流通を支える
大規模な自動倉庫群が15,000アイテムに及ぶ製品の流通を支える
また、各工場には大規模な自動倉庫システムを導入しました。コンピューター制御された機械が自動で入出庫する倉庫です。現在では国内合計26万パレットを超え、国内最大規模の自動倉庫を運用する会社に成長しました。この自動倉庫を活かし、各々の工場では取扱アイテムを限定せず、全てのアイテムが在庫できる仕組みになっています。これらの取組みについて健太郎は、「物流センターのなかに工場を作っている」と表現。ユニークな発想としてメディアにも多数取り上げられました。
当時、営業として東海地区のホームセンターを担当していた石井英夫は当時を振り返りこう語ります。「三田工場ができる以前は大河原工場から3日間くらいかけて納品していました。『メーカーベンダー』とはいうものの、まだまだ他のベンダーの物流サービスにはかなわない面がありましたが、三田工場ができたことで翌日配送が可能になり、営業がしやすくなりました。それまでお客様にはケース単位での発注をお願いしていましたが、物流の人員が増え細かなアソート出荷にも対応できるようになりました。メーカーベンダーに変わったことが実感できるようになりましたね。」
この全国をカバーする強力な物流体制あってこそ、消費行動の「ネットシフト」等の人々のライフスタイルの変化にも、ネット通販事業の強化などで素早く対応できたのです。
(第十三話に続く)
- 運賃をシビアに見積もり、「納品してみたら赤字」をなくす
- 当時メインとしていたプラスチック製品は単価の割に容量が大きく、運賃については以前からシビアに管理していましたが、全国配送網を確立したことで運賃が平準化できました。 一般的に運賃や保管費は販管費として計上されますが、当社は単品の製造原価に運賃などを加えた販売原価を用いて単品利益計算をしています。製品は原材料費、人件費、設備費など製造費用に加え、予め運賃や保管費も細かく計算し開発されます。製造原価は黒字、しかし納品してみたら赤字だった…ということはあり得ないのです。