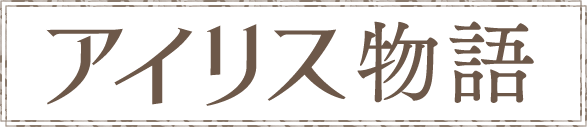アイリスオーヤマは、プラスチック製品の下請け町工場「大山ブロー工業所」として創業しました。
「アイリス物語」では、現在に至るまでのアイリスグループの歴史を連載でお届けします。
第十四話中国への進出〜中国愛麗思グループの始まり
 大連周辺図
大連周辺図
1980年代後半から中国は、国策として「改革開放政策」を掲げ、外国の企業や資金を積極的に受け入れ始めました。そしてその傾向は90年代中盤以降急速に強まります。95年、中国国内を回った健太郎は帰国後すぐに中国進出の計画を練り出しました。成長著しい中国に対して、非常に高い可能性を感じたのです。進出先として検討したのは大連・青島・上海の三都市。土地・建物代や人件費、物流効率、税制面の優遇措置など多面的に検討した結果、健太郎が選んだのは大連でした。仙台―大連間を定期便が就航していたこと、日本語の話せる人材が多く親日派が多いことも理由となりました。
1996年に「大連愛麗思欧邪馬工貿有限公司」が設立され、翌年1月に工場が竣工。プランターや猫用トイレといった小・中型成型品、ホースリールや噴霧器などの組立品を中心とした生産が始まりました。 大連で新規採用されたスタッフには、原料や設備に関する知識は殆どなく、ガーデニングをする、ペットを飼うという習慣もありませんでした。大連工場成功の可否は彼らをいかに教育するかにかかっていました。

機械操作や安全衛生など、教えなければいけないことは山積みでした。もちろん工場に通訳はいましたが人数は限られ、常に日本人スタッフのそばにいるとは限りませんでした。日本から出向したスタッフ達は現場で指導することを重視し、身振り手振り、手取り足取りの指導で品質や技能を高めていきました。良品・不良品の判断基準を合わせるのには特に苦労し、製造現場に不慣れな中国人スタッフが工場内で大きな事故に遭ってしまったこともありました。二度と起こらないよう、その後は設備に細かな注意事項を掲示するなどの環境整備を行っていきました。
このように習慣や経験の違いを理解し、仕組みや環境の整備をする一方で、人間関係においては「国の違いを必要以上に意識せず、構えずに接したのが良かった」と初代工場長の時津は振り返ります。「他の企業の日本人駐在員は、日本人同士で集まって日本食を食べることが多いようです。当社の駐在員たちは中国人スタッフに混じって同じ食事を取ることでコミュニケーションを深めました。中国人スタッフは勤勉な人材が多く、日本語の習得の速さには驚きました。寮の周りに何もなく、空いた時間は勉強するしかなかったのかもしれませんが(笑)」(時津)
また、健太郎は教育を大連工場任せにせず、日本(角田工場)でもしっかりと研修を行うこととしました。日本同様の管理手法や品質基準、モチベーションで工場運営を行うために、2カ月から半年の間、実務や日本語、仕事に臨む姿勢や企業理念などについて教育をしました。また、店舗を見学させるなどして日本の品質基準を理解させました。一方、慣れない土地、言葉の壁や習慣の違いから中国人研修生がストレスを抱えないように、休日には毎週のように観光バスをチャーターして観光地に連れていくなどの配慮をしながら長期間の研修を進めていきました。
大連工場稼働当初は、品質が不安定だったり資材調達に失敗してしまったりと様々な問題に見舞われました。しかし、日本人駐在員と現地採用の中国人社員が信頼関係を築き、また日中双方での教育に力を入れてきたことで一つ一つ問題が解決でき、現地に任せる経営が可能になりました。こうして、グループ全体の大きな強みとなる中国での生産体制が作り上げられていったのです。
(第十五話に続く)
- 経営の現地化進む中国グループ
-

- 1996年の中国進出当時は約500名の現地従業員に対し、約50名の日本人社員が働いていました。現在、現地従業員は約4000名に増えましたが、日本人社員は約15名で、グループ総経理にも中国人社員を登用しています。