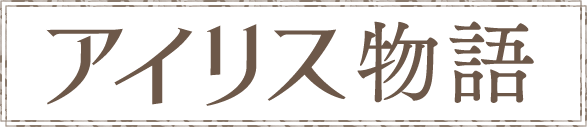アイリスオーヤマは、プラスチック製品の下請け町工場「大山ブロー工業所」として創業しました。
「アイリス物語」では、現在に至るまでのアイリスグループの歴史を連載でお届けします。
第二十四話LED電球の市場創造について(上)
“2,500円で売れるLED電球を作れ。”健太郎が開発担当者にそう指示したのは、2009年11月のことでした。先行する電機メーカーが10,000円近い価格で販売していた時代。当社は同年夏に市場相場の半値にあたる5,000円のLED電球を発売していましたが、更にその半値とは―。開発マネージャーの小野は仰天しましたが、健太郎の発想は至ってシンプルで合理的でした。
 電源設計課/小野
電源設計課/小野
世の中は確実に二酸化炭素の削減や省エネの方向に向かっていましたが、100Wの白熱電球が数百円で買えるなかで、高価なLED電球を使おうと考える人はよほど意識の高い人だけ。しかし、2000円台のLED電球が開発できれば10年使えて、1年で元が取れる。そうすればより多くの人々に受け入れられるものとなるはずだ、と。
さらに、健太郎からは指示がもうひとつ。“発売は、4か月後の3月。”理由は簡単で、電球が売れるのは3月と12月だからです。翌12月ではなく、困難が想定されようとも目前の3月をターゲットにする点が、アイリスオーヤマらしさと言えるでしょう。
このように生活者視点で価格や発売日を真っ先に“決め”、実現するにはどうするか知恵を絞る「引き算方式」がアイリスオーヤマの流儀。多くのメーカーにおいて、価格や発売日が原価や期間を足し算するなかで“決まる”のとは非常に対照的です。
“2,500円、3月発売”を実現できれば、業界にインパクトを与えられることは確実でした。しかし、採算を度外視して業界シェアばかりを追うようなことをしてはほどなく撤退を余儀なくされてしまいます。事業として永続させていくためには、利益もしっかりと残さなければなりません。開発を命じられた小野たちは、イルミネーションライトで培ったノウハウをベースに必死に工夫改善を積み上げました。回路の構造や部品を一から見直し、さらに筺体に用いるアルミの量を抑えられる形状や工法を考案し、苦心の末に目標の価格を達成することができました。
また、安価だからといって性能が劣ればお客様に満足頂くことはできません。品質の作り込みにも余念はありませんでした。電球に流れる電流は全てが光になるのではなく一部は熱に変わります。この熱はLEDチップや電源回路の寿命に影響を与えるため、いかに効率よく熱を逃がすかがポイントです。小野たちは電球に何度も負荷をかけ、業界水準以上の性能が出なければ再設計・改善を繰り返しました。
 遂に完成した
遂に完成した2,500円のLED電球
そして、約4カ月に渡る集中的な試行錯誤の結果、“1年で元が取れるLED電球”がついに誕生。製品発表会にはイメージキャラクターとして歌手・小林幸子さんも登場。小林さんが舞台演出での電球の使い過ぎを反省し、「エコバヤシサチコ」へ変身するというユニークなTVCMも話題になり、販売は好調に推移しました。
しかし、この時点ではまだ販売は“爆発的”ではありませんでした。真の発火点となったのは、その後も研究開発を継続していた小野たちが送り出す“1,980円のLED電球”が登場する、8か月後のことでした。
(第二十五話に続く)