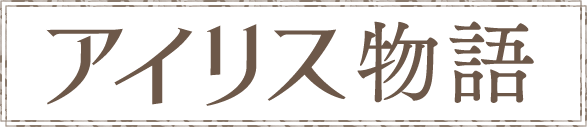アイリスオーヤマは、プラスチック製品の下請け町工場「大山ブロー工業所」として創業しました。
「アイリス物語」では、現在に至るまでのアイリスグループの歴史を連載でお届けします。
第八話メーカーベンダーの始まり
1980年代半ば、ホームセンターとの直接取引によってアイリスオーヤマは大きく売り上げを伸ばしていました。しかし、直接取引は新たな問題を生んでいました。それは、『出荷形態の変化』でした。問屋だけの取引であれば商品は「ケース単位」の出荷であったのに対し、大きなバックヤードを持たないホームセンターとの取引は、売り場で売れた分だけの発注という「商品1個単位」の発注形態になっていました。
当時の出荷形態は、鉢受け皿であれば「1箱60個」入りからの注文で、問屋からは「60個(1箱)」「120個(2箱)」の注文が通常出荷できる形態でしたが、ホームセンターからは「1個」「2個」の単品注文となり、いわゆるアソート出荷となっていました。加えて、「値段を付けてからの出荷」や「専用伝票の記入」等、注文が増えると同時に、ホームセンターからの要望は増えていきました。また、直接取引により問屋を外すことは日本の商道徳に反すると非難され、問屋にあった在庫は不良品であっても返品を受けざるを得ない状況に陥りました。
これに一つ一つ対応していかなくてはならない営業や物流部門からは悲鳴が上がり、「問屋経由に戻すべき」や「出荷単位を大きくしてもらうべき」など、社内の意見は割れていました。
 当時のミーティングの様子
当時のミーティングの様子
健太郎はここでも大きな決断をします。「問屋機能も自社で受け持とう!」というある意味とんでもない発想をしたのでした。
「メーカー」と「ベンダー(問屋)」を一つの会社・工場で受け持つこんなことが果たしてできるのか。こうして、他に例がなかった「メーカーベンダー」がスタートしました。
現在の流通のチャネルでは多様化していますが、以前は、生産者から卸売業者、そして販売店というのが一般的なチャネルでした。
アイリスオーヤマのメーカーベンダーシステムは、卸売業者を抜いてメーカーが販売店に直接的に商品の提供をし、つまり、生産者が卸売業者の役目も果たすということです。
問屋を省くことによって、中間流通の段階で発生するコストをトータルでダイナミックに削減することができます。これが価格競争力のある商品開発力を生み出し、販売店とメーカーの適正な利益の確保を可能にし、商品の価格を抑えるというメリットを生み出しています。
また、生産者が直接販売と接点を持つことによって、販売店の生の情報を吸収するという大きなメリットにつながります。当然、お客様のニーズも収集しやすくなります。
商品をつくって売る際に、もっとも無駄なのが問屋を通すことによって発生する“商流”コストです。物流も含め、中間流通上の無駄を省き、同時に在庫を削除するためには、手間はかかっても、自社でベンダー(問屋)機能の役割を果たすべきだと健太郎は考えます。
アイリスオーヤマには当初から販売店との直接取引を基本とする商売を通じてのベンダーとしてのノウハウの蓄積があります。この蓄積を生かし、戦略的にベンダー部門の強化を図り、メーカーベンダーという明快な経営スタンスを打ち出しました。
(第九話に続く)
- メーカーベンダーのしくみ
-
第四話のコラムでもご紹介しましたが、ここではメーカーベンダーのシステムについてご紹介します。
メーカーベンダーシステムは、商品を小売店に届けるだけでなく、小売店の売場をコンサルティングしながら魅力的な売場作りや販売促進をサポートし、生活者の声がダイレクトにフィードバックされる、生活者ニーズに対応したオンリーワン商品のスピーディな開発を可能にしました。 - 『メーカーベンダーシステム』について ≫