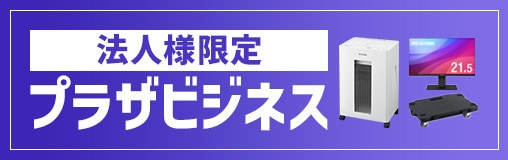vol.18
vol.18
-
いまこそピンチをチャンスに
-
 アイリスオーヤマ株式会社
アイリスオーヤマ株式会社
代表取締役 会長 大山 健太郎
1945年生まれ。父親の死去に伴い、大阪のプラスチック加工会社である大山ブロー工業の代表に19歳で就任。以来、約50年にわたって社長を務め、園芸用品や収納用品、家電製品などに事業を拡大。2018年に長男・大山晃弘に社長職を譲り、現職。
こういう時こそ積極的に投資を
当社は、政府からの要請を受けてマスクの国内生産を6月から開始しました。順次生産ラインを立ち上げ、月産2億3000万枚の供給体制が整います。マスク用の資材設備も導入し、国内で一貫生産を行うことになりました。世界の市況に左右されないでマスクの販売価格を維持していきたいと考えており、高品質のマスクを安定供給するために、積極的に設備投資することで社会貢献をしていきたいと考えています。当社の企業理念の第1条は「いかなる時代環境に於いても利益の出せる仕組みを確立すること」です。私は、オイルショックの時に倒産寸前を経験しました。私は会社を絶対に潰さないと強い覚悟を持って経営をしています。まだ会社が小さな時から毎年、経常利益の半分を必ず投資に回してきました。設備に余裕を持たすためと商品のアイテム数を増やすためです。当社の稼働率は常に約7割ですが、効率を優先するなら稼働率が高いほうがいいに決まっています。製品群も広げず、得意なものに絞れば効率が良い。しかし、平時はそれで強くても有事の時に受けるダメージはとても大きくなります。今回のマスク生産設備の導入をスピーディーにできたのも、工場のスペースに余裕があったからなのです。
「機を見るに敏なり」ピンチをチャンスに
当社はこれまでさまざまなピンチに直面してもチャンスと捉えて、商品や事業展開で会社を成長させてきました。現在、当社の主力事業に成長した家電事業が本格参入した2009年は、技術者を含めた早期退職者を募る大手家電メーカーが増えた時期でした。家電事業を海外家電メーカーに売却するケースもあり、家電業界が弱体化する状況を目の当たりにして、日本の技術流出を防がなければならないと考えました。そこで数多くの優秀な技術者がいる大阪・心斎橋に家電の開発拠点を新設し、早期退職した技術者を積極的に採用することで当社の家電事業は年々品揃えが拡大し、現在では全社売上の59%を家電製品が占めるまでになりました。また、2011年に発生した東日本大震災では当社も被災しましたが、農業の復興なくして東北の復興はないと考え、被害を受けた多くの農家の皆さんのお力になりたいと宮城県亘理町に精米工場を建設しました。東北のおいしいお米を低温で精米し、簡単・便利・美味しいをコンセプトに2合の個包装にして発売しました。現在では、そのおいしさの認知が広まり、大手スーパーやホームセンター、コンビニエンスストアでも販売することができています。そして何より、当社のLED照明事業もピンチをチャンスに変えた事例の一つです。東日本大震災直後、計画停電が行われ、節電は日本全体の課題になりました。そこで当社は、LED照明を一気に増産し、節電ができて明るいLED照明を日本に広く普及させることができました。お陰様で今年、5年連続6度目の省エネ大賞を受賞いたしました。現在では、家庭用のLED電球やシーリングライト、BtoBビジネス向けのLED照明など品揃えも拡大し、主力事業になりました。これにつながるように、アイリスグループの強みを活かし、シナジー効果を発揮してBtoB事業は広がっています。
景気は必ず上向く苦しい今こそ雇用を大切に
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大で大変な思いをされている方が多くいらっしゃると思います。これまで、およそ10年単位で想定外の危機がやってきました。バブル崩壊、金融危機、リーマン・ショック、東日本大震災。しかし、次の危機がウイルスとは予測できませんでした。日本のGDPの約6割が個人消費です。消費低迷によりGDPがマイナスになることはあり得ますが、長期間にわたって大幅に落ち込むとは考えにくいと思っています。いまは消費が戻ってきた時のために人材教育、体質改善をする時間にしましょう。料理店なら、もっとおいしいものをいかに早く作るかを考えましょう。ホテルなら、どんな運営の仕方をすれば効率的で、お客さまにはこれまで以上に満足してもらえるサービスができるか、社員と共に知恵を出し合うのもいいでしょう。これまでサービス業は人手不足で大変だったでしょうから教育にも時間がかけられなかった分、いまやるべきです。今年の消費が7掛けなら、来年は8掛けなのか、9掛けかは分かりませんが、必ず消費は上向きます。いまは大変かも知れません。しかし、日本の少子高齢化による慢性的な人手不足は変わらないのです。 東日本大震災の後に見てきたことですが、目先の赤字に対応するために社員を解雇した企業は、復興需要が発生した時に採用難で十分な人手を確保できず結果的に事業の回復が遅れてしまいました。一方で、最も苦しい時期に我慢して雇用を守った企業は社員のロイヤルティーが高まり、素早く復興することができたのです。今回のコロナショックでも、人員を減らさず我慢すべきです。日本の上場企業は自己資本比率が高いのですが、こうしたときにこそ雇用維持に使ってほしいと私は思います。企業の厚い財布を使って、社員つまり消費者の財布を守ることが大切です。借り入れをして赤字を出してでも雇用を守ることこそ、日本的な経営の基本であり最大の社会貢献だと私は考えています。
働き方、生活スタイルの変化で地方にもチャンス
コロナショックでは働き方が変わりました。当社でも大都市圏を中心に一部でリモートワークを実施しましたが、今後は時差出勤やリモートワークが定着していくと思います。リモートワークによる在宅での仕事が定着し、首都圏に本社を置く企業もバックアップオフィスとして地方に移転するのもいいでしょう。そして、地方もこれを促進すべきだと思っています。地方創生にもつながっていきます。また、流通の形態も大きく変わりました。家電製品や日用品が主力の当社ネット通販に関していえば、大都市で製品を作って全国に供給するよりも地方都市に本拠を置く方が競争力は高くなります。今こそ地方企業がネット通販への本格展開を考えるべきだと思っています。地域の特色ある商品や企業にとっては、まさにチャンスです。
-
6月から不織布マスクの国内生産をはじめた、宮城県・角田I.T.P.(かくだアイ・ティ・ピー)。今後はマスク用資材である不織布などの資材製造設備を導入予定。中国2工場と合わせて月2億3000万枚の供給を目指します。 
-

東日本大震災直後、被災した角田工場をすぐに復旧することで生活用品の供給を継続。 
新型コロナの感染拡大抑制を目指し、映像をもとに発熱者を検出できるAIサーマルカメラを発売。医療機関、商業施設などのニーズに対応しました。
オンリーワンをたくさん持つ
当社にはたくさんのオンリーワン商品があります。皆さんもオンリーワン商品を1つではなく、たくさんのオンリーワン商品を持つのが良いと思います。最初は2つ。次に3つ。一歩ずつでいいのです。私も中小企業だった頃から、時間をかけながら一つひとつアイテム数を増やしてきたのですから、皆さんも絶対にできます。コロナショックで大きな打撃を受けている会社は、主力商品やサービスのジャンルが限定的なのかもしれません。これを機にリスクヘッジした経営に転ずれば、会社はぐっと強くなるはずです。効率の追求は大切ですが、それだけではいけません。ロングセラー商品に傾り過ぎると会社をダメにします。真の効率とは何かを考えることこそ、本当の意味でコロナ危機を乗り越えるということなのかもしれません。
お客さまとともに課題解決できるパートナーに
当社はこれまで社会の流れをいち早く読み取り、顧客ニーズに迅速に対応してきました。今回のコロナショックではお客さまの経済活動再開に向けて、映像をもとに発熱者を検知できるAIサーマルカメラをはじめとする商品開発を最優先で行いました。社内ではWeb会議などのシステム環境の整備を行い、遠隔でも意思疎通が図れるようにしました。その結果、当社の特長である全国60拠点の地域密着型ダイレクトマーケティングがより強化されました。このWeb会議システムを活用すれば、専門知識を持った開発者が遠隔で打ち合わせに参加でき、お客さまのニーズに対して技術的な見地から課題解決に導くことができます。それぞれの地域・業種でニーズは異なりますので、そのニーズを顕在化させ、当社の総合力で応えることが私たちの使命だと考えています。これからもどのような困難に直面するか分かりません。しかし、当社は今後も社会の変化に柔軟に対応し、お客さまに寄り添い、一緒に課題を解決できるパートナーでありたいと考えています。
バックナンバー
-
new
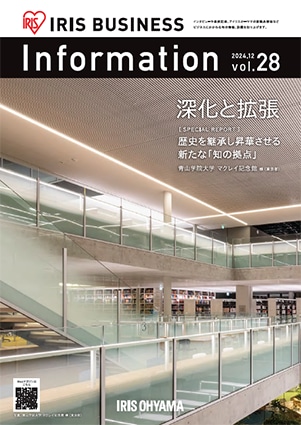 vol.28
vol.28
2024年12月号 -
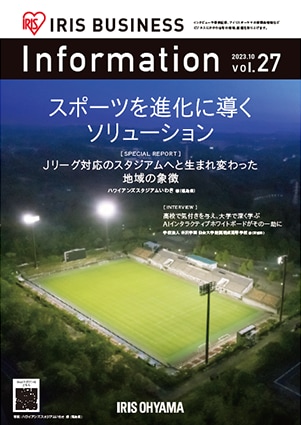 vol.27
vol.27
2023年10月号 -
 vol.26
vol.26
2023年5月号 -
 vol.25
vol.25
2022年12月号 -
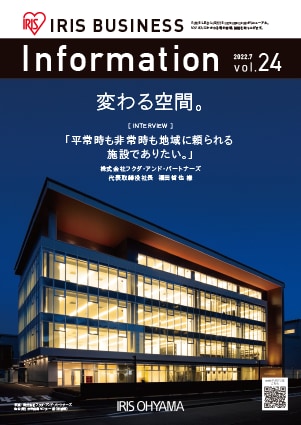 vol.24
vol.24
2022年7月号 -
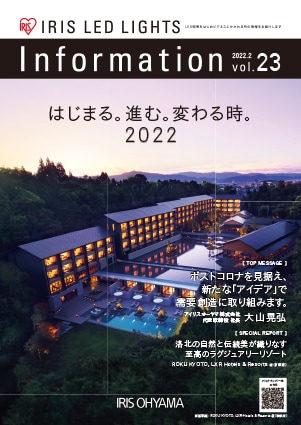 vol.23
vol.23
2022年2月号 -
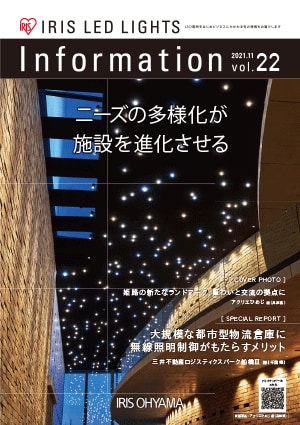 vol.22
vol.22
2021年11月号 -
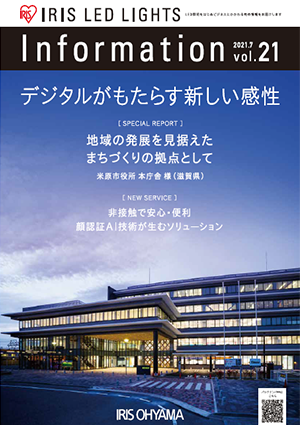 vol.21
vol.21
2021年7月号 -
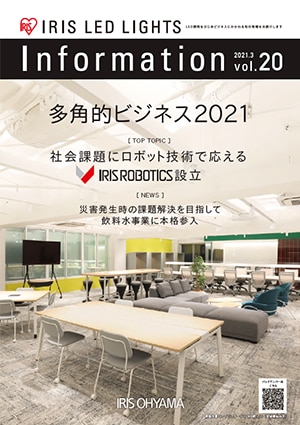 vol.20
vol.20
2021年3月号 -
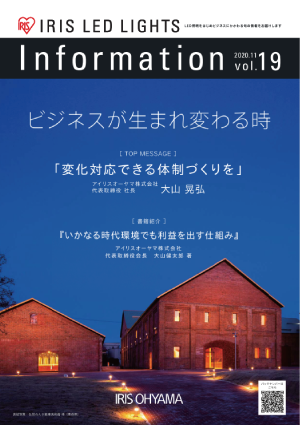 vol.19
vol.19
2020年11月号 -
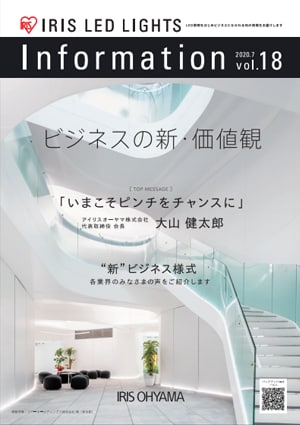 vol.18
vol.18
2020年7月号 -
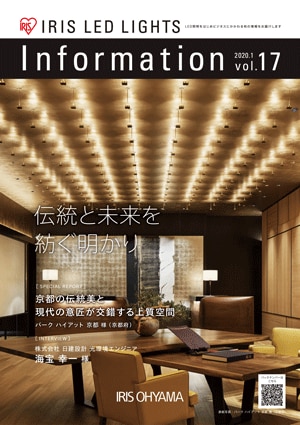 vol.17
vol.17
2020年1月号 -
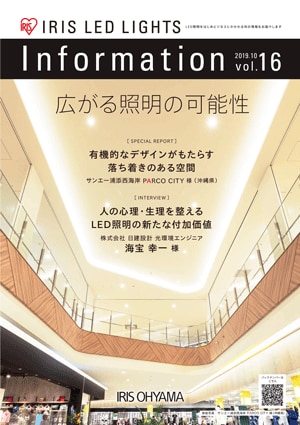 vol.16
vol.16
2019年10月号 -
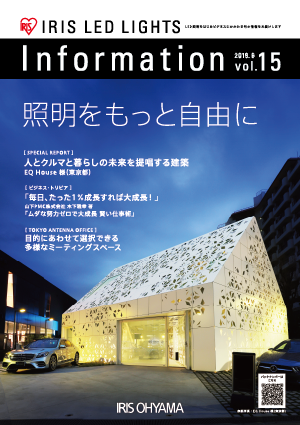 vol.15
vol.15
2019年6月号 -
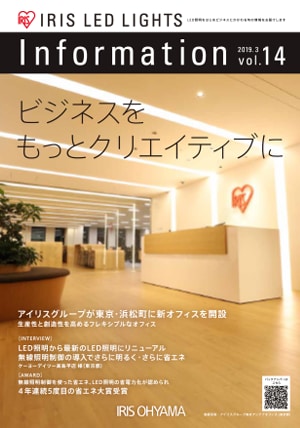 vol.14
vol.14
2019年3月号 -
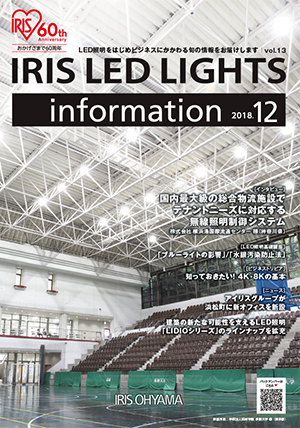 vol.13
vol.13
2018年12月号 -
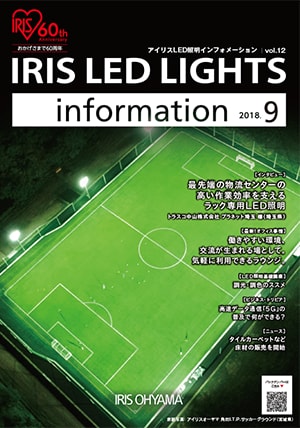 vol.12
vol.12
2018年9月号 -
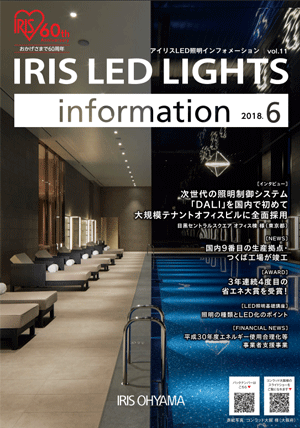 vol.11
vol.11
2018年6月号 -
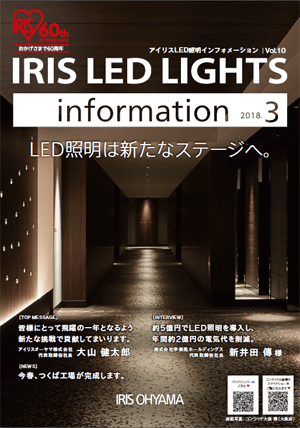 vol.10
vol.10
2018年3月号 -
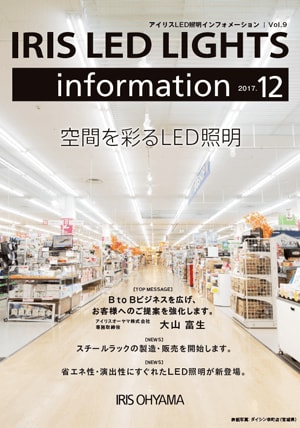 vol.09
vol.09
2018年3月号 -
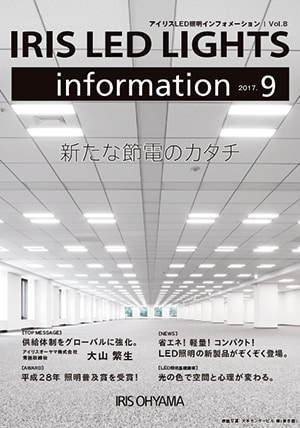 vol.08
vol.08
2017年9月号 -
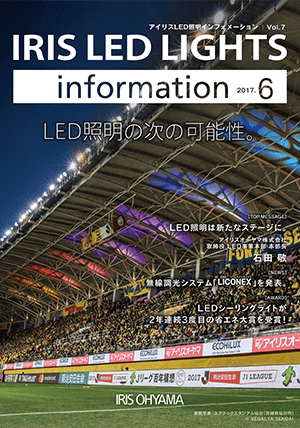 vol.07
vol.07
2017年6月号 -
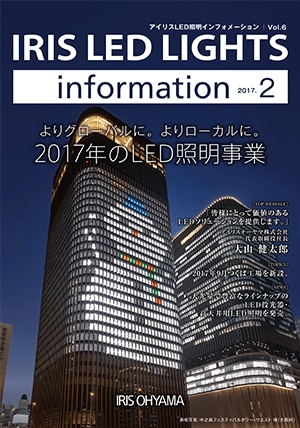 vol.06
vol.06
2017年2月号 -
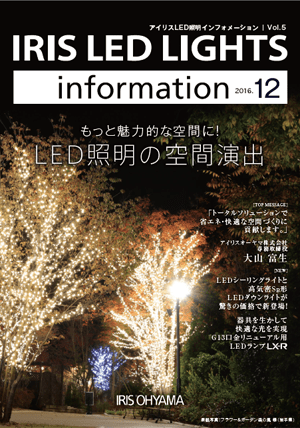 vol.05
vol.05
2016年12月号 -
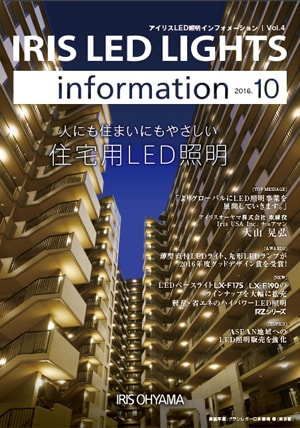 vol.04
vol.04
2016年10月号 -
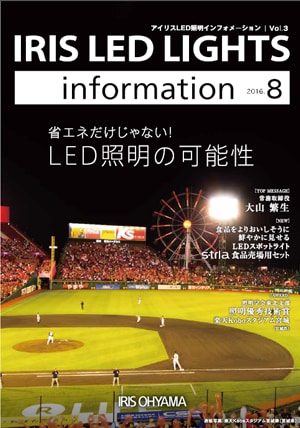 vol.03
vol.03
2016年8月号 -
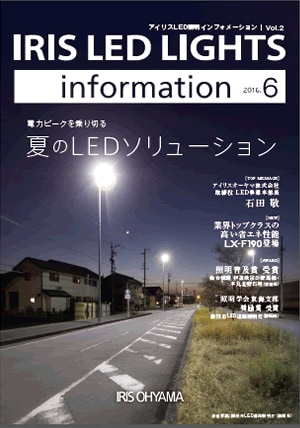 vol.02
vol.02
2016年6月号 -
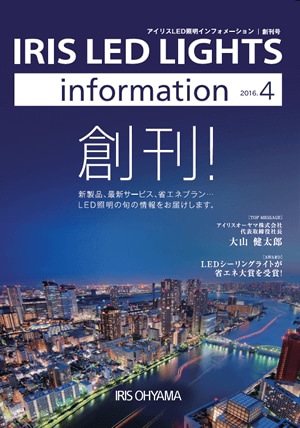 vol.01
vol.01
2016年4月号